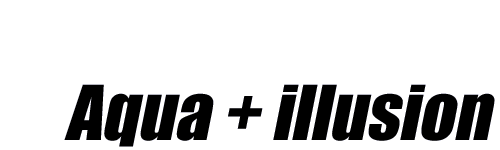
01. あたしと「とわの瞳」
「まさき……。こら、まさき!」苛立ちのこもった声色になる。「まさき! 起きなさい、遅刻よ!」
「う〜ん、今、何時〜?」あたしは布団を頭からかぶったまま、寝ぼけ半分に目覚まし時計を探す。左手は無意識に枕を抱え、右手が時計をめがけて虚しく空を切る。と、固いものが手に当たり、あたしはそれを自分の方に引き寄せた。「……はち時いっぷん? ……」
心臓が口から飛び出すくらいに驚いてあたしはベッドから跳ね起きた。ついでに長いサラサラの髪の毛が視界を遮って、勢い余って転がり落ちた。
「ちょ、お母さん! どうしてもっと早く起こしてくれないの! いっつも七時過ぎには起こしてっていってるのに。もう、八時すんじゃったじゃない、絶対に遅刻よ。センセに怒られたらお母さんのせいだからね!」
パジャマを脱ぎ捨て、あっという間に着替えていく。壁のハンガーから黒いセーラー服をもぎ取るようにして外すと歩きながら着始める。朝の陽射しが何だか憎い。
「何、ばかなこと言ってるの。七時から一時間も叫んでるお母さんの身にもなりなさい! まったく、まさきは。起こせと頼んでおいて、まともに起きたためしがないんだから」
「そんなこと言ったってぇ〜、眠いんだから仕方がないじゃない」
あたしはそう言いつつ、階段を駆け降り、上り口から目と鼻の先の台所に飛び込んだ。お母さんも毎度のことと心得ているようであたしが顔を出すのと同時に、トースターから焼き立てのパンを取り出し手渡した。
「ほら、パン。朝ご飯、のんびり食べる時間はないでしょ。朝抜きは良くないからそれでもかじりながら学校まで走りな! まさきの足ならまだ何とかなるんじゃないの?」
「ムチャ、言わないでよ」あたしはまだ熱いパンを頬張りながら、靴を履く。「あたし、長距離走者じゃないの。百メートル十三秒台で走れても、二キロは無理。ついでに心臓破りの坂が控えてるんだよ。あたし、華奢な作りしてるから」
「そんなこと喋ってる暇があったら、さっさと行け!」
もどかしいあたしにお母さんは苛立ちを隠せない様子で蹴飛ばすふりをした。
「きゃん!」あたしは両手でお尻を押さえて微笑んで見せる。そして、振り返って鞄を取ると出かけようとした。「ひどいじゃないの、お母さん」
「はああぁ? 蹴ってないでしょう。まったく、我が娘ながらいやになるわ」
「ふふっ」悪戯っぽい笑みを浮かべ、パンを掴んだ手を振る。「じゃね」
「やっと行ったか、バカ娘。毎朝毎朝、懲りもせずによく朝寝坊できるねぇ。誰に似たんだか」
「え? 何? 何か言った」
扉の閉じかけた玄関口からパンをくわえてあたしはひょこっと顔を覗かせた。
「何も言ってないよ。いいから急がないと本当に遅刻するでしょ」呆れた顔でお母さんは言った。
「ホント? 私のこと呼ばなかった? まさきって」
「呼んでない! くどいよ、まさき」それから大きく息を吸い込んだ。「とっとと行け! このバカ娘。予鈴まであと十分。さあ、カウントダウンだ。せっかく頑張った皆勤賞がぱあになるよ!」
「え? あ、ホント? やっば〜!」
でも、あたしの足ならまだ余裕だな。玄関前でう〜んと伸びをして、軽くストレッチ。鞄を肩から掛け直してよし行くか。柊まさき。レディーゴー。と、思ったらがっことは反対方向からゆうやがのんきに現れた。
「よっ! まさき。今日もまたがっこまでダッシュなのか?」
「あら、ゆうや」あたしは目をパチクリ。
「こりねぇ女。これで、二年半も皆勤だってんだから驚きだよ」
「巧みな計算と言ってちょうだいよね」
「そおなのか?」ゆうやは意外そうに目を真ん丸くしてあたしの瞳を覗き込んだ。
「あたしのこと、何も考えてないおバカだと思ってたんだ。ふ〜ん。そうなんですかぁ。いいこと聞いちゃった。……後でどんなことになっても知らないかんね!」
「ほお。出来るものならやってみなよ」今日はやけに挑戦的だぞ。
「いつからあたしにそんなこと、言えるようになったんだ?」
「今日から。と言うより、今日だけかも」
「はぁ?」思わずに裏返った声が出ちゃって恥ずかしい。
「じゃあ、一回だけ言うからちゃんと聞いておけよ」
何を? と言わんばかりにあたしはゆうやの顔を訝しげに覗いていた。
「今日の帰り、美術館に行こうぜ。まさきの見たいって言ってた例の秘宝がようやく来たらしいぜ?」出来る限り爽やかに言ったんだろうけど、どこかぎこちない。
「あの、まさか、その一言のために塀の陰で待ってたんじゃないでしょうね?」
と言うと、ゆうやは図星だったのか、ドキッとしたように仰け反っていた。
「呆れたぁ。そんなのがっこで言えばいいじゃん」
「だって、クラスのみんなにばれたらデートだってうるさいし」
何を今更という気がしないでもない。クラスのみんななんて向こうで勝手に“出来てる”って思ってるから、二人でどこ行こうと驚きも冷やかしもしないのに。
「まぁ、それはいいや。で」あたしは腕時計をちょんちょんと指さした。
「何?」ゆうやはあたしの時計を覗き込んだ。「八時半ですか……。本鈴まであと十五分ですねぇ。――走れ、まさき! レディーゴー!」
「あっ! ゆうや、抜け駆けはずるい。それにそれはあたしのかけ声だ」
怒鳴りながらあたしは先に行ったゆうやを追っ掛けた。
放課後。あたしはがっこの玄関ロビーの安っぽいソファに座って、ゆうやを待っていた。けど、来ない。市の美術館の閉館時間は五時のはずだから、ゆっくり鑑賞している時間がなくなっちゃうよ?
「よっ! まさき。進路指導の大河に捕まっちまって」
手を振りながら余裕綽々でゆうや登場。
「遅いヨォ」あたしはふくれっ面。「それにセンセと今更何を話すって。ゆうやは一流理系大進学三重丸で安心なのにぃ」羨ましい光線を浴びせかける。「あたしなんかどうするの。怖くて怖くて、お父さんとなんて会話も出来ない……」
「でも、その分まさきは自由でいいよね」急に淋しそうな色を湛えてゆうやが言う。
「なぁに言ってるの? あたしなんかうちに帰ったら修羅場よ、毎日。高校卒業したらぷらぷらしてるつもりなのかって。そんな……つもりはないんだけどさ」
気がつけばあたしの右足はポンと一つ空を蹴っていた。
「そ、言えばいつか言っていたね。大きなズダバックしょってあちこち歩いてみたいって。けど、今日はこの話やめね。語り出したら終んね」
「でも、あたしにそんな勇気ない。いけるだけの勇気があったらもういないよ」
正直、そうに違いなかった。もどかしかった。最初の一歩さえ踏み出してしまえさえしたらもうどこまでだって行けるような気はしてのに。立ち止まったあたしは歩き出せない。怖かった。何もかも捨てないとあたしはいけない。捨てたあと、また色々拾っていけるのかがとっても不安だった。
「ま・さ・き。行くぜ」ゆうやに背中を叩かれて、あたしは立ち上がった。
「行くか!」あたしは微笑んだ。
こんなことは今考えることじゃないんだ。うちに帰って、窓を開けて、夕暮れに赤く染まった空を見上げながらゆっくり考えるんだ。きっと、今日も結論は出ない。でも、切っ掛けさえあればあたしだって。ぎゅっと唇をかんで涙をこらえた。このことを考えるとあたしはいつだって泣きたくなった。
「涙ぐんでるぜ、まさき」
「! コラァ。気がついてても口に出すなよな。声上げて泣くよ……」
「おいおいおい、それは勘弁な。いつだったかは知らない人にお巡りさんまで呼ばれてえらい目にあったんだぞ。覚えてないのか?」
「覚えてるよっ。だから」あたしは左手の甲で涙を拭いた。
「ホントなんだろうかね。この女」ため息まじりにゆうやは言った。
「ホントだよ」この件についてはあたしは全然信用がないらしかった。
それから、あたしたちは玄関前の五十七段の階段を駆け下りた。がっこは千メートル級の山の麓にあって、山を削った場所に建っていた。だから、四階の教室から街を見下ろすととっても眺めがいいんだ。これはここの生徒、千五百十八人の特権! 冬になると粉塵が空を覆って茶色く見えるんだけど、それまではとても素敵で、よく晴れた日なんかは近くの海や、二百うん十キロもはなれた山系がくっきり見える。
「ねっ! ゆうや」
「何が『ね』なんだ?」
「ううん」あたしは首を大きく横に振った。「何でもない」
「変なやつ?」と言いつつも、別段おかしがっていないのがゆうやのいいところ。と言うか、高校に入ってからずっとの付き合いだからいいかげん慣れてるのかな。
ともかく、がっこから美術館に行くには高速道路の下をくぐって、二キロほど坂を下って近場のJRの駅から電車で三駅ほど。時間にしたら十分くらいでそこからまた二十分は歩くんだ。これ全部市内駅だから田舎と言っても結構大きな街だよね。
「まさき、よそ見してるとはぐれるぜ?」
「大丈夫だよ。あたし、ゆうやと違って方向音痴じゃないし、土地勘あるから」
「へぇへ。俺はそんなに頼りないのかい」
「ええ、ことのほか、ナビゲーションに関しては」あたしはイーッとして見せた。
「――否定できねぇ」がっくり肩を落としてる。
そ、この間なんていつもの通学路から少し入っただけで道に迷っちゃったんだから。
「でもな? 今日は絶対、大丈夫だ!」ほう、やけに自信満々で明るい笑みをしているではないですか。「秘宝展への看板が電柱ごとにくくりつけてあるよ」
「はぁ。これで迷子になったら手の施しようがないよ」
「というかさ、もお、見えているんだけど」ゆうやは一際目立つ大きな建物を指さした。
しかし、ここまで来て迷ったことが一回だけあった。それはともかく、あたしたちは市内にある美術館まで足を運んだ。ここに名のあるものが来るのはホントに珍しくて何年かに一度あるかないかの出来事だった。一応、県下一大きい美術館らしいけど、田舎の都市にはこの頻度で限界らしい。『世界の秘宝展』だったかな。
「あれ、ここに呼ぶの大変だったらしいよ」
「あれって、あれだよね。あの〜、……とわの瞳――?」
「お! 大正解。また、いつだったかのように知らないでついてきたんだとばっかり」
「ゆうや……絶対、あたしにケンカ売ってるでしょ?」あたしは詰め寄った。
「い・い・やっ! オレはそんなに意地悪なつもりはないけどね」
にこやかにそんなことを言われてもいまいち信用できない。だから、あたしはさらに詰め寄る。
「そお? 誰かさんはいっつも意地悪で、今度の展覧会がなんなのか全然教えてくれなかったんだヨ」ありったけの嫌味を込めて言ってみた。
「……そのようなことはぁ、全く記憶にございませんが、お嬢さま」
ゆうやの決まり文句。あたしが詰め寄るといつも何とかの一つ覚えみたいに瞳を逸らしてそう言った。
「素直じゃないよね。この男」
「素直じゃないのはお互い様だろ?」
「ま、ね……。でも、ま、それはどうでもいいんだけど、あれは曰く付きなんでしょ」
「かなりね」ゆうやは眉をぴくぴくとさせて嬉しそう。そう言えば、ゆうやは妙にミステリアスなことが好きだったんだ。「だって、アクアリュージョンのあることないことうわさ話って多いだろ? 結局、みんな噂でホントのことなんて誰も知らない」
「まぁた、ゆうやの悪い癖が始まったよ。何でも変なことに首を突っ込みたがる」
でも、あたしもゆうやも物好きなのには変わりがないか。
「でも、ただのアクアマリンを見るよりはこんなまん丸目玉みたいに削られた“アクアリュージョン”を見る方が想像が広がると思わないかい? 誰が何のためにそうしたのか。こう言うのは謎が多ければ多いほど面白いと思うのは俺だけ?」
落胆したような残念そうな、まるで捨てられた子犬のような哀れな視線。
「やだ、ちょっと、そんな目で見ないでよ」
「うろたえたまさきも面白いな」
「か?」あたしは目を真ん丸くしてゆうやを指さした。「からかっただけ?」
ゆうやには瞳を閉じて力強く頷かれてしまった。悔しい。
「純真無垢な乙女をからかって喜ぶなんてサイテー」
朴念仁・ゆうやなんて放ったらかして、あたしは順路通りに奥に行く。
「怒るなよ、まさき。他愛のない遊び心だろ」
「ゆうやにはそうかもしんないけど、あたしの心は深〜く傷ついたのだよ」
呼び止めようとするゆうやに振り返って、あたしは胸に手を押し当て、ちょっと大げさに振りをつける。すると、追っかけてきたゆうやは呆れた顔をして、ため息をついた。
「陸上やめて、演劇始めた方がいいんじゃない?」
「そお言うとは思ったけどね。それはあまりに演劇部の方に失礼じゃなくて」
「……演劇に知り合いはいないから別にいいよ。っと、そっちそっち」
「どっち?」ゆうやに突然背中を押されてあたしは戸惑った。
「警備員さんの大勢集まってる方。まさきが、いっちばん見たがってたもののあるぜ」
あたしはゆうやに押されるがまま展示室に入っていった。他のとこよりも少し人が多いみたいで、あたしのようにとわの瞳を待ち焦がれた人たちでいっぱい。
アクアリュージョン。その直径十センチほどのアクアマリンの丸い玉。美術館にあったパンフレットを見たら、それはどこだったかの文明が俗に言う四大精霊、水、火、風、土だったかな、をモチーフにして創ったらしかった。そのうち、現存しているのがあたしたちの前にあるアクアリュージョンだった。
「綺麗だよな」
ゆうやは近寄ってまじまじと見詰めてる。すると、警備員さんが寄ってきた。
「……触ると警報が鳴るから、近寄りすぎると危ないよ」
「あ、はい、気をつけます」ゆうやは恥ずかしそうに赤くなった頭を掻いてた。
その様子を見てたらあたしは何だかおかしくなって、クスクス笑い。気がついてゆうやがこっちを向いたから、あたしは唇を噛みしめて笑いをこらえた。少しでも気を抜いたら吹き出してしまいそうだった。
「この笑い上戸!」
「あは、ごめんね、ゆうや。でも、こいつをよく見たいってのはあたしも同じ」
そう、アクアリュージョンは透明感の溢れる海の水色。
「アクア、リュージョン……。流石は『とわの瞳』の別名をもつだけあるね。ホントに目みたいだ。青くて透き通ってて……、このヒビがまた。ここがぱかっと開いたら本物の目玉がギョロッて睨み……ませんね。はい、ど〜も、突拍子もないこと言ってごめんなさい〜っだ」
「何を一人芝居打ってんだ? そして、美術館ではし・ず・かに! ほらっ、警備員さんがまたこっちを向いて睨んでいるよ」ひそひそ声であたしに耳打ち。
「そんなこと、ゆうやに言われなくたって判ってるよ!」
「全然ッ、判ってねぇじゃん騒々しい」
『汝、我を持て……開け』
「え? ゆうや。なんか言った?」
「何も言ってないよ。それより時間がないし、次を見に行こうか?」
「ダメ! も、少し、その青い瞳を見ていようよ――。だって、まるであたしの澄んだ心みたいでしょ? ロマンチストのあたしにぴったり」
「ウソこけ」ほんのちょっとも考える素振りを見せずに、瞬間的にゆうやは言った。
「それはどういう意味ですか?」
「深読みしても時間の無駄だぞ? 単刀直入、ストレートな意見を言ったまでだ」
にやり。
「そお? 遠回しな性格をしていると思ってたんだけどぉ」
「それは時と場合によるよな。やっぱ」
「ふ〜ん。そっかぁ。そしたら、待ってるだけじゃ、期待薄なのかなぁ」
「何が?」
「んふ〜、内緒!」あたしは微笑んでお茶を濁した。この鈍感!
「青い瞳か。一説によると、こいつには赤い瞳が対になっているらしい」
「赤い瞳?」興味津々でゆうやの横顔を見詰める。
「そう。こっちはね、ガーネットのより赤いのだって話なんだけど。名前は“アクア”に対して“フゥ”って言うらしいよ。ファイアレッドに近いみたいだから。水と炎。まあ、何というか反対の要素だよね」ゆうやが横を向いてあたしと目が合う。
「じゃさ、対のその片一方はどこに消えたのさ?」
「それが判っていたら、そこに二つ並んでいるんじゃないのかな?」一瞬だけ、勝ち誇ったようなゆうやの表情が見えた。「案外、そいつは二つ並ぶのを夢見てるのかもね?」
ゆうやにしてはロマンチックなことを言うじゃない。
「ふ〜ん」
あたしは気のない返事をして、アクアリュージョンに見入っていた。眠っている瞳が夢見ているのは何なんだろう。青い瞳と赤い瞳。その昔、仲良しだったのかな。仲悪かったのか? 想像力をたくましく、色々考えてみると面白い。
「そいつの片割れは“フゥリュージョン”って言うらしい。和名は幻の炎」
『我が名はアクアリュージョン』
近くに人がいた訳じゃないのに、その声は確かにあたしの耳元で聞こえた。あたしはキョロキョロとした。けど、周囲の状況はさっきと全く同じ。ゆうやは隣にいて、あ〜でもないこ〜でもないとまだうんちくをたれているし。
「落ち着かないぞ? どうかしたのか、まさき」
「ううん、何でもない」
と平静を装いつつも、あたしは怖くてゆうやの制服の裾を掴んでいた。
『汝は……我を求めている』
誰かがあたしを見詰めている。でも、あたしを注視している人はいない。みんな、思い思いに見学しているだけで、あたしの存在にも気がつかないかのようだった。熱い眼差しを送るのは誰? あたしに何を求めているの。
『汝、我が声が聞こえるか?』
「ゆうや? ゆうや!」あたしは怖くなってゆうやを呼んだ。けど、返事はない。
掴んでいたはずのゆうやの制服の端も、いつの間にかあたしの手の中から消えていた。血の気が引いてく。なくなるはずのない周囲の雑音さえあたしの耳に届かなくなって、落ち着きをなくしてキョトキョト、おろおろとするあたしの微かな足音だけがコンクリートの壁と床に反響していた。無人じゃないはずなのに、音を吸収する何もかもが失われてしまったかのようだった。
『汝、我が声が聞こえるか』
「誰?」
初めて、はっきりと捉えたその声に言い知れない怖さがあった。ガラスケースの向こう側に一つ目が見えた。心臓が大きくドクンと脈を打つ。そんなことあり得ない。石がしゃべるなんて。そんなバカなことがあってたまるか。でも、あたしを睨んでいるそれは明らかに生きたものの瞳だった。石の鉱物のような無機的な冷たい色合いはなく柔らかそう。無性に突っついてみたい衝動に駆られたけれど相手はガラスケースの向こう側。ちょっと残念。けど、あれの外側がアクアマリンの煌めきを持っていなかったら、それはホントに生きた眼だった。
『何時は我の存在を認めている。――ならば、我と来るがいい』
「はぁ? ちょっと、待って勝手に決めないで!」
『汝が望んだことだ……』
こんな訳の判らない状況だったのに、あたしは妙に落ち着いてた。
「あんたに何を望んだの?」
『汝は望んだ。ゆけば判る』
「小悪魔みたいなこと言わないでよ」
『――!』
そんなことを言われたことがないのかアクアリュージョンのとわの瞳は呆気にとられたようにしばらくキョトンとしていた。そして、瞬き。
『ともかく、行って来い』
とわの瞳の最後の言葉があたしの耳の中でこだましていた。あたしが望んだことは何だったのか。ゆうやといること。世界中を股にかけてみたいこと。思考が妄想世界に入り込もうとした瞬間、あたりが白い闇に呑まれてゆくのをあたしは感じた。暗闇に閉ざされたことは幾度となくあったけど、白闇に放り出されたことはない。と、床の抜けて落下するような、遊園地のフリーフォール並みの嫌な感覚があたしを襲ってきた。吐きそう。それから、先のことは全然記憶になくて、気がついたらあたしは、
「ここ――、どこ?」
と、しか言いようのない知らない風景の中にうずくまっていた。荒れ地でごつごつとした大きな岩が転がり、時々思い出したかのように雑草が生えてる。少なくとも、ここはあたしの街じゃなくて、あたしのいたはずの美術館じゃなかった。アクアリュージョンの瞳と出会って、それから、何があったの? 理解不能。あたしのの〜みそじゃその程度の回答しか出てこない。ゆうやがいたらな。と、ゆうやはどこ?
「ゆうや、ゆうやぁ?」
不安に駆られたあたしはそのときまで隣にいたゆうやを求めた。きょろきょろと落ちつきなく見回しても見慣れた人影はなかった。その代わり……。
「――葬式でもねぇのに真っ黒い服着て、おねぇちゃんはどこから来た?」
帽子を被って、乞食みたいにボロを着た男が一人佇んでいた。
「判んない」惚けたようにあたしは言っていた。
「やっぱりね。じゃ、おねぇちゃんがここ五年ばかしの間で五百何人目だかのあれだ」
ど忘れしたのか、ボロの男は腕を組んでうんうん唸っていた。あたしはその様子を眺めているしかなかった。あたしは五百何人目かなの何なのかも気になったけれど、あたしにはここからどこに行けばいいのかすらも判らなかった。
「ここはどこなの? 五百何人目かの何だかは後でいいからそっちを先に……」
すると、ボロの男は考えるのをやめて、その目線はあたしの瞳を捉えた。
「アクアリュージョン。まさきの求めた世界」口元がニヤリと笑った。
「な? 何であたしの名前を?」
「知っているさ。柊まさき十八歳。……お転婆娘」
「余計なお世話だよ。って、だからどうして知っているのかって」
「こうなったんだ。少しは落ち着きなよ」右手をひらひらさせて言われると余計にムッとした。やる気なさそうになだめないで欲しい。ただでさえ気が立ってるんだから。
「……怒ってるの?」ボロボロで穴だらけの帽子のつばの下から青い目が見えた。
「怒ってません!」
「ま、そう言うことにしておいてやるよ。不毛だから」
「……」腕を組んで流し目でつい。「あんたの頭が不毛なんじゃないの?」
「近頃の娘は遠慮がないね。はっきりと言うのはいいが、じじいは敬えよ?」
「や・だ!」
高圧的にこられるとあたしは反抗的になる。悪い癖。ところが、ボロをまとった男はあたしの眼を見詰めて、フッと微笑んだ。瞬間、あたしは自分の言ったことが恥ずかしくなった。
「ハハッ! 威勢がいいねぇ! 人選は間違っていなかったようだよ」
「どういう……意味?」あたしは眉間にしわを寄せて質問していたのに違いない。
「それは後で教えてやる」とっても嬉しそうな鋭い煌めきが見えた。「そう、ヒントだ。始めに南西に行きなさい。小さな村があるから。そこで聞きなさい。五百十二組目の……お嬢さん」
不敵な笑みを浮かべて、ボロの男はあたしのそばから去っていった。
「帰るためには片割れを探せ……」
去り際に言ったその言葉。どういうことなんだろう。あたしに何をさせるためにここに呼んだんだろう。あたしの望んだことは冒険。冒険。でも、考えてる時間は余りなさそうだった。陽が落ちきる前にあたしは行かなきゃならない。