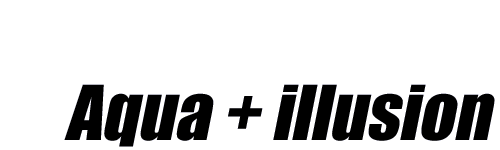
02. ジュンの家族とあたしの道
結局、あたしは訳も判らずに、歩き出した。と言うより、絶対に帰る。そのためにはあのボロをまとった男の言葉を信じて、とりあえずは南西に行ってみるほかなかった。身を守るものが何もない以上は誰かの助けを借りるしかない。いくら、都会育ちのあたしだって、こんな荒れ地を装備なしに一人でうろうろするほどバカじゃなかった。あたしは慣れない暑さにふらふらしながら、小高い丘から降りていった。するとあたしのくたびれた目にひなびた町らしきものが見えた。ちょうど田舎の国道をドライブするような感じで、道の表サイドに数えるほどの店がならんで、あとは民家。よく見ると、その外れに「INN」と看板のあがった小さな家があった。
「ね〜、父ちゃん。あそこからふらふら歩いてくるのなんだと思う?」
「幻だ。幻。夜更かししすぎると時たまおかしなものがよく見える。はい、どっこらしょっと」
「けどさ、いるもんはいるんだもん。幻見てんの父ちゃんじゃないの?」
「スイ……。あっちの方に人は住んでいないだろう」
それほど遠くもないところに女の子と男に人の姿が見えていた。女の子は男の人の肩をぽんぽんと叩いて、あたしを見ろと言っているみたいだった。
「あ〜。人だねぇ。女の子だねぇ。真っ黒い服を着ているねぇ……」
「幻じゃねぇじゃん。このクソ親父め」仲良しの父娘なのかな。
「なんだ、クソガキ。それが親に向かって言う言葉か!」
「黙らっしゃい、欠食児童ども」と、女の人が看板の奥の家から姿を現した。
「けっ欠食児童?」
「めし〜、めし〜っていっつもうるさいからだよ。あんたらの胃袋は一体どこにつながってるんだか、毎度毎度、不思議で仕方がないんだよ」
「父ちゃんの胃袋は底なしズダバッグだからね。諦めなよ母ちゃん」
「考えなしに食われたらうちの財政が破綻するんだよ」
「母さん、その話はまた、今度にしましょう? 来ちゃったみたいだから」
「来ちゃった? 何が?」
「あれだよ」誰かがあたしを指した。
「まっ黒。しかも、フラフラ歩いて頼りなさそうだよ」
「そうだね、母ちゃん。また、来ちまったようだ。でも、女の子は初めてだよな。五百十二人目」
「もう、そんなんなるのかい。すっかり、ここは旅立ちの宿になっちまったねぇ」
「旅立ちの宿ねぇ。ただの民家じゃん? 『INN』の看板あげた」
「屁理屈なんかあとで聞いてやるよ。ホレ、迎えに行ってやんな。こっち来る前に倒れちまいそうだ」
「へいへい、全く人使いが荒いんだから、うちの母ちゃんは」
男の人があたしに近づいてきて、支えてくれようとした。けれど、あたしはつっけんどん。助けてくれる人が欲しかったはずなのに、攻撃的な言葉があたしの口をついて出た。
「……さわらないで」
「名前は?」男の人は困ったようにため息をついて頭を掻いていた。
「……」初めて見た人なのに。そして、暖かそうな人たちなのに、どうして?
「じゃあ。何か、食べるもの、食事は?」
「要らない。何も要らない。何も要らないからあたしを帰して!」
「……。母さん。ともかく、この娘に温かい飲み物だ。それからのことは後で聞こう」
「ゆうや……」
あたしは無意識のうちに呟いていた。その名があたしの喉から零れ落ちたとき、心臓がぎゅっと締め付けられるような感覚が来た。どうして、ゆうやを忘れたんだ?
「ゆうや? あんた一人しかいなかったよ」
「ゆうや!」あたしは女の人に抱き付いてわめいていた。
「……誰か一緒だったんだねぇ。父ちゃん! ちょっと、父ちゃん、呑気にめし食ってないでゲートを見てきてやんな。ユメもいっといで! 連れがいたらしいんだよ」
「連れより飯だよな? スイ?」
「父ちゃん、腹の虫は諦めなよ。母ちゃん、結構本気で睨んでるよ」
「そうだよなぁ。スイは母ちゃんの味方だもんなぁ。そして、フライパン」
「めしは剣よりも強し。行くかい、父さん」
「そうだね。そちらのお姉ちゃんにうちにお泊まりいただき、俺の腹満たすためには」
女の人に抱き付いて泣きじゃくったあたしの耳に遠くで聞こえいた。ありがとう。口先では嫌がっていたようだけど、心の向こうは違うように感じていた。詳しくは覚えていないけれど、二つの男声はとても優しくあたしの中に響いていた。
「……おう、母ちゃん? あの娘は落ち着いたのかい」
「何とかねぇ。そこのソファで眠っているよ」
あたしの背中で二人の会話が聞こえていた。ちょうどあたしは二人に背を向けて、背もたれの方を向いて丸くなっていた。
「名前は聞けた?」
「聞けたよ。え〜っとね、……柊まさき、十八」
「ユメの五つ下か。――まだまだ、子供かな……」
「もう、十分大人でしょうよ」
「そりゃぁ、スイに比べたら遙かに大人だろうけど」あたしはあの女の子以下ってこと?
「ま、いいわ。それより、ゆうやって子、いたのかい」
「いいや、向こう、誰もいなかったぜ」
誰もいなかった。やっぱり、ゆうやはいなかった。あたしは一人。と、思ったとたん、急に切なくなって涙が零れ落ちそうになった。あたしは両腕で自分の身体をきつく抱き締めて必死にこらえようとしたけれど無駄な試みだった。
「あと、しわしわの紙が一枚きりな……。お決まりのパターンだ。ナンバー五百十二。柊まさき、岡田ゆうや。もう、間違いないね……」
「挑戦者だ・ね。こんな可愛い娘なのに」何か、同情に満ちた声色だった。
「ああ、無事に帰れるといい。帰らせてくれるか?」
「誰かがアクアリュージョンの望みを叶えたのなら、挑戦者なんて来ないはず。誰も成功していないんでしょ? つまり、帰ったのはいないんでしょ?」ため息が聞こえた。
「まさきが成功したらいいだけだろ」
「そりゃあ、そうだけど。……そ、言えば、父ちゃん。今日は青い目のおじいちゃんに会わなかったの?」
「いなかったねぇ」
「挑戦者を呼んだときはいつもいないよ」もう一つ別な声が聞こえた。
「どういうこった? ユメ」そっか、あの人はユメって言うんだ。
「何だ、父さん知らなかったの」
「もったいぶっていないでさっさと教えろ。父ちゃんは万能じゃあない、知らないことはそれこそ星の数ほど」
「そんなこと自慢してど〜すんのさ、父ちゃん」
「――! スイ、母ちゃんに似て父ちゃんの揚げ足取りがうまくなったなぁ」
「そりゃ、母ちゃんの娘だもん」
「父ちゃんの娘じゃないのかい?」
「うん、そうだよ」屈託のない明るい声が聞こえる。
「父さん、形無しだね」
「もお、ほっとけ」憤慨したような、でもどこか楽しげな声色。
あたしは不思議な親子漫才(?)を聞いて、ちょっと爽やかな楽しい気持ちになっていた。どこに行っても、人の基本は変わらないように思えて少しだけ安心できていた。
「ところで、そこの黒服のおねぇさん。肩が震えてるぜ、起きてるんだろ?」
隠したつもりはないけれど、ばれてる。この状態からあたしはどうやってみんなの方を向いたらいいんだろう。あれだけ騒ぎ立てみんなに迷惑をかけたあとで気恥ずかしい。その上、家族みんなが集まってあたしに注目しているみたい。
「いつまで寝てるの? まさき。変に強がってると朝まで寝てなきゃなんないよ? そこ、ちょっと硬いだろうし、夕飯、あたんないぜ?」
「ェえ? これから半日もおなかを減らしてるなんて耐えられない」
あたしは軽い笑いの口上に感謝して、勢いよく起きあがった。
「ホラ、ユメ、スイの言った通りでしょ? おなかぐ〜ぐ〜言ってたからめし〜の話をしたら、絶対に飛び起きるって」
あたしはこんな小さな女の子の策略に引っかかったの? 何だか、悔しい。けど、みんなに向き直れなかったあたしに切っ掛けをくれたのがこの娘なら文句は言えないよね。と、あたしはさっきのことを思い出して血が頭の方にじわりじわりと昇ってきた。首の付け根から顔が熱くなってくるのをあたしは感じていた。
「ごめんなさい。ここに来たときあんなことは言うつもりはなかったのに」
「そんなことは気にしなくてもいいんだよ。あれでもましな方。来るなり父ちゃんの胸ぐら掴んできたアホもいるんだから」
「もちろん、その場ではり倒してやったけどな」力こぶを作って苦笑いをしてる。
「それも、もう、五年間、五百十二人目だ。やつらの望みは叶わずに犠牲者だけが増えていくな」
「父ちゃん! そんな辛気くさい話は明日にしな。まさきも落ち着いたし、何より、ここに来た初めての女の子なんだよ。今日くらいは、そんな話、忘れてさ」
「まあ、そうだな。レン」
口元で微笑んで、見つめ合ってる。いいな。そんな仲の良さそうな二人を見ていると羨ましい。ゆうや、もっともっと、あたしを見て。
「じゃ。俺は空っぽの腹を満たしてもいいのね?」
「いいえ! まさきが先。父ちゃんは後」
レンには澄ました笑顔がよく似合う。
「父ちゃん、今日はすっかり女難だねっ」
スイが笑いながらチャチャを入れるとどんな緊張の空気も柔らかくなりそうだった。
ジュンの「INN」に来てから三日目。その間に、あたしは何回もアクアリュージョンの呼び声みたいなのを聞いた。『探して……』聞こえるたびにあたしは怖さを感じた。あたしは行き先に迷ったただの女の子なんだ! と言ったところで、あの青い瞳には通じないんだろうな。あたしはやっぱりフゥリュージョンを捜すための挑戦者なんだろうか。ジュンやユメの教えてくれた地名なんて、あたしの地図帳のどこにも載っていなかった。“帰るためには片割れを探せ”ボロの男の言葉が急に真実みを帯びてあたしの中で響いていた。
「ユメ……。ユメェ?」
「何だ? まさき。夜中に大声出すな、みんな寝てる」
「ごめん……」少し反省。「でも、聞いて、あたし、決めたの」
切れ切れの言葉で何を決めたのかも言わなかったのに、ユメは判ったようだった。
「明日、出発する――。……あたしは帰らなくちゃダメなんだ。帰った人がいないなら、あたしが最初になるんだ」
「本当に行っちゃうつもりなのか」残念そうにユメが言った。
「行くさ。そのためにあたしは来たんだから?」
「ふ〜ん、夜な夜な泣いていたくせに、けっこう、芯が強いんだ!」努めて明るい。
「う、な、あぁ」あたしは真っ赤になった。「き、聞いてたんだ」恥ずかしさでいっぱいで声が裏返った。
「聞きたくなくても、聞こえるんだよ。壁薄いから」
「じゃ、聞こえない振りしてくれよなぁ」
「それは出来ない相談だ。俺って真面目だから」
絶対ウソだ。目が笑ってるから信じないぞ。だから、あたしは訝しげ眼差しでじと〜っと湿っぽくユメを見詰めた。
「ま、信じてくれなくても構わないけどさ。もう、お休みよ。明日、発つんだろ?」
「うん……。でも、どおしてあたしだったんだろう――」
「さあね」
素っ気なくユメは答えた。それから、ユメはあたし一人を部屋に残して、出ていった。
結局、その晩、あたしはほとんど眠れなかった。寝苦しいほどの熱帯夜というわけでも、異常に緊張していたわけでもないと思う。ベッドに入って、薄い毛布をかぶっても眠気は来なかった。軽いあくびの出るよな仄かな眠気はあったけれど、目は冴えていて、深夜の止まったような時間が静かに流れていた。
だから、あたしは起き出して月の青白い光が照らし出す窓の外を眺めていた。ジュンの家の庭先。雑草が揺れてて、タンポポが咲いてて、ひまわりのつぼみは大きくて。あたしが来る前からここはこうで、あたしがいなくなってもここはこうなんだね。
あたし一人がいなくなっても何かが変わることはないだね。いつもの答えの出ない淋しさを胸に抱えたままベッドに横になった。空が白んでくる前に少しだけ寝ておこう。
これが夢じゃないのなら、あたしは歩いていくほかない。
『フゥを探して……』
行かなきゃダメなんだね、行くしかないんだね、行けって言うんだね。
ちゅん、ちゅちゅん。朝、あたしの腕時計だと午前五時。ジュンの一家は畑を持っていたから朝が早かった。初日なんて、あたしは両親共働きの鍵っ子の気分だった。かっての判らない家に置いてけぼりにされて、ちっちゃな子供のようにオロオロしちゃった。それは朝早くに「起きろ〜!」って怒鳴られたって起きないだろうけど。
あたしは窓から差し込む朝のあったかい日差しを浴びて着替え。朝にこんなゆったりとした時間が流れているなんて初めて知った。
「おはよっ! みんな」元気に挨拶。
「おっ! まさきが起きてて、しかも、着替え終わってるなんて一波乱ありそうだな」
「なんて言い草だ、失礼だぞ!」
でも、これも今日で最後。あたしは自分のホントにいるべきところに帰る。アクアリュージョンがフゥリュージョンを探しているように、あたしにはゆうやが待ってる。
「ジュン。あたし、行くよ」
あたしの唐突な発言に、朝食をとるみんなの手が止まった。
「そうか……まさきは行くんだな」
食事をする手を休めて、ジュンはしんみりとあたしを見詰めていた。セイも、スイ、ユメさえも黙ってしまって、あたしはどうしていいのか困ってしまった。
「……じゃあ、俺はお決まりの前口上をたれなきゃならんわけだ」
目は天井を見て、右手にはレタスが突き刺さったフォーク、口はもしゃもしゃとサンドイッチをはんでいる。さっきの緊張感はどこに吹き飛ばしてしまったの? それとも気を紛らわすためなんだろうか。
「あの……」黙りを決め込まれるよりも、あたしは対処に困った。
「慌てるな、まさき。こう言うときは、まず始めに腹ごしらえな」
ジュンだけは拍子抜けするくらいに落ち着いていた。
あたしはため息まじりの気のない返事。
それからの三十分はレタスをハミハミ、モシャモシャ。沈黙の中を流れる食事の音ばかり。まるで、父さんを交えた家族会議みたい。思い出すだけでも怖すぎ。でも、ジュンはあたしを威圧したいわけでもなくて、純粋に腹ごしらえをしたいだけ。ここんちの鉄則、朝食は身体の資本! あたしもここにいたら早起きになれるのかな?
「ごちそうさまでした。んじゃ、いいか、まさき? とりあえず、外に出て」
「い? いいけど?」
「今までに五百十一人。生きて帰ったやつは一人もいない」
あたしはジュンの言葉に息を飲んだ。
「ここに来たやつみんなに聞いた。けつまくって逃げるなら今のうちだってな。街の外のゲートを越えたらアクアリュージョンの魔力が消える。そして、帰りのゲートの開き方、俺たちは知らん」
「冷たい言い草だねぇ。賢者に聞けって一言アドバイスしてやりゃいいのにさ」
「ほっとけ、クソばばあ」
「! クソばばあ、だって? このクソじじい!」
「ま、まあ、落ち着いて……」
「まさきは黙っとれ!」二人に凄い形相で睨まれればあたしはたじたじ、ものさえ言えなかった。
「チャレンジするならそこのゲートを越えてゆけ」
あたしの目前にはフランスはパリの凱旋門ばりの巨大ゲートがそびえ立っていた。その向こうには何にもなくて、絶望を促すような荒野が広がっていた。
「ど、どっちに行ったらいいの?」あたしは思わず聞いていた。
「とりあえずはどこまでも真っすぐだな」ジュンはあたしの頭を髪の毛がぐしゃぐしゃになるまで撫でてくれた。「それと、餞別の代わりだ。これ、持ってけ」
ジュンがあたしの前に差し出したのは刀剣だった。あたしの腰の位置より少し長いくらいで、ちょうど使いやすい長さだった。重さも柄も、まるで最初からあたしが使うことを計算していたみたいにぴったり。不審がってジュンを見ても、ただ頷くだけ。
「人殺しの道具は要らない……」
「必ずしもそのためだけじゃないんだけどね」
「だけどっ!」髪を乱してあたしはジュンを見た。
「まさきっ。父ちゃんの言うことは聞くもんだよ。ここはあんたらの世界と違うんだ。特にそのゲートを越えたらあっちは戻れない。そうなったら頼るのも身を守るのも自分しかいないんだ。みんな自分のことで手いっぱいだからまさきのことなんか構ってくれないよ」
(なれてるからいい)そう口走りそうになるのを飲み込んだ。
「構ってくれないだけだったらい〜んだけどねぇ。――まさきって女だからぁ」
意味深な響きを含ませてユメが言った。もちろん、言いたいことは判った。丸腰の女の一人旅はこの世界ではタブー。と言うより、一生を街の周辺のところで生きる人たちが大半を占める中で、旅すらも珍しいようだった。それに旅人といえばそのまま剣術か、武道に長けた人だったし、そうでなければ護衛を付けた商人たちだった。ただの素人が旅行できるほどの治安はここにはない。
「判った? まさき」
「判ったよ。みんな、あたしの身を案じてくれてるんだね」
あたしはジュンからもらった剣を天にかざした。太陽の光が当たって剣が煌めく。出来れば、ここから先一度だって使いたくなかった。
「もう、行くよ! 名残は尽きないし。湿っぽくなるの嫌いだから……」
「そうか……」
ジュンは短くそれだけを言った。あたしの見たジュンの瞳は水面に映った月のようにゆらゆらと揺れていた。涙をこらえて、嗚咽を漏らさないようにしているのがあたしのも判った。
「これ、持っていきなさい」レンがあたしに小さなノート一冊とペンを一本くれた。
「これは……?」それを受け取りながら、あたしはレンの瞳を見つめていた。
「謎解きをするんだろう」あたしは頷いた。「だったら、紙とペンは必需品だ」
「ケチケチばばあが随分と奮発したもんだ」
ジュンの言ったようにここでは紙はそんなには安くなくて、庶民が手を出すのはなかなか難しい存在だった。それなのにレンは気軽にあたしに渡してくれた。
「こんな高いもの受け取れないよ」
「いいから! あたしたちからの餞別だよ」
「いや!」
「全く、頑固だね、この娘は!」
「まさき……もらってやりなよ」ユメはそっと諭すようにあたしに言った。「それ、妹の――」
「ユメ。やめなさい」震える声でレンが言った。すると、ユメは静かに首を横に振る。
「母さん、ホントのこと言わないと、まさきはもらってくれないよ……」
ユメが諭すように言うと、レンは哀しそうな眼差しをあたしに向けため息をついた。
「……物書きの好きだった、セイの持ち物だった。……殺されたよ」
「殺……された?」レンの言葉、あたしには信じられなかった。
「ここはまさきのいたところほど治安がいいわけじゃない。つまりはまさきもそうなっちゃうかもしれないってことさ」
「だって、だって、殺されたんだよ。警察は? 犯人は?」
「自分の命は自分で面倒を見るのがここの決まり」
「じゃあ、弱いやつは死ねっての? そんなのヘンだ!」
「違うよ――」冷めた口調のユメだった。
「違うって何が。どっかおかしいよ」
「……黙れ! まさき!」ジュンが怒鳴った。あたしはビクッとして声も出せない。「ここのホントの状況を知らないやつがごちゃごちゃの口出しするな」
「父ちゃん、何も本気で叱らなくても」レンがなだめようとしたけれど、効果なし。
「いいや、母ちゃんは黙ってろ。まさきっ! 中途半端にしか知らないくせに文句をたれるな。そう言うことはまさきのフゥリュージョンほどにアクアリュージョンを知ってから言うんだ。そしたら、俺だって色々と答えてやるよ」
「はひ……」ジュンの迫力にあたしは完全に気圧されていた。
「……やっぱり、素直なやつはかわいいね」
「ねぇ、父ちゃん母ちゃん、剣も筆記道具もお説教だって何でもいいんだけど、肝心なもの忘れていない? まさきが来たときからせっかく用意してたのにね」
玄関先で、エキサイトしているところへ飄々としてひょっとスイが現れた。
「忘れてる?」ジュンとレンが同時に返事をした。
「これ!」スイが持ってきた学生鞄より少し大きめのリュックサックを指さした。
「あ! 身、一つじゃ、旅なんか出来ないからって用意したんだった」
あたしが急に出発すると言い出したせいなのか記憶から綺麗さっぱり消えてたらしい。ジュンはスイからリュックを受け取ってあたしに渡してくれた。正直言って重い。
「ジュン……、重いよ、これ」
「そりゃ、軽くはないよ」あっさりと、ジュンにかわされた。「ここで、旅をしならが生きてくための半分が入ってる」
「半分……だけ? じゃ、残りの半分はどこにあるの?」
「もう、半分はまさきが持ってる」ジュンはあたしの胸を指さした。
「あた……し?」
「そう、あ・た・し」ジュンはニヤニヤ。「道具をそろえたって足りねってこと。最後まで行く気持ちがなかったら、いくら物があってもダメってことさ。それはまさきの方がよく知ってると思うけどね……」
あたしはジュンのその言葉を背中にして歩き出していた。
「まさきぃ、元気で行けよぉ。俺たちのこと、忘れるなよ〜」
「忘れない! どこに行ったって絶対忘れないからね」あたしは振り返って手を振った。
また、あたしは一人になるんだ。そう思うと突然胸の奥から湧き出るような不安と淋しさが込み上げてきた。膝を抱えて木陰にうずくまるあたしには何もなくなっていた。
「……泣くなよ、まさき」誰かに頭をクシャッとされた。見上げると。
「な、ユメ!どうしてここに?」ユメを指さしたまま口をパクパク。
「――父さんがね、まさきをなんとしても元のところに返してやれってね」
ユメは木に寄り掛かって頭の後ろで手を組んで空を見上げていた。
「ジュンが」
「そう、父さんがそんなことを言ったのは初めてさ。よっぽどまさきが可愛かったのか、セイに似てるんだろうな」
「セイってどんな娘だったの……?」
「容姿はそれなりにまさきに似ているよ。でも、性格は正反対――かなぁ?」
「あたしに聞かないでよ」
「そう、そんな勝ち気なところはまさきとそっくりだったな。街ん中じゃねぇ、憧れの的だったんだぜ、あいつ」懐かしい思い出を語るようにユメは空を見上げていた。
「女剣士さ」
「女剣士?」
「元はと言えば、父さんがまさきにやったその剣もセイの持ち物だった」
「セイの?」
あたしの中では突拍子もなかったユメの言葉に単語でしか応えられなかった。
「強かったんだけど、魔が差したんだろうな……」
急に淋しそうにションボリとしてユメはその先を語ろうとはしてくれなかった。あたしに教えたくない。と言うよりは、あまりその時のことを思い出したくないような様子だった。あたしに問いかける勇気はない。
「はは! 悪い悪い。いずれ教えてやるから、今日はなかったことに」
ユメの乾いた笑いは心の奥に直接、響いていた。何があったのかは知らない。でも、ユメの目尻に光った一粒の涙が全てを物語っているような気がした。セイってどんな人だったんだろう。
「さあ、立って、まさき」ユメがあたしに手を差し伸べてくれた。「丘を越えた街なんて、今から出かけたら何もなけりゃ、昼までには行けるから。そこで昼飯な」
「うん……。――よっと」
あたしはユメの手を借りて立ち上がった。ユメとバッチリ目があって、ユメは微笑む。
「ご案内いたしましょうか? お姫さま」冗談めかして薄笑い。
「でも、あたしはお姫さまなんて柄じゃないよ?」
「向こうじゃどうだか知らないけどね。ここじゃまさきは小生意気で世間知らずのお姫さまってつもりで言ったんだけど……違う?」
「ち、違わない……」
否定できないあたしがいた。口をもごもごとさせてショボンとうつむいた。
「ハハ、面白いよ、まさき。やっぱり、どこかでセイににている」
ユメとあたしは街を抜けて、最初、あたしの来た方とは反対側の草木の生い茂った山の方に来ていた。
「向こう側は丘は荒れ地だったのにちっちゃい丘を越えたらそれなりに緑があるんだね。ちょっと不思議」
「まあ、緑って言っても畑と人工林だけどね。俺のじいちゃんの代が開拓史で入植して開いた土地なんだ」
「そうなんだ……」
「俺たちの集落を過ぎてね、山を越えたグリーンズは元々原生林で覆われたとこだったんだけど、こっちは土地がやせてて草あんまり生えてなかったって」
「何でそんなところを選んできたのよ。だって、すぐ向こうはそりゃ、開墾は大変なんだろうけど、森の中なら土は良かったんじゃないの? 荒れ地より?」
「さあ? と言うか、じいちゃん“無”から“有”を創るのに燃える男だったからじゃないかって父さんは言ってたけど」
「“無”から“有”って言ったって何もないじゃんあそこ」
「そこがよかったんだ」
「はぁ?」あたしにはユメのおじいさんの気持ちがいまいちよく判らない。
地平線の見える景色なんて、初めて見た。あたしが生まれてからいた世界はせせこましくて小さなものに思えた。ぎゅうぎゅうに立ち並んだ家々と、無秩序に生えた高層ビル。地平線に沈む夕陽も見たことはなくて、霞んだ星空しか知らないあたしは何だか惨めなような気がしてならない。
「……まさきのところはどうだった?」好奇心にきらめくユメの瞳があたしを見ていた。
「あたしのところは……人工物の山……」シュンとしてあたしは言った。「人の住むところに自然に、昔からあった物なんてほとんどない」
「変なところから来たな」
「でも、あたしの世界じゃそれが当たり前だった」
「そして、この丘を越えたら、グリーンズ。ここから見たら眺めは壮観。驚くぜ?」
峠を越えて少しまで左手の谷側の視界は森に遮られていた。けれど、それが切れてずっと遠くまで視野が開けたとき、
「すごい……」あたしは息をのんで立ち止まった。
あたしの街じゃこんな風景は絶対に見られない。抜けるような青い空と、入道雲の下には畑がどこまでも連なっている。反対側の山が見えるまでずっと畑なんだ。所々には、防風林があって、そのまた間に色とりどりの屋根を持った民家があった。
「ここら辺は斜面が多いから、そこら中はほとんど小麦かな。ちょっと色づき始めてるだろ?」
あたしは綺麗な景色に見とれてただ頷くだけ。
「あと、ずっと東の山の奥に行ったらリンゴの果樹園があるし……」
「リンゴ? もう、収穫できるの?」
「ハハハ、リンゴの季節にはまだ早いよ。向こうの山を抜けて西に行ったら水田とか玉ねぎが見られるよ。まさき、その様子だとあんまり、知らないんだろ?」
ユメの言葉にあたしは恥ずかしくなった。
「面白いぜぇ? 防風林なんてみんな斜めに生えている。風が強いんだ。……時間がもっとあればグリーンズを全部案内して歩きたい。きっと、ここを気に入ってくれる」
「あたしがここを気に入る……」
あたしはユメの言葉を繰り返した。その時、あたしはジュンの言葉をフッと思い出していた。自分のフゥのこと、街のことをあたしはどれだけ知っているんだろう。きっと、ほとんど知らない。知っているのはあたしの興味のあるとこや、ホンの一部分。なのに、あたしは――ジュンを傷つけていた。