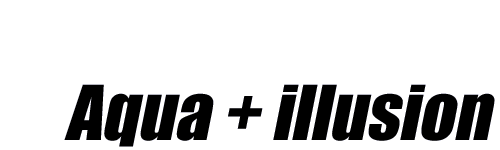
05. 見果てぬ大地、ノーシーランド
翌朝。アクアリュージョンに来て五日目の朝。あたしたちはクロウの翼で羽ばたいていた。シャンルーの大断絶を渡る。その向こうはノーシーランドと言うんだって。誰も見たことのない土地とは呼ばれてるんだけど、グリーンズの人たちが見たことないだけなんだとユメが言ってた。
「うわ、すご! ユメ、クロウ。この谷、底が見えないよ」
「それが大断絶の呼び名の由来でもあるんだ」
「ひぇぇえ、落っこちたら、絶対確実にダメだよね、こりゃ?」
「試しに落ちてみる? 一応底はあるんだ。ずっとずっと、北に行ったら降りれるんだよね。歩いたら一週間はかかるかなぁ」
「いやだよ、そんなの」単刀直入に言って、あたしはユメを流し目で見た。
「俺もいやだ」くりっとした眼で悪戯っ子の微笑み。
その一週間かかる谷越えもクロウの力を借りたらホンのひとっ飛び。底の見えない断絶を越えたその先は、
「……何だか、無性に帰りたくなる土地柄だね、ここ」
見渡す限りの大平原。だったらまだましだったんだろうけど。減反されてうち捨てられてしまったような水田や耕されたのはいいけれど雑草ぼうぼうの畑。淋しい景色の中にポツンポツンと埋もれるようにあった崩れかけの廃屋。そんなのがあたしの胸をギュッと締め付けた。捨てられたんだ。
「まさきが弱音を吐くなんて珍しいね」
「弱音じゃないよ」ニコリ。「淋しそうな空気を持っているところは苦手なんだ」
「はぁ〜ん、まさきならそんな感じがするよね。情熱の夏! とか、灼熱の熱帯とか似合いそう」
「でしょ?」ちょっと得意げに鼻を高々とさせてみる。「あたし、夏女なの」
「夏の女? じゃあ、これからがまさきの季節なんだ」
「そ」あたしは誇らしげに大きく頷いた。「陸上の季節はあたしの季節! 足の速さだけならきっとユメにも負けないよっ」
「確かに体力はありそうだよな。ここまで愚痴一つ言わなかったもんな。ま、人の良さそなやつだけグリーンズまで付き添ったことあるけど、そいつらだって弱音吐きまくってウンザリだったしなぁ。……もしかして、まさきって体力バカ?」
「体力バカって、もっと他にいい言い方があるでしょうよ」
「いやぁ、まさきを見てたら他の言葉なんか全然思いつかない」
強く否定されてしまった。恥ずかしいやら腹が立つやらで、あたしは頭から湯気が立ち上る一歩手前、ユメの顔を直視も出来ない。
「もおいいです! どうせ、あたしは走ることしか能のない体力バカですよ〜だっ! ユメなんか知らない!」あたしは拗ねてあっちを向く。
「なぁ、ユメ? もう少し女の子の扱い方覚えた方がいいんじゃないのか?」
何故だか、クロウがフォローしてくれていたけど、あまり効果なしのようだった。
「はは、いいよ、別に」乾いた笑い。「今にそれどころじゃなくなる……」
ユメの言葉、それはすぐに現実になった。
気分は最悪。あたしは頭から血の気が引いていくの感じた。まるであてがない。どんなファンタスティックな冒険だって行く先を見失うはずなんてないのに。あたしたちの前にあるはずだった道筋はぷっつりと途絶えていた。
「あたしたちは何を追っていけばいい?」
「さあ……?」ポツンとユメは言って教えてくれない。
だから、結局、あたしたちはヨウの言葉を信じて南へといくほかなかった。けど、誰が一番最初にこのことを記録に残したのか、あたしには不思議だった。こんな世界の片隅での出来事が語られる日が来るとも思えない。
「ねぇ、ユメ」つい癖で、ユメの袖を引っ張った。
「却下だ」間髪入れずに不機嫌な返事。
「なぁんで? あたしまだ何も言ってないよ」あたしは食ってかかった。
「どうせ、ロクでもないことを言う。しまいにゃ月の裏側見せろとか言い出しそうだ」
「そ、いくらあたしでもそんなこと言うわけないしょ?」
「じゃあ、何、言うつもりだったんだ」
「なあ、ユメ、俺さ。明日から一日、留守していいか?」
「え?」ユメとあたしで見合わせた顔を次の瞬間にはクロウの横顔を注目していた。
「そろそろ顔見せてやんないと、あいつ、ふてくされて手に負えなくなるからよ」
「つまり、何、恋人に会いに行きたいってこと?」
「簡単に言えば、そうなるな」
「あたしとどっちが大切なの?」クロウの背中をぐいっと押して詰め寄った。
「もちろん、あいつに決まってるだろ」寸分の迷いもなくクロウは言った。
「クロウ、どこかそこの街道筋におろせよ。もう、夕方だからこのあたりで一泊だ」
「ありがとうよ」前だけを見たまま、クロウは淋しげな空気を持っていた。
彼女に会いに行くのにどうして乗り気じゃないの? って聞こうと思ったけれど、あたしの中におかしなためらいが生まれて聞けなかった。
「別に構わないさ。その代わり、蜜たっぷりのリンゴはやめにして玉ねぎね」
「冗談でしょ?」ちょっと焦った裏返った声色。
「半分は本気。半分は冗談だな」悪戯っぽくニヤリとしたユメの笑顔が印象的だった。
「じゃ、いい。ユメたちは置き去りだ。迎えに来てやんないもん」
「てめぇは駄々っ子かってんだ」ぶつぶつ言ってる。「じゃ、俺は報酬やんないもん」
「え〜。ただ働きはもっと嫌」
「だったらちゃんと帰って来いよ。全部、リンゴで払ってやるから安心しろよ」
「う〜、判った」ちょっとだけしかめっ面で、不平たらたら。
でも、結局、クロウは何の未練もなく、ひゅーんと飛んで行っちゃった。また戻ってきて、会うつもりでいるんだろうから当たり前の反応なのかもしれないけど、五日も行動を共にしたんだから少しは名残惜しんで欲しいものもあった。だから、
「ねぇ、飛竜ってみんな、あんな風にたんぱくなの?」
「どうだろうなぁ。飛竜の友達はほとんどいないようなものだからな」ユメは空を見上げ、クスッと笑いながらあたしを見た。「でも、クロウに関して言えば情にもろいだろ」
「そっかな」首をひねる。
「でなきゃ、あの連中が人間にくっついてきてくれるなんてことはないのさ。正直言えば、シャンルーとクロウは飛竜族の変わり種。“ハグレ”って言うのかい? 群に入ってない。そして、あの連中はまず、ノーシーランドやグリーンズには寄らない」
「どうして?」
「まさきのいたところに飛竜はいたか?」ユメの瞳だけがあたしの方を向いた。
「ううん、いるわけないじゃん」
「つまりそう言うことなのさ」あたしはキョトンとしちゃって首を傾げた。「飛竜族は俺やまさきの世界の住人じゃないってこと。アクアとフゥ以外も幾つかあるみたいだぜ?」
こういう話が好きらしくてユメの目は嬉々と輝いてる。
「それと飛竜が人に懐かないのと何かつながりがあるの?」じとっと眺めて嫌がらせ。
「さあ?」面白半分に冗談めかして言っていた。
「さあ?? 言い出しっぺのくせに話、はぐらかすつもり?」にじり寄り。
「本気にするなよ。ホントを言えば、シャンルーやクロウは群に入れてもらえなかったのさ。どこか違うところから迷い込んで、……ここの飛竜ってのは元々そんな連中なんだけど。……クロウだってもといたところに帰りたい。シャンルーもね。帰るのを諦めた連中が――群れてるのさ」
「じゃあ、あの、その」あたしは聞いてしまうのが怖かった。
「チャレンジャーはほとんど死んだ」あたしの質問を察してユメが答えてくれた。「フゥの人がいるのは恣意的だけど、飛竜さんの方は“紛れ込んだ”の。多分、その差だ」
「うん……」あたしは完全に意気消沈していた。おっきな木陰を見つけて座り込んだ。
「そして、生きてるやつは諦めていない。ま、知ってる限りだけどさ」
すると、ユメは枯れ木を集めてくると言ってちょっとした防風林に入っていった。
「ちょっと、ユメ。あんまり遠くに行かないでよ」
森のはずれの小さな木陰でひとりぼっち。クロウは恋竜(?)のご機嫌取りに帰っちゃったし。飛竜の世界も人間の世界もその辺のことは大差ないんだなと思った。けど、この場合、あたしたちをほったらかして行っちゃうってのはひどすぎるんでない?
と、考えて愚痴ったって聞いてくれる人もいやしない。つまんない。
「ユメ〜。こ〜んな可愛い娘を放ったらかして、ぜぇったい後悔させてやる」
悪態をついても空しいだけだね。だから、あたしは西に沈む赤い大きな太陽をぼんやりと眺めていた。よく考えたら、のんびりと夕焼けの下で佇んでるなんて何年もなかったな。小学生くらいの時は夕焼けがとっても淋しかったのを覚えてる。毎日六時くらいになったら、「さっさと帰れ〜」って校区中に大音量の夕焼けこやけが鳴り響いてたっけ。それが鳴り終わるまでに帰んなきゃって、橙色の光の中を自分の長い影を追っかけて走ったのを覚えてる。友達と「バイバ〜イ」って別れて一人で帰路につくと、いっつも何かが追いかけてきそうで怖かった。
「おう、まさき。何、ポケ〜っとしてるんだ」
「な、ユメこそどうしてニヤニヤしてるんだよ」
「うん? ヒューマンウオッチング。まさきの百面相を見てると飽きないよ」
「ひゃく、めん、そう? こぉ〜んな美人を捕まえてそれはひどいんでないの?」
両手を大きく広げてちょっと大げさにポーズ付けたりして。
「バ〜カ」
むかつく。でも、何だかとってもいい空気。あたしとユメの間を涼やかな風が吹き抜けてしんみりとしていていいな。こんな場面に一人で出会ったら淋しくてあたしは泣いてる。ゆうやと会うまで夕焼けの街にあたしの場所はなかった。
「!」ユメの目つきが急に険しくなった。「まさき、立て、木陰に、急いで」
「な? むぎゅぅ」口を押さえられた。
「大声出すなよ。誰か、……そう、五、六人はいる。気配を感じる。ベリル、だな」
「どおしよ〜」泣きそうな声色であたしは言っていた。
それからザリザリと複数の足音だけが聞こえていた。あたしはユメの背中にしがみついて音のする方をずっと見ていた。
「……隠れても無駄です」抑揚のない声は男だった。がさつなリンネの声じゃない。
「隠れたわけなじゃない。お前の視界から外れただけだ」
「どちらでも構いませんが。そろそろやめにしませんか?」
「お前はネゴシエーターか?」すっごく訝しげな眼差しでユメは男を睨んでいた。
「ベリル……リンネはいないの?」
「判らん。と言いたいが、こいつら尖兵だろ。いねぇな。まさき、話し合おうと思うだけ無駄だぜ」
「尖兵とは失礼な言いぐさですね。わたしたちはベリルの情報部隊、あなたたちを探りに来ました」
争い、戦、そんな物騒な空気の中でそいつはやけに紳士的だった。
「正確には“殺しに来た”んだろ? 俺たちがあいつと会ったらうまくない。そうだろう?」
ユメは今まであたしに感じさせたことのないの凄味をきかせた。けど、ネゴシエーターには全くの無意味みたい。幾つのもの修羅場を駆け抜けてきたかのような余裕の笑みさえ浮かべていた。
「そこまで判っているなら話が早い。手を引きなさい」
そいつは腰に吊った剣に手を伸ばした。
「何故?」ユメはフッと力の抜けた笑みを見せた。「あいつと遭ったからと言って上手くいく訳じゃない。九割以上の確率で失敗する。いつも、見て見ぬふりをしてきただろう、今更」
剣を抜いた。ユメは落ち着き、剣の柄を握っただけだった。
「セイとまさきは似すぎています。倫一の気持ちが揺るがないとは限りません」
「イレギュラーな因子は今のうちに取り除くってことか。なら、二百五十六人目の倫一を消した方が早いだろ。新たなチャレンジャーと違って、あいつはずっとノーシーランドに腰を落ち着けている。逃げもしなければ、隠れもしない」
「……リンネが許してくれません」
そいつの発言にあたしは違和感を覚えた。セイとあたしが似ているとどうしてその“倫一郎”ってやつの気持ちが揺るぐのか。そして、不安定要素を取り除くより確実な方法をとらないのか。
「倫一に未練たらたらなのか。そこら辺は変わらないか」
「侮辱するのですか?」
「いいや、事実を述べただけだ」
ユメの言動にそいつはカチンときたみたいだった。表情が敵意に満ちて、目が三角になった。剣の柄をつぶれるくらいにギュッと握りしめて、ユメを睨め付けていた。
「リンネを作ったのがあなただとしても、そんなことが言えますか?」
そして、そいつは大きく息を吸うと、斬りかかってきた。その時、ユメは初めて剣を抜こうとした。目が違う。いっつも優しくて尖った目をしたことのないユメの目が怖かった。
「まさきは下がれ。……レイピアは構えておけ」
「でも……」
つい、反射的に反抗してしまう。人殺しの道具は持ちたくない。今更、綺麗事を言うつもりはなかったけど、これが誰かを突き刺していたかと思うと心穏やかではなかった。
「何も出来なくてもいいから、ちゃんと構えろ。最後の最後でてめぇの命を守るのは俺じゃなくてまさき自身なんだぞ。いつまでも俺がいると思うな」
「そんなぁ」あたしは泣きそうになる。
「泣き言は言うな!」
あたしは剣を振るうユメの背中を見ていた。「背中を守れるようになる」って豪語したところであたしには何も出来ない。手を出せば、ユメの足かせになる。だから、あたしはユメの後ろでふるえているしかなかった。
ギィィイイィンン!
剣が激しく交差し火花を散らした。ユメとそいつは見つめ合ったまま動かない。
「流石は我が将の兄上さまですか?」
「あいつの兄貴はずいぶん昔にやめたんだ。放っておけ。あいつは俺の妹じゃねぇ」
でも、あたしは衝撃的なユメの言葉を聞いた。セイは死んだんじゃなかったの? 殺されたんじゃなかったの? そいつとユメの言動を聞いていたら、あたしの中で一つの疑問が湧き上がった。
「ユメ! リンネがセイなの? 答えて!」あたしは怒鳴っていた。
キンっ!
そいつにユメが弾かれたみたいだった。
「教えていなかったのですか?」いやらしく口元を歪めるのが見えた。「あなたもひどい人です。何も告げずに実妹と剣を交えさせようとは。そんなに許せないのなら、お前が直接、手を下せばいいだけのことでしょう。自分に自由なセイが羨ましい……。違いますか、ユメ」
ユメはそいつの瞳を突き刺したまましばらく動かなかった。
「……お前に俺の気持ちは判らない」絞り出すようにユメは言った。「それに俺はまさきとリンネを対峙させるつもりはない。決着は俺がつける」
「そうですか……。では、尚更あなたをここから先に行かせられません」
そいつがパチンと格好良く指を鳴らすとワラワラとどこからともなく手に手に武器を持った輩が現れた。あたしが察するに彼らがベリルの精鋭たち。ざっと五、六人かはいるように見えて、ユメがどんなに強くても勝てないような気がした。
「数にものを言わせるお前らのやり方が気に入らない」
「そうですか」冷めた口調がカンに障る。
あたしはユメの鬼神のような戦いぶりを見てしまった。でも、ユメは人を殺さない。ユメの使ってる剣は剣と言うより刀だった。片刃の剣を持って、絶えず峰打ち。だけど、ユメは強かった。狙った場所を外さない強力な打撃は相手を一撃で伸していた。
「相変わらず、甘ちゃんですね。それでよく“一流”をやって生きてこれましたね
「ほっとけっ! 死にたいやつは殺してやるが、こいつらはただの手先だろ?」
「ま、そうですね」もうすぐ、ユメの刃が届こうというのに平気そうだった。
「けど、安心しておけ。お前は地獄の底まで送ってやる」
「そう言うわけにはいきません」
「さあ、来いよ」ユメが挑発してる。あたしと喋ってる時の目つきとは全然違っていた。突き刺すような眼差しでそいつの目から絶対に視線を逸らすことはなかった。「怖じ気づいたか?」
「バカを言うんじゃありませんよ」
そして、フッとキザな笑みを浮かべた。
「リンネの言っていたことを確かめに来ただけです。最初に言ったでしょう? ユメがそれほど肩入れするまさきに何が出来るのか見てみたい」
どうして、そいつがそんなことを言ったのかあたしには判らなかった。度々、出てきて剣を交えるけどいつも本気じゃない。何かを望んで、願っている見たいにあたしには感じた。他力本願なんて大嫌いだけど、ホントにそれしか仕方がないのかもしれない。
「倫一に会うのもいいかもしれない。……仮にそうなるとしたら、次に会うのはあそこですか」
あそこってどこだろう。けど、あたしは問えなかった。
「ベリルってのはつくづくおかしな連中の集まりだな」
「何とでも」ユメの悪態をすんなりと受け流してしまった。
「まあ。いいさ」ユメは何だか決まり悪そうに頭をかいていた。「五年前の決着をつけるとリンネに……セイだった女に言っておけ」
と、啖呵を切る夢を見て、そいつはほくそ笑んでいた。まるで予定通りになったと言いたげな凄く嫌な笑い。シェンリースーで会ったノスみたいな直線的なやつの方がまだあたしは好きだな。
「どうやら、ここに来たのは正解だったようです」
そして、そいつはあっさりと剣をさやにしまっちゃった。一体、何をしに来たのかあたしには理解出来ない。ユメに殺されるような危険を冒してまで、たったそれだけの事をしに来たとも思えない。だから、そいつの目的って他のところにあるのかなっとあたしは思った。
「……リンネはやっぱり、セイなの」
あたしはユメに聞いた。だって、もう聞かないわけにはいかないから。兄妹ゲンカが命の取り合いだなんて嫌だけど、知りたくなかったけど、あたしには隠し事をしないで。だから、今度はちゃんとした答えをもらうまで質問はやめないんだ。
「そうだ……」ユメはあたしの方を見てくれなかった。「ベリルの子どもに殺されたってのはウソ……。言えるはずがないだろ。セイがベリルに行ったなんて」
「うん……」
ユメはどれだけの重さを抱えてこの五年を過ごしてきたんだろう。セイに似ているあたしを見て、ユメはあたしを放っておけなくなった。だから、今もユメはあたしの傍にいるんだね。セイをなくしたみたいにあたしをなくしたくなかったから。
「ユメ、やっぱり、あたしはレイピアを使えるようにならなきゃダメなのかな?」
「――」
ユメは即答を避けた。しばらく、あたしの黙って見詰めていた。じっと、何かを訴える? ううん。ただじっと。あたしの心を見透かして、あたしの真意を推し量るかのように。
「誰も殺さなくたっていい。でも、いつもお前を守れるとは限らないんだ。こんな状況がいつまで続けば、俺だっていつまでまさきの前に立っていられるか判らない……」
「そんな……淋しいこと言わないでよ……」
あたしはユメの胸板を叩いていた。
「そんな辛いこと言わないでよ! ユメがいなくなったらあたし、ここで生きていけない。ユメがいなかったら、……あたし、帰れないよ。帰れなくなっちゃうよ」
「――お前は帰れるよ。一人でも。最初から決まってる」
そんなはずない。ボーダーランドの外れで青い目のボロの男に会わなかったら、あたしはここにいないはずだった。あの荒れ地で途方に暮れたまま野垂れ死んでいたような気がする。ジュンにもユメにも会うことはなくて。と思うと泣けてきた。
「おいおい、何でそこで泣くんだよ」困り果てたユメの声。
「だって、淋しいよ。帰ったってあそこに居場所ないんだもん」
「まさきの居場所はここじゃない」ユメはあたしの目を見ずに言った。
「ここだったら、あたしの居場所を作れるよ。だから……」
ユメから離れたくなかった。今、ユメから手を放してしまったら、あたしはあたしでいられなくなるような強迫観念があったのもホントのこと。でも、きっと、違うんだ。ゆうやを忘れたワケじゃない。けど、あたしはもう何かをなくすのは嫌だった。
「ダメだ、まさきは帰らなくちゃならない。どんなにがんばってもまさきはここの住人になれない」
「……」あたしは答えられなかった。
そんな折り、クロウが楽しそうな顔をしてデートから帰ってきた。「丸一日は帰ってこねぇぞ」って言ってたくせに半日くらい。ご機嫌にあたしたちの上をクルッと宙返りなんかしてる。何なんだろうね、あれは。
「よう、しけた面してるな。何かあったのか?」
「何かあったんだよぉ。でも、教えてあげない」
「……言わなくても、判るさ」
クリッとした悪戯っ子の瞳にクールな煌めきが宿るとあたしはドキッとする。クロウの澄んだ瞳にはウソはお見通しみたいだった。
「だから、俺は帰ってきたんだぜ? 最後までつきあってやるぜ、まさき」
その瞬間、クロウがもの凄く切ない表情をしたのをあたしは見逃さなかった。クロウこそ隠し事をしている。あたしには判った。女の勘ってやつかな。クロウは別れに行ってきたんだ。楽しそうに空を飛んで、あたしたちに感づかれないようにしたつもりなんだろうけど。
「恋人と別れてきたんでしょ」あたしはあたしは腕を組んで、強い口調で言った。
「どうして?」きょとん。全然動じていやしない。腹の立つ。
「どうしてって、さよならを言いに行ってきたんでしょ?」あたしのほうがうろたえちゃう。
そうしたら、クロウは胡乱そうな眼差しであたしを見詰めると、突然、ケラケラと笑いだした。
「勘ぐりすぎだぜ、ま・さ・き。俺はそんなに甲斐性なしじゃねぇ!
「うな?」あたしはびっくりして素っ頓狂な声を出した。
「たまには顔、見せてやらんと拗ねちゃうから。判るだろ、まさきなら」
瞳がクリッと閃かせて、クロウがあたしに微笑みかけた。
「な〜んだ、結局、尻に敷かれてるってコトか」
「うるさいだよ」でっかい目玉がギョロッとあたしを睨んでた。
「なあ、もう、いいか? 折角、クロウも戻ってきたし、行こうぜ。ベリルも悠長には構えていられないだろ。……次に来る時は奴らも本気だ。時間もあまりない……」
あたしたちの下らないやり取りに業を煮やしたみたいだった。
「あいつのところに行くのか?」これはまた気乗りしなさそうにクロウが言った。
「ああ、高速の翼を持ってるんだ。行かなきゃ、損だろ」
「リンゴ、もう一トン、よこせ、そうしたら考えてやる」
クロウはそっぽを向いて、遠慮がちにボソボソ言った。
「聞こえないな」余裕の笑みを浮かべて、ユメはクロウの背中をぶっ叩いていた。それでいて、クロウが怒らないところを見ると二人はとっても仲良しなんだね。
「余ったタマネギでよかったら、考えてもいいけどな」
「だから、水っぽくて辛いのは嫌いだっていってるだろ?」クロウの表情は渋かったけど、目は笑ってた。「追加料金をいただこうと思ったんだけどね。ま、いいや、乗れよ」
クロウはあたしたちに背を向けて、尾っぽであたしの足をくすぐった。
そして、再び空の人。大断絶を北の端に持つ大森林地帯・ノーシーランド。どこまでも続く針葉樹と広葉樹の混成樹林帯。深緑の尖った梢と、淡い緑の扇形に広がった梢。あたしは普段なら、見られないものを、絶対にあり得ない条件で観察していた。
「でよ」クロウの声風に負けそうになりながら聞こえた。
「あの山の麓に梢から出っ張ってる松の木が見えるだろ」
ユメはクロウの背中に腹這いになって、その方角を指した。
「あ〜あるね」まるで興味なさそう。「あるのはいいが、俺、どこに降りたらいいわけ?」
「もちろん、垂直着陸!」あたしは茶々を入れた。
「出来るか、ぼけ!」本気で言ってるんじゃないのに、ぼけ扱いはひどいんじゃない。
「……池に着水しろ……」
「……」間の悪い沈黙。クロウが滑空する音だけが妙に大きく聞こえていた。
「マジで言ってる?」
近づいてくるその松の木をみんなで見詰めていた。
「マジで言ってる」抑揚のない平坦な声。
「……あっそ。追加料金よこせ」
「断る。……が、タマネギなら払ってやるって言ってるだろ?」
ひ〜、一体どうなっちゃうんだろう。あたしはドキドキしながら二人を見守った。剣呑な雰囲気で一触即発。クロウは不機嫌そうにうなるし、ユメは譲る気は全くないようだった。
「あ、あの、ケンカはやめて、ね、ね?」
「俺たちがいつケンカしたって?」二つの声が重なって、二個の瞳がこっちを向いた。
「あう。見詰めないでください」あたしは思わずうつむいた。
結局のところ、この二人ってケンカするほど仲がいいって言うのを地でいってるみたいだった。初めてあった時、ユメとクロウが知り合いだなんて思っていなかったけど、それはどうやら大きな間違い。そのやり取りを聞いていたら、結構、古くからの友達のように思えてきた。
「そいでよ。ポーッとしてたら池に落ちるよ」
「え?」
クロウの言葉にあたしはハッとした。もう、水面がそこまで迫っていた。クロウの巨体が梢をかすめて池の上を一回、超低空飛行で水飛沫を上げながら通り抜けた。そして、再び上昇。滑空出来る距離を測ったらしい。クロウは空中で大きく旋回して、着水にチャレンジを始めた。クロウは着水目標地点に狙いを定めて、降下を始めた。
池が視界いっぱいに広がるのと同時に、クロウは池の上を滑るように滑走していた。水飛沫を派手に上げて、舞い上がった飛沫が頭の上から振ってきた。水浴び。と言えば、少しはステキな気分だけど、服の上からの水浴びなんて最低な気分。
「……最悪ぅ。頭のてっぺんから足の先までびちゃびちゃだよ」
「どこか、そこら辺の木陰に行って着替えてこい。待ってるから」
「はぁ〜い」あたしは気のない返事をした。
そして、歩く。方向をしっかりと見定めて、初めて来たような足取りじゃなかった。以前もユメはここに来たことがあるに違いない。あたし以外の誰かを連れて。ちょっと焼けるな。けど、女の子は初めてだって言ってたから、男か、なら別に構わないか。
森の下草をかき分けて、あたしとユメは歩き続けた。
「方向はこっちであってるの?」足場の悪い道なき道を歩くのは流石に疲れた。
「引っ越ししてなければ多分あってる」
「それでも『多分』なの〜?」あたしは駄々をこねた。
「それでも『多分』だ」ユメはずっと前を見ていた。
まるで何かを警戒しているかのようにユメの背中が緊張していた。と言っても何に警戒しているんだろう。ここは森の中だけど、空の上から見た限りじゃ、すぐに草原があったし、どう猛な動物もいなさそうなところだった。鹿、熊、狐、狸。いそうと言えばいそうだけど。一番危険そうな熊だって、ユメなら一撃で倒せそうだった。
そして、ユメは不意に立ち止まった。
「俺のなわばりを荒らしてるのはどこのどいつだ?」
男の渋い声だけがして、姿は見えない。あたしはキョロキョロと辺りを見回したけれど、どこにいるのか判らなかった。もしかして、透明人間とか。ちょっと、バカみたいな事を考えて恥ずかしくなった。
「下らないことをやってないで、降りてこい!」
「何だ? ユメか?」今度は頭の上から声が届いた。
「何だじゃない。どうせ、知ってたんだろ。クロウが着水した時から」
「まあな」
木から身軽にするすると大男が降りてきた。シェンリースーで会った男なんかよりもずっとたくましくて、格好がいい。顔も身体も引き締まって凛々しい笑顔。眼もキラキラとして、淀んだところはどこにもなかった。そうしたら、ふと「瞳は生き様を映す」誰かが言った言葉を思い出した。ジュンもユメもスイもレンも綺麗な瞳をしてたな。あたしの華やかだけど荒んだ人の曇った瞳はなかった。
「セイ?」
ユメと一通りの言葉を交わしたあとで、男はあたしに気が付いたようだった。
「あ、あたしはセイじゃない! まさきって言うの」
「まさき? ということはてめぇが噂の五百十二人目か、ここまで来たからどんな猛者かと思ったらただのガキか」
「ガキって何よ。ガキって。十八はもう、十分、大人だもん」思わず憤慨。
「俺から見りゃ、てめぇなんざケツの青いガキだ。……ま、いい。折角、遙々来たんだ。寄ってけ。……と、挨拶がまだだったか。俺は倫一」
「倫ちゃんって読んでね」横からユメが茶々をいれた。
「うるせえ! とっとと帰れ」顔を真っ赤にして、あたしたちを腕でなぎ払おうとした。
「そうはいかないだろ。断っても、寄らせてもらうぜ」
どっかでそのセリフを聞いたような気がする。ユメってどこに行ってもそうなのかな?
「は、相変わらず減らねぇ口だ」倫ちゃんは笑いながらあたしたちを誘った。
「でよ。常套句になっちまったが、言っておくぜ。まさきにゃ、無理だな」
「何でよ? 会ったばかりで何が判るん?」あたしはつっけんどんに言った。
「やつらはてめぇが考えているよりもずっと卑劣だぜ」
「卑劣?」眉をひそめて、りんちゃんをじとっと湿っぽく見詰めちゃった。
「来たときは二人だったはずだぜ? やつらは必ず大切なものをけしかけてくる」
「でも、ボーダーランドの隅っこに来たとき、あたしは一人だった……」
あたしはぶすっとした表情で男を睨んでいた。
「はぁ〜ん。やつもだんだん巧妙になってくるね。だが、二人だ」男はあたしの瞳を見詰め返し、左手の中指と人差し指を立てて表現した。「てめぇはやつがホントに何を望んでいるのか知っているのか?」
「し、知ってるよっ」あたしはうろたえそうになるのを必死でこらえた。
「何を」面倒くさそうにあたしに問いかけてきた。
「もう一つの瞳、フゥリュージョンを探すんでしょう? 二つの世界を一つにって」
「ちょっと足りない」やっぱりなと言いたげな冷めた視線があたしを刺す。
「う、くく」
あたしは真っ赤。すると、ユメがあたしの肩にポンと手を置いて前に出てきた。
「ユメ!」今まで見たことのないような凛々しい表情だった。
「アクアリュージョンは試しているのさ。生き別れた、二つが一つになるのに値するのかをね。そして、何故、諦めもせずに五年間五百十二人もここに来たのか……。今のまさきにならきっと答えられる」
「フゥと並ぶことを諦めきれないんだ」
それだけはあたしにもすぐに答えられた。あの日、ゆうやが言っていたことを忘れていない。『二つ並ぶことを夢見ているんじゃない?』あたしも見てみたかったから。あたしとゆうやがまた会うために。
「そう言うことさ。誰も気付いていないけど、二つの世界は強烈に引き合ってる。アクアの連中がどんなに望まなくて、妨害してもやがて二つは一つになる」
「……じゃあ、あたしじゃなくても良かったんだね。誰でも良かったんだ」
「それは最後まで行ってみなければ判らないぜ?」ユメがクスリと笑った。「まさきじゃなきゃダメな理由がどっかにある。そう思わないか?」
ユメが真顔で言えば、りんちゃんが鼻で笑う。
「てめぇがファイナリスト、か?」ちゃんちゃらおかしいと言いたげな視線。
「あたし、何も出来ない。あの日だって、偶然、美術館にいただけ。ホントにたまたま。たまたまなんだよ。別にあの日にあそこに行かなきゃならない訳なんかなかったし」
「じゃあ、必然だったと思うようにしないか?」ユメがクリッと瞳を煌めかせた。
「え? ど、言う、意味、それ?」
「ここに来るためにその日、まさきとゆうやは美術館の、しかも、アクアリュージョンの前に立っていた。言い換えれば、あいつはまさきたちが来るのを待っていた」
「あたしを待っていた? そんなはずない。そんなはずないもん」と、あたしはふと思った「ねっ! 最後まで行けた人っているの?」
「いるよ」拍子抜けするくらいの勢いで答えてくれた。
「だったら――」
「続きから始めりゃいいって言いたいんだろうが、でもダメだった」りんちゃんがあたしを遮った。
「どうして?」間髪入れずにつっこんだ。
「言ったろ? 試されてるって」ユメがりんちゃんが口を開くのよりも早く答えた。
「……監視カメラ付きなのかぁ。やんなっちゃうなぁ。ね、ずるしたら何かあるの?」
へんてこな好奇心に駆られてあたしはユメに質問した。
「何もないよ。知ってる限りではね」
「ふ〜ん、そっかぁ」
「まさき、何かたくらんでるんだろ?」
「ううん、別に」
何かたくらんでみたところで、アクアリュージョンを出し抜くような考えなんてすぐには思い浮かばない。それにそんなことが出来るならとっくに誰かがやってそうな気がした。あたしの前に五百十一人もいたんだから。高校生なのはあたしだけだし。
「でも、きっと、みんなと違うことをしなくちゃダメなんだろうね……」
「まさきはもうみんなとは違う」どう違うのかはあまり聞きたくない。
「ああ、違うな」攻撃的だったりんちゃんの瞳が不意に和らいであたしを見ていた。「一番違うのは……てめぇがこっち側に来たってことだ」
「どいう意味? それ?」キョトンとしちゃった。
「こう言っちゃあ、腹立てるんだろうが、女はいつも助けを待つお姫さまの役だったのさ。ところが今度は救出されるのは王子さまときたもんだ」
「王子さまが助けられちゃダメなの」
「ダメじゃないさ。ダメじゃない。けど」
けど、何だったんだろう。ユメは言葉を切ったまま何も言ってくれなかった。すると、りんちゃんがユメの代わりにちょっとだけ喋ってくれた。
「……最後が一番辛いのさ。みんな、そこで心を壊した。そう言うことだ」
「そう言うことってどういうこと?」やっぱり問いただしたくなった。
「行けば判る。そう言うとこだ」
二人してまともに答えてくれないなんて一体どういう事よ。と問いただそうと思ったけれど、二人の周りの空気がどよよんと淀んでいてとても聞けるような雰囲気じゃなかった。
「ど、どうしたんよ?」
「まさきは――まさきのままでいられるのかなってさ」
りんちゃんが頭の後ろで手を組んでそのまま後ろに倒れるように寝転んだ。そして、あたしはりんちゃんの言葉に言い表せないような焦りを感じた。
「あたしが死んじゃう? 帰れないって?」
「いや、そうじゃなくてよ。――いや、フェアじゃねぇな」
「生きて帰ったやつはいない」ユメの眼差しは険しくなっていた。「帰れずにこのアクアリュージョンに留まったやつもかなりいるけどな」
「それが、え〜と、マルーンヒルの誰だっけかが言ってたやつ?」
「そ、治安が悪くなる。実際、まさきみたいに優しいやつなんか片手に余るよ」
「あたしがそうなるって事? でも、みんながみんな悪い人じゃないと思う」少し腹が立った。
「それはもちろんだ。でも、善人より悪人が目立つのが世の常さ。しかも、それで大方判断されちゃうんだよね」ユメは間違ったことを言っていない。けど、あたしは悔しさでいっぱいになった。
「あたしは……がんばってる。でも、誰も認めてくれない。認めて欲しいんじゃないけど、けど、せめてあたしだって一生懸命やってるんだって判って欲しい」
どうして、あたしはユメにそんなことを言ったのか判らなかった。ユメは知ってる。少なくともあたしがあたしなりにやってるってコトを認めてくれてる。
「そんなことは判ってる」ユメが静かに言った。
「うん――、そうだったね」
あたしが帰ると言うことはどういうことなのか、ここの人たちは知っていた。二つの世界が一つになる。どっちの世界が母体になって、どっちの世界が吸収されてしまうのか。はたまた、二つは重なり合うようにそれぞれの特徴を残して一つになるのか。どの結末が巡ってくるのかは判らないけれど、そうなることを心得ていた。
だから、当然、あたしが帰ろうとあれこれ画策するのを快く思わない連中もいて……。アクアリュージョンの謎かけよりも、妨害工作を阻んで先を目指すことの方が数段難しいようだった。でも、あたしにはユメとクロウがいる。何がどうでも絶対帰る。
そして、そのまま夜は更けた。