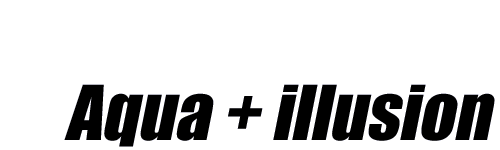
06. フゥの試練、アクアの望み(1)
「ユメ、まさきを連れて行くのか?」
「そのつもりだ。まさきなら、大丈夫」
前の晩、ユメとりんちゃんが話し込んでいるのがちょっとだけあたしの耳に届いていた。全部は覚えていない。けど、とても大事な話のようだった。炎の中で木の弾ける音にかき消された会話だけど、ニュアンスは何となく伝わった。
「あいつなら、答えを見付けられる。自分で考えて、行動してる。怒って、笑って、泣いて、珍しいやつだよ」そして、ユメは少し黙ってから、「あいつの百面相は面白い」
な、何でそんなことを言うかなあ。あたしはユメたちの背を向けたまま真っ赤になった。
「惚れたか?」からかい半分のりんちゃんの声が聞こえた。
「さあ?」はぐらかしてる。
それとも、ユメはあたしが狸寝入りをしているのに気がついていたのかな? 嘘でもいいから肯定の言葉が欲しかった。あたしは一人。ユメに嫌われていないことを確かめたかった。
「ま。てめぇを見てりゃあ判るわな、で。あそこに行くのか……。――あそこに行くって事はてめぇはまさきがファイナリストになると信じるんだな。だが、知らない方がいいこともある」
ごそごそと音がして、ユメは首を横に振っていたようだった気がする。
「見せておくべきだろう……。実はもう呼んだんだ」誰を……?
「手回しがいいな。流石ユメだ」
あたしはユメにどこかに連れて行かれるらしかった。けど、あたしはユメに聞かなかった。そこを実際に見るまで聞いちゃいけないような気がした。うん、きっと、聞いても答えてくれない。ユメはそう言う人だ。大事なことは人に聞かずに自分の目で確かめるんだって。
明けない夜がないように解決しない問題もない。そんな勢いで、あたしがアクアリュージョンに来て六回目の夜が明けて、朝が来た。昨日よりはずっと気持ちは楽だったけれど。思いの外、早い内に旅の終わりが来ちゃいそうなことをあたしは薄々感じ始めていた。淋しい。ここまで、そんなことを考えたことは一度もなかったのに。仮に終点に行き着いたら、あたしはみんなと別れなくちゃならない。
あたしたちはりんちゃんの家を出発して、昨日クロウが着水した池に向かって歩き出した。散々、ぶ〜たれてたけど、ちゃんと待ってくれてるのかな? 責任感なしの外道だとは考えたこともないけど、理由もなく不安になる。けど、ユメは至って平静で、仮にクロウがどっかに行っていても自分たちが戻るまでには帰ってきてる。とそんな風にクロウを信用してるように思えた。
「……どうした? 元気ないな?」
別に元気がないワケじゃないんだよ。けど、あたしはそれは言わずに他のことを言った。
「ゴールインも間近なのかな?」少し気になってあたしはユメに問い掛けた。
「さあね」乾ききったつれない返事。何だか、腹が立つからあたしは意地悪をする。
「帰ったって、もう、あたしのいるとこなんかどこにもないよっ――」
「まさきっ! へこたれるな。フゥリュージョンへ帰るんだろう?」
少しだけ関心があたしに向いたみたいで反応がウェットになる。と言っても、よそよそしいぞ、ユメ。何か、あたしの判らないような心配事があるのか、ユメは微妙にあれだった。舌足らずな言葉じゃ説明出来ないくらい。ちょっとだけ変なユメ。
「ねぇ? さっきからちょっと変じゃない?」聞いてみる。
「変じゃない! いつも通り」
怒られた。そしたら、また急に淋しくなって、あたしはユメの瞳に訴えかけた。
「へこたれそうだよ。どんどん自信がなくなってく。大切なものが零れ落ちていくような気がして仕方がないんだ。あたしはどうしてここにいるの?」
「フゥリュージョンに帰るためだろう? 大切な誰かがまさきの帰りを待っているからだろう」
「誰も待ってない」あたしは膝を抱えてうずくまりたい気分になった。
「父さん、母さんが待っているのはホントのあたしじゃない。待っているのは……自分たちの思い通りに動く“お人形・まさき”だもん。ゆうやもいないし」
「ゆうやってあいつか……?」
気遣うように優しくユメは言ってくれた。あたしはただ頷く。
「……フゥに頼んで見ろよ……。『一緒に帰らせてください』とか『見付けてください』とか」
「え?」思いもかけないユメの言葉にあたしは目をまん丸くしていたのに違いなかった。
「アクアリュージョンが人を他の土地に飛ばせるなら、それくらい造作もないことかもしれないよ。ダメ元で聞いてみるだけ聞いてみればいいさ」
「けど、その消極的な態度は嫌だな。やっぱ、その、待って捜してもらう……? 他力本願で物事を解決しようという姿勢は――サイテーだね」
「まさきならそう言うとは思ったけどな。そう、願うやつも多い」
「待ってるだけなんて、ダメだよ。天は自ら助くる者を助くって知ってる?」
「ああ、けど、たまには力を抜いてみるのもいいもんさ」
ユメの言ったその言葉はいつしかあたしの微かな希望に化けていた。帰りたい、でも、帰りたくない。けど、本当の意味であたしのいる場所はこの世界にはないのかもしれなかった。五百十二人目の挑戦者。所詮は異邦人。グリーンズの町の人たちは好意的だったけれど、みんなの瞳はそう訴えているようにあたしには映っていた。
「そうだね。ウジウジしてても仕方なかったね。言わない思いは伝わらない!」
「そうそう。その意気さ! くよくよしているまさきはらしくないよ」
「そうだよね」
そうだけど、あたしはそんなに強くない。今だってあたし一人じゃどうにも出来ない不安感に押し潰されてしまいそうなのに。終わりが近づいている。けど、ホントに終わるのかどうか判らなかった。ゲームオーバーか、トゥルーエンドか。デジタルな下らない思いもあたしの頭をよぎった。
「けどな――」声のトーンを落としてユメはいう。「困ったら、遠慮しなくてもいいんだぞ」
「うん……、ありがとう」ユメの左側につと寄り添って、あたしは素直に言った。
「……くっつくな、暑苦しい……」
何だとう、この! 可愛い娘が抱きついてあげたのになんて言いぐさだ。でも、ホントは照れてるだけなんだよね。だから、手を振りほどいたりしないんだよね。
そしたら、その様子をクロウが池から呆れたように眺めていた。
「朝っぱらから、見せつけてくれるな、お前ら」
「うるさい。まさきがくっついて離れないんだ」
嬉しいくせに。とは言わなかった。ちょっと嬉しそうにしてたから水を差すのも可哀想かな。
「どっちでもいいけどよ。微妙に変わったな、雰囲気」
「黙れっ!」
ユメはめっと言う勢いでクロウを睨んだ。けど、クロウも慣れたものなのか、生返事。手があったら、頭を掻き出しそうだった。
「ところで、ヨウからから借りてきた本は読んだか?」突然何を言い出すかと思えば。
「うん。ざっとはね。けど、どうして?」
「別に……」そう言われてもあたしはヨウの本の中身を思い出していた。
世界はかつて一つだった。テレビゲームでしか見たことのないような記述に出会った。アクアリュージョンとフゥリュージョン。二つの世界に分断された『とわの瞳』がすべての鍵を握る。アクアマリンとファイアレッドの瞳。それぞれが水と炎を司り、水の門と炎の門を統括する。何だかよく判らないけれど、あたしが最初の通ったのが水の門のようだった。そして、そのゲートは一方通行らしく、こっちからあっちに帰るには炎の門を開けなければならない。
「けど、突飛なイメージがあるんだけど、それってホントなの?」
「少なくとも嘘じゃない」
と、水平飛行を続けていたクロウが高度を下げはじめた。カクンと小さなショックがあって、空ばかりと遠くの山が見えていたのが、下の茶色い地面も見えてきた。
「ねぇ、あっちの方に見える変なぼっこの集まりみたいなのは――」
あたしは右手に見えるそれを指した。けど、ユメは無反応。黙って前だけを見て答えてくれない。あたしは仕方なく、また地面を見下ろした。すると、その辺の棒の群れの手前には崩れ去った何かの跡が見えた。廃墟。きっと、そうだ。ここに来るまでに見た街はたったの二つ。ユメたちのボーダーランドの小さな町とグリーンズのマールンヒル。
何故、ここにはこんなに人がいないのか。不意に疑問が湧き上がった。
「ねっ、ユメ?」
いつものように服の裾を引っ張ろうと思ったら、クロウがさらに高度を落とした。あたしは意表をつかれたその挙動にクロウの背中から転がり落ちそうになった。
「ちょっとっ! 落ちたら、死んじゃうでしょ?」がなる。
「まさきなら、大丈夫だよ」ケロッとしたようにクロウが言う。
「それじゃぁ、あれかい? 不死身だって言いたいの? あたしは魔物かって!」
「……」ユメがキョトンとして見てる。「――魔物じゃないのか?」
「げっ。ひどいんだぁ。ねね、クロウは?」
「右に同じ」瞳だけをくるんと後ろに、あたしを見て言った。
なんなんだ、この男どもはっ! か弱くて、清楚で、こんな可愛らしい娘を捕まえて“魔物”とはどういう事だ。それとも、妖精とかそっちの……。
「ユメ、セイレーンとか、ヴァルキリーとか――」
「差し当たって」差し当たって? ユメはじっとあたしの顔を見詰めた。「……ハーピーかな?」
「あ、あたしは鳥女かい!」
憤慨してユメに食ってかかったら、クロウが着陸態勢に入った。そのころには高度も随分下がっていて、木々の梢と同じだった。さっき見えた廃墟も間近に迫ってすぐそこだった。昨日の夜、ユメが連れて行くと言っていた場所はあそこなのかな。お化けがでそうな雰囲気なんか、とうに通り越して、湿っぽい怖さなんて消し飛んでいた。軒を連ねる廃屋もかつては人家だった面影すら残していない。ただ、それはそこにあった。
「……かつて、ノーシーランドで最も栄えた街・フォーレスタ。今は……挑戦者の墓場……」
あたしはごくりと唾を飲んだ。何で、こんなところにあたしを連れてきたの?
「ユ、ユメ?」声が震えた。
と、同時にクロウの足が地面についた。水飛沫なんか上がるはずもなくて、草がクロウの滑走したとおりに見事になぎ倒されていた。
「よっと――」フォーレスタを訪れるにあたっての前振りはなくて、ユメはクロウの背中からとっとと飛び降りた。「まさき、早くしろよ――、人を待たせてる」
「え、何? よく聞こえない」
と言いつつも、誰かを待たせてるとか何とか。あたしは尻尾を伝って地面に降りようとした。けど、クロウは尾っぽを左右に振ってあたしの邪魔をする。
「こら、クロウ。尻尾フリフリするな! 降りられないじゃない」
「そんなに高くないぜ? 飛び降りたら?」クロウは意地悪にニヤリとした。
「怪我をしたらどうするのさ?」
あたしは地面に飛び降りる代わりにクロウの上で飛び跳ねてやった。
「オレの背中で跳ねるな!」
「へんだっ! あたしを邪険に扱った報いだ」
クロウの尻尾の動きが止まったのを見計らってあたしは駆け下りた。
「お待たせ、ユメ」
「何をやってるんだか……」呆れられちゃった。けど、いいんだ。ちょっぴり楽しかったから。
そして、あたしはかつて街だった場所を見た。そこにはどこまでも軒を連ねた廃屋は日本の建築物みたいだった。あたしは遠くに来たんじゃない。きっと、ここはSFのパラレルワールドみたいに隣り合わせなんだ。何か、些細な出来事が切っ掛けになって一つの世界は二つになった。
「まさき?」放心してたのか、ユメが心配そうな顔をして近づいてきた。
「あ、ごめん。大丈夫だから。ただちょっと見てただけ」
ここの文化はあたしが想像するに、日本そのものみたいだった。と、ぐるりと辺りを見回していたら、スッとあたしの瞳の中に見覚えのある顔が映り込んだ。
「まさか、マスター? どうして、どうやってここに来たの?」
シェンリースーのマスターだった。大断絶を越えてグリーンズからここに来るには、一週間以上かけて回り込むか、飛竜のお世話になるしかないはず。けど、マスターはあたしの浅はかな考えを見透かしているようだった。
「飛竜は……クロウだけじゃなかったはずだよ」
「シャンルー……、あの子、飛べるの?」暗い洞窟の奥で佇んでいるシャンルーの姿が浮かぶ。
「飛べない訳じゃない。しかし、外れだ。クロウの恋人は知っているだろう?」
思いもかけないマスターの言葉にあたしはただ頷いた。
「うん……」
「……そこにいる」マスターはそっとその方向を示した。
あたしはドキドキしながらそっちを向いた。すると、クロウとその娘が談笑してた。それって一体どういう事なのさ。この前あたしの勘が外れたこともしゃくだけど、クロウが別の女の子と――って飛竜に嫉妬してどうするつもりなんだろう。あたしは燃え上がるように自分の顔がぼっと赤くなるのを感じた。
「お? まさき、そんなところにいたのか? 紹介するぜ、俺の彼女。マイちゃん」
「マイちゃん?」このクロウめ。あたしのこの繊細な乙女心をなんだと思ってるだ。
「お噂はかねがねお聞きしてますわ、まさきさん」
と、言われた日にはいやになっちゃう。クロウのやつ、マイに一体何を言ったんだろう。でも、聞いたら、どうせいいことなんか言ってくれないだろうから、あたし自身が滅入ってしまいそう。だったら、聞かない方がいいよね。
「はぁ、クロウくんに彼女がいるとは聞いてたけど、美人さん……なのかな、ユメ?」
あたしは隣にいるはずのユメに問う。
「俺に聞いてどうするんだよ。飛竜の美的センスなんて知らん」
「知らないなんて連れないことを言わないでよ」
マイがあたしをじっと見てる。それ以上でも、以下でもないようだけど、何か気になる。何かを期待してるのか、訴えかけてるのか、哀れんでるのか、そんな眼差しだった。
「まさき、マスターが待ってる」
ユメが言う。そして、ユメの顔を見たら、この前、クロウが恋人に会いに行くといってたのはこのためじゃなかったのかなって思った。マスターを連れてくるために。
「あ、うん」あたしは急に気恥ずかしくなった。「でも、どうしてこんなところに来たの?」
「フゥに行くまでの最後の“試練”だから」
あたしの心臓はドクンと大きく脈を打った。もうすぐ旅の終わり。クロウの翼を手に入れたから、あたしの旅は長くはなかった。けど、今までのみんなはまだどこかを歩いている。
「そして、まさきの先輩たちの墓場」
「それは……?」
マスターは背中で手を組んであたしの前を歩き出した。付いてきなさいという意味なのかな。あたしはマスターの真意をはかりかねて、ユメに助けを求めた。すると、ユメは瞳を閉じてそっと頷いた。マスターに従えって受け止めてもいいんだね。
あたしはちょっと遠くなったマスター少し曲がった背中を追い掛けて、走った。
「マスター。どうして連れて行く気になったの?」
「まさきが……真のファイナリストだからだ」
「え? 何、それってどういう意味?」
けど、マスターはそれ以上はどうあっても答えてくれないみたいだった。腰の辺りで手を組んで、昔は繁華街だったような街並みを抜けていく。ずっとずっと。クロウの背中に乗って飛んできたあたしにはとっても長く思える道のり。でも、実際には二キロも歩いていないんだと思った。やがて、十字架じゃなくて卒塔婆の見える風景が目に入った。空から見えていた棒の群れがこれなんだ。これでカラスでも飛んでいたら、幽霊でもでそうな日本の墓地と同じなんだろうけど少し違った。どこまでも続くような卒塔婆の群れは背丈のある雑草に半ば埋もれていた。手入れをしてくれる人はいないんだ。あたしは淋しくなった。
「……あ……」気付いた。
一カ所だけ、草が綺麗に刈り取られて、手入れをされている場所があった。
「気がついたかな……?」マスターがとても儚く切なさそうな声色であたしに言った。「全ての手入れをしてやれればいいんだが、墓守は性に合わんし、寄る年波でな」
気を抜いたら、あたしもここに仲間入りをするとマスターは言いたいのかな?
「こっちに来てご覧」
マスターはあたしを促した。墓石こそなかったけど、卒塔婆の周りはきちんと片づけられていた。マスターの様子から察するに、手入れをしてるのはマスターなんだね。他のところは放っておいてもここだけは綺麗にしてるなんて、マスターの大切な人だったのかな。
「――助けてやれなかったんだよ――」
「まさか、そんな――」マスターが短くそう言った瞬間、あたしの思考はある一点に帰結した。
その思いはどんなにがんばっても振り払えなかった。シェンリースーでユメの言ってた事、ボラーランドの丘の向こうで会ったおじいさん。「そんなはずはないよね?」
あたしは動揺を隠せないでオロオロしていた。だって、マスターみたいな人が。あたしはどうしてか判らないけれど、泣きそうになって、後ずさりをしていた。そうしたら、背中が何かに当たった。振り向くとユメ。暫く、あたしの瞳を見詰めて、そっと語りかけてくれた。
「まさきの思った通り、マスターは最初のファイナリスト」
「最初のファイナリスト?」あたしはオウム返しをした。
「そして、まさきは最後のファイナリストになる。きっと。だから、マスターを呼んだ」
ユメは最初からおしまいまで全部、どういう道筋を辿っていくのか知ってるみたいだった。あたしは涙に潤んだ瞳でユメを見た。
「ファイナリストって?」
マスターが試練に臨んだ人だって事は判ったけど、ファイナリストってどういう意味なんだろう。
「――最後まで辿り着いた人」
それが判らないほど、あたしはお間抜けじゃない。だから、あたしは瞳でさらにユメを促した。
「――フゥを手に取る直前まで来た挑戦者のことをそう呼ぶようになったのさ。いつの間にか」
あたしがファイナリスト……。
「終わりはどこにあるの? いつ来るの?」
と問えば、ユメはただ首を横に振った。流石のユメといっても、ガイド的な枠割りで詳細を知るには至らないようだった。それはヨウも同じで、あの本には肝心のそこだけは空白になっていた。
「聞くのは俺じゃないよ……。マスターに聞いてご覧」
マスターは卒塔婆の前に膝をついて手を合わせていた。
「マスターの奥さん?」不意に思った。「……え、このチャレンジってここ五年だって。マスターがここに来たのは五年前?」
「答えはノーだ」後ろからユメが来て、その問いに答えてくれた。「俺が物心つく前からマスターはシェンリースーにいたよ」
「わしがここに来たのは四十三年前。その後に数十人呼ばれて、そのまま終わったよ。ファイナリストはわし一人……。アクアはがっかりしたのかも知れないな」
それは幻滅して諦めたって事なのかな。でも、二人が会いたいだけなら、こんな面倒くさいことなんかしなくてもいいはずなのに。すぐに見付けてもらえるようにし向けたらすぐにおしまい。アクアリュージョンが五百十二人もの挑戦者を叩き込んだのはこっちで埋もれたパートナー・フゥリュージョンを探し出すためのはず。わざわざ、手の込んだことをして遠ざける訳が判らない。
「納得のいかなさそうな顔をしているよ。マスター、まさきの破滅的な好奇心に火がついたら、止められなくなるよ」
ニヤニヤしながらユメが言う。うるさいよ、ユメ。あたしは声に出さずにユメを睨んだら、ユメは肩をすぼませてやれやれとして見せてくれた。
「二つの世界を融和させるのには条件がある……。それは秘宝を見付けただけじゃダメなんだ。ただ、くっつけるだけで気持ちが晴れるなら、ここまではしないはず」マスターは静かに言った。
「アクアリュージョン・フゥリュージョン。二つの世界、二つの秘宝」呟いてしまう。
「ココロとモノ」マスターがあたしの呟きに応えるかのように言った。「暫く考えてご覧」
ご覧と言われても考えるのは苦手。でも、考えないとマスターは何も教えてくれないだろうし、何より、何でもかんでも教えてもらって、安堵するのはあたしの主義に反するのだ。ちょっぴり不安だけど、あたしは歩きながら考えをまとめだす。
「――ココロとモノ? 精神と物質……。水と炎。――豊穣と干魃?」
あたしは不意に気がついた。アクアリュージョンとフゥリュージョン。それぞれの世界がそれぞれの名前と秘宝を持つ理由。マスターのヒントから青天の霹靂のような閃きを呼んだ。呼ばれる名前は精神世界。
秘宝の名前は物質世界。そう思うと悔しいけれど、やけに納得出来てしまうのだった。あたしたちの世界フゥリュージョン。モノは豊かだけど、精神の荒廃は言われて久しい。ユメたちのアクアリュージョン。モノこそホントにないけれど、みんな優しくて暖かかった。
「心を示せってこと?」それ以上、あたしには思いつかなかった。
けど、おかしいとあたしは思った。たった、それだけのためにマスターを呼んで、こんな話をするためだけに? もっと他に何かあるとあたしは勘ぐった。
「フウの人も捨てたもんじゃないと言うことを教えてあげたらいいの?」
「その可能性もある」煮え切らない。約束は出来ないらしかった。
「でも、ここはあたしのフゥリュージョンと変わらない。空気も何もかもが同じで違和感も感じなくて。でも、ここはあたしがいるべきとこじゃないみたいに居心地が良くなくて……。とってもよく似てるんだけど、なんか違うんだよねぇ」
その微かな違和感の原因が何なのかあたしには判らなかった。と唐突にユメが言った。
「――始まる……?」視線を落ち着かなく、空や、卒塔婆や、廃墟に向けて。少し驚いたような声色で、“今、来る”とは考えてなかったかのような雰囲気。「まさき、必ず行く、持ちこたえろ」
「な、意味が判らない!」
あたしの声は突風にかき消された。不意に砂塵が舞って、あたしの視界を閉ざした。
「まだ、マスターから答えをもらってないのに。何? 何が始まる……?」
フォーレスタを包む空気が変わった。
戦ぐ風が何か得体の知れないもの呼び込む。そんな予感。最悪の展開。ヒーローの前に立ちはだかる巨大な敵。すぐに現れそうな呼んだ空気。
「ずっと捜していたんだよ……」
聞き覚えのある声にあたしはハッと息を呑んだ。抑揚のない平坦な口調で、さらに続けた。
「――一週間もどこにいたんだい?」感情がないみたいだった。
あたしは張り裂けそうなくらいドキドキする胸を右手で押さえて、振り向いた。
「ゆ……?」
そこであたしはりんちゃんの言ったことを思い知った。“卑劣”そんなのないよ! とあたしは言いたかったけれど、始まってしまったからには終わるまで次は来ないに違いなかった。
けど、堪えられないかもしれない。あたしは挫けるかもしれない。
ユメやマスターの期待に応えられないかもしれない。あたしはみんなが思っているほど強くない。
こんな現実を突きつけられたら、あたしは……。
ゆうや、どうしてキミがここにいるの? あたしは地面に崩れ落ちた。