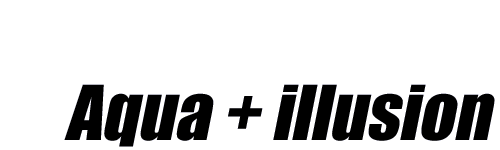
07. フゥの試練、アクアの望み(2)
何故かあいつは死んだ魚の瞳をして、血塗れた剣を下げていた。あたしはハッとして左手を唇に押し当てていた。マスターの言葉“助けてやれなかったんだよ”……。
「マスター。そう言うことなの?」
あたしは唾を飲んだ。と言うことは、あたしかゆうやのどっちかが。それ以上は判りきっているだけに考えたくなかった。
「何だ、まさきじゃないか。随分、捜したよ」
ゆうやと離ればなれになった最後のあの日、通学路で、美術館で見た笑顔と同じだった。優しくて、けど、切ないゆうやの微笑み。あたしの大好きなゆうやの笑顔。
「どうしたんだい。そんなに泣きそうな顔をして」
けど、口調には感情の欠けらも感じられなかった。やがて、ゆうやの笑顔も蝋人形の冷えて固まった不気味なモノに見えてきた。
「ユメっ!」返事がない。あたしは急いで辺りを見回した。けど、いない。ユメがいない。と言うか、違うんだ。卒塔婆が、壊れた街並みが見えない。あたしがみんなと違う場所に来たんだ。いつの間にか。そうしたら、ユメの発言が一気に理解出来た。
こんなゆうやを前にしてあたしは一人なの? 気がつけば、いないのはユメだけじゃなかった。マスターもクロウも、マイもいなかった。あたしは隔絶されて一人きり。
「ユメって誰だい?」そんな虚ろな眼差しであたしを見ないで。
唯一、あたしの手元にあったみんなの証はセイのレイピアだけだった。これで戦うしかないの。戦って勝てば、道が開けるの? それとも、閉ざされてしまうの。
あたしは腰に吊ったレイピアに手を伸ばした。マスターはきっと武器を手に取った。けど、りんちゃんはどういう選択をしたんだろう。“まさきはまさきのままで居られるのかな”寝転んで空を見上げたりんちゃんの言ったことを思い出していた。
「あたしがあたしのままで居られるのか――?」
運動があまり得意でなかったゆうやが血塗れの剣を下げているのを見たらりんちゃんの言っていた意味も判らないではない。けど、そんな事態になるのかという気もする。蝋人形の笑顔をたたえるゆうやを前にあたしは楽観的すぎたのかもしれない。
「――結局、最後まで来ちまったね」かさっと何かの音がして、がさつな声が届く。
不意をつかれた。ユメも誰もいなくなってここにはゆうやしか居ないと思いこんでいた。
「リンネ!」あたしは焦って怒鳴った。
「そんなに驚いた顔するなよ。心外だぜ?」
「どうやってここに? ゆ、ゆうやに何をしたんだ?」
「答えてもいいが、いっぺんに聞くな」
少なくとも味方じゃないやつに怒られるなんて納得出来ない。けど、仕方がない。
「う……。判った」
「お〜いい心がけだ」むかむかする。「ここは誰だってすぐに来れる。フゥのやつの悪戯さ。フォーレスタからそんなに離れてないぜ? クロウもマイも居たからすぐ見付けて来るんじゃないか?」
ユメやマスターのこともリンネは知っているようだった。
「そして、……ゆうやに何かをしたのはアクアリュージョンで俺じゃねぇよ」
「どっちだって、おんなじだ!」あたしはがなり立てた。
「そう怒るなよ。せっかくのお楽しみが台無しになるぜ?」
お楽しみの訳がない。こんな蝋人形みたいなゆうやと一体何を楽しめと言うの。
「不満か?」リンネは意地悪そうに口を元歪めてニヤリとした。
「違う」あたしはほとんど直線的に否定した。
「違わないよ」
「違うっ!」あたしは髪が絡むほどに激しく首を横に振った。「不満とかそう言うんじゃない、どうして、こんなコトをするんだっ!」
「それは試したいからだろう?」まるで何事もなかったかのような普通の答えだった。
そして、今さら聞くまでもないコトを聞いたのかもしれない。アクアとフゥは確かめたいんだ。お互いが再び出会うために。互いの世界を試すんだ。それぞれの宝石はそれぞれの世界と強く結びついてる。だから――。
「そして、ここをまで来たファイナリストと呼ばれる者たちは全五百十二人中、たったの七人、確率はおおよそ百分の一。他のやつらはどういう事か判るだろ?」
判るけど、判りたくなかった。マスターの言った言葉の意味もきちんとつながる。あの卒塔婆の群れはここまで来られなかった無念の証。きっと、そうだ。けど、リンネの言ったことは違った。
「あとはここで死んだか、逃げ出した」
「逃げ出した?」
「そう、臆病風に吹かれた情けない連中のことさ。りんいちろうも、マスターも、そしてユメも」
「ユメが?」あたしは度肝を抜かれた。何だか、口が金魚みたいにぱくぱく。
「あいつは例外だな。唯一、フゥとアクアの認めた」
どこか遠い過去の一点を見ているかのようだった。リンネがセイだとユメは言った。唯一の例外、ユメは囚われの姫(?)を追って挑戦したことがあるというの。あたしは動揺していたのに違いなかった。そして、あたしはリンネの瞳を見詰めたまま動けなかった。問えない。リンネとユメの関係。そうやって、まるで何でもないことのように言うけど、二人の過去に何があったの。
心を決めて、問おうと思ったけど、あたしの口から飛び出したのは別の言葉だった。
「何で、ゆうやが居るの?」
「――誰かに聞いただろ? 二人呼ばれるんだって。一人は旅し、一人はこの通りさ」
あたしを指さして、何故だか、リンネは嫌がるでも訝るでもなく答えてくれた。
「あたしに何をさせたいの?」折角だから、聞けるだけ聞いてやる。
「さあね。けど、ゆうやだっけ? をどうにかしないとフゥは姿を見せてくれない」
「方法は教えてくれないの?」
「何で?」キョトンとした表情を一瞬見せて、リンネはあたしをあざ笑った。それから悪意のこもったクスリとした微笑み。「ま、手っ取り早くはゆうやを殺せばいいさ。けど、ま、いいや」リンネは面倒くさそうに頭をボシャボシャと掻いた。
「せいぜい、殺されないようにがんばりな」
リンネはわざわざこんなところまで冷やかしに来たんだろうか。
絶対帰ると決めた心が揺らいだ。ゆうやを殺さないと先へ行けないなんて、そんなのいやだ。あたしは知ってる。がっこで何とかやってこれたのはゆうやがいたからなんだって。ゆうやの顔が見たくて、ゆうやとお喋りがしたくて、あたしはがっこに行っていた。ゆうやがいなくなったら、あたしはあそこで独りぽっち。そんなの……嫌だ。
「あたしが――ゆうやに殺されたらいいの?」
「その選択も悪くない。が」真顔の鋭い視線があたしを突き刺した。「そんな答えを選ぶなら最初から帰ろうと思わなければ良かったんだ」
「……そうだね。けど、何もしないのはサイテーだと思う」あたしはリンネを睨み返した。
「ふん……『何もしないのはサイテー』か……」リンネは急に物思いに耽ったかのような遠い眼差しをして呟いた。「しかし、何もしないことが最良の選択の時もある」
宙を舞った視線が戻ってきて、再びあたしを見定めた。もの凄い威圧感。短い言葉の中にも説得力があって、その中に力を持たせられるくらいの経験をリンネはしてきたんだとあたしは思った。
「それでも、あたしたちで終わり、あたしが突破口を見つける」
「だったら。ゆうやは俺が殺す。――それで終わりだ」
「ダメ。そんな終わり方は絶対にさせない。そんなの終わりじゃない」
けど、ここに来たみんなと同じようにしたら、あたしはフゥを手に入れられない。ゆうやを殺したとしたら、フゥはあたしを認めてくれないのに違いなかった。一つの世界が二つになった訳。それさえ判れば。あたしはリンネを睨んだ。
「ここまで来たんだ。好きにしたらいいさ。俺はてめぇが破れる方にかける」ニヤリとした。「恋人に殺される気持ちを聞いてやるぜ?」
「こ? 恋人? ちが、ゆうやはただの友人で……」
って、そんな釈明なんかする必要ないんだ。
「慌てるところが怪しいな――。ま、ギャラリーがいたら、気が散るな」
笑いながらリンネは言った。キミの気持ちはどこにあるの? ベリルを率いるキミは挑戦者の邪魔をしたんじゃなかったの? ホントにそう考えているなら、物騒だけど、あたしたちを殺してしまえばすむ話。リンネなら、隙だらけのあたしたちを消すくらい造作もないと思うのに。
「……リンネ。いや、セイ。もう、こんなことはやめにしよう」
背後からのユメの声にあたしの心臓はそれこそ口から飛び出してしまいそうだった。
「え、ちょっ、え? だって、どこから来たの?」
「クロウの背中に乗ってだ。空から見たらここなんかすぐに判る」鋭い視線、冷めた口調。「まさきはそっちの相手をしろ。――俺は……セイ……。――三年前の決着を付けよう」
そう言いつつ、ユメはあたしから視線を逸らしてリンネを向いた。
「今さら、何の決着を付けるつもりなんだい、……お兄さま?」リンネは両手を広げてバカじゃないのと言いたげにあざ笑う。「俺を見捨てたのはあんただろ? セイを殺したのはあんただろ? セイはもういない。いるのは俺、リンネだけだ」
リンネは豹変してユメを問い詰める。でも、ユメは反論するでもなく、リンネの瞳を見詰め返したまま動じなかった。
「ああ、殺したつもりだったが……、お前の中でまだ生きてるみたいだからな」
「キレイゴトを言うんじゃねぇよ。フゥの試練に破れ逃げたあんたにそんなこと言う資格はねぇ」
ユメはしばらく答えなかった。
「殺したと思ってたからな。――それが正しいと」
リンネとユメの会話の意味がはかりきれない。けど、そんなやり取りを呑気に考えてる余裕はなくなった。ゆうやが剣を振り上げた。薄気味の悪い死んだ微笑を浮かべて、さっきまで、さっきあった時、美術館での優しい笑顔だと思ってたのはホントは違ったんだ。もう、あたしのゆうやは居ない? 感情を殺されたフゥの傀儡。ああ……父さんが望む“あたし”はこんな感じなんだ。やれと言われたことを疑うことなく実行するだけ。想像の欠けらもないお人形さん。
帰っても、あたしの居場所はなくなっちゃたんだ。
ガキンっ!
「何をぼーっとしてるんだっ!」
激しい金属音で、思考の淵から我に返ったら、ユメが剣を止めていた。リンネのじゃない。ゆうやの剣。ゆうやが本気であたしを殺そうとしてる。あんなシャイで虫も殺せないようなゆうやが。そう思ったら、急に震えが走った。あたしは両手で自分自身を抱いてどうしようもなく潤んだ瞳を従えて、ユメの肩越しにゆうやを見ていた。
「……助けて……ユメ……」涙が溢れて視界の揺らぐ目で、あたしはユメの背中を見てた。
「……『天は自ら助くる者を助く』そう言ったのは、お前だぞ、まさき」
クールな声色にあたしはビクッと身を震わせた。ユメは助けてくれないんだね。そんなことは頭で判ってたけど、あたしは動けなかった。フゥの望みはゆうやを殺す事じゃないと思う。でも、このままじゃあたしが――。パニック寸前でどうしたらいいか頭が回らないよ。考えなくちゃならないのに、思考出来ない。だって、ゆうやが虚ろな目であたしを見てる。
ゆうやにはまるでユメが見えていないみたいだった。
ユメはゆうやを押さえたまま瞳だけを左に向けた。視線の先にリンネがいた。
「てめぇの相手は俺だろ? ユメっ」
「あっ、ユメ!」恥ずかしいくらいの涙声。
けど、ユメはゆうやの剣を容易くなぎ払った。バランスを崩したゆうやはつんのめって前に倒れ、ユメはなぎ払った勢いのまま剣をリンネのそれに交錯させた。ギギギ。耳障りな金属音があたしの耳を貫いていく。
「少し鈍ったんじゃないのか、セイ」まだ余裕のある不敵な笑みを浮かべていた。
「てめぇが鈍ったんだろ? ……以前のユメなら、ここで止まらなかったさ」
「かもしれないな」ほくそ笑む。「まさき、剣を取れ! お前に、今、出来ることをするんだ」
「……レイピアなんか使えない。……あたしに出来ることなんか、何もないよぉっ!」
「そうか?」優しい声だった。「お前にしか出来ないことがあるから、アクアはお前を選んだ。そして、俺は……今、俺しかできないことをする」
「はん? 百二十八番目に破れたてめぇにそんなことが言えるのか?」
「ああ、今なら言えるな」ニンと笑ってた。「お前にまさきの邪魔をさせないことだ」
そして、ユメとリンネの激しい攻防が始まった。けど、あたしは良く覚えていない。ただ、はっきり判ったのはユメが本気だってこと。ユメは剣の峰じゃなくて、刃をリンネに向けていた。
「フン――、ま、いいさ。どの道、結果は変わらない」
それから、あたしはゆうやしか見れなかった。ユメは邪魔にならないようにと思ったのか、リンネをそれとなく引き寄せて、あたしたちから距離を開ける。と言うことは、ユメは来ないってこと。ゆうやが剣を振るったら、あたしは自分で逃げて、防がなくちゃならないんだ。
「ゆう……や?」虚ろなゆうやを見ると、どうにもならない思いがこみ上げてくる。
ゆうやは力無いように剣をズリズリと地面を引きずってあたしに近づいてくる。
「どうしたの、まさき」のっぺりとした口調はあたしに恐怖を植えて付けていく。「泣き出しそうな目をしているよ。……でも、安心していいよ――」
声色が変わったような気がした。『安心していいよ』と言う言葉とは裏腹にロクでもないことを感じる。だって、ゆうやは剣を持ち上げてる。あたしは後ずさる。レイピアを取るしかないの? ゆうやを刺し殺してしまうしかあたしが生き残る方法はないの?
あたしは腰に下げたセイのレイピアを手に取った。ユメに教えてもらったように構えて、あたしはゆうやの虚ろな瞳をじいっと睨み付けた。あたしのゆうやだったら、『恐い顔をするなよ』とか言って、きっと剣を降ろしてくれる。けど、ゆうやは口元を歪めた……。
「ひぃっ!」
剣を振り下ろしてきた。運動音痴で、走るのだって苦手、剣道だってやったことないはずなのに。あたしは地面に突き刺さる剣を横目で見ながら、飛び退いた勢いで地面に転がった。
「……どうして逃げたりするの? 折角、持ってるんだろ? それ……?」
心臓が止まるかと思った。まさか、そうなることを望んでいるの。そうしたら、あたしはフゥのところに行かせてもらえるの。ゆうやをコ・ロ・スことが正しい選択?
でも、待って。混乱の中、あたしは出来るだけ心を落ち着かせようとした。早まったことをしたら、卒塔婆の群れの中にあたしもゆうやも並ぶことになってしまう。あたしは左手で胸を押さえて、大きく深呼吸をした。それぐらいの間がある。あっちではユメとリンネが緊張感のある戦いを繰り広げているみたいだけど、あたしとゆうやの間には少なくともそれはない。
まるで、そう、まるで殺して欲しいみたい……。
「でも、きっと、違う――」あたしは呟いていた。
「何が違うんだい?」呟きを聞き咎めたゆうやは問い返してきた。
けど、あたしは答えない。妙に間延びした時間が過ぎて……。不意にさっきのユメの言葉が脳裏に浮かんだ。『正しいと思ってたんだけどな』そして、マスターの大切な人のお墓。正しい選択は、ううん、間違っててもいい。あたしはゆうやをなくしたくない。ゆうやのいないがっこなんて、何も知らないあたしのちっぽけな世界だけど、ゆうやがいないあそこにあたしがいる意味なんかない。
ゆうやがいたから、あたしはあの場所で存在する意味を持てた。
「ゆうや、一緒に帰ろう。また、待っててよ、塀の陰で……。がっこに行こうよ……」
「そう?」素っ気ない返事。もう届かないのかな。
もう、ずっと堪えていた感情がほとばしってしまいそうだった。あたしはレイピアを落とした。こんなモノ要らない。ユメが見たらきっと真っ赤になって怒るんだ。『殺される前に殺せ』そう言ってたもんね。でも、あたしはゆうやを信じたい。
「まさきが来ないなら、俺から……」
ゆうやが再び剣をかざした。どうして、こんなコトになっちゃたんだろう。あの美術館で見たキミの笑顔が最後だなんて、絶対に嫌だよ。泣き笑い。あたしは泣きながら笑ってた。今まで、色んなものを諦めて、追い掛けることなく捨ててきたような気がした。
けど、ゆうやは諦めない! あたしは隙のあるうちにゆうやの胸に飛び込み、抱きついた。もう、そうするしかない。ゆうやと一緒に帰る。帰れなくても、せめてこのアクアリュージョンの片隅で暮らしていきたい。ゆうやがいたら、どこにだって行ける。
「……放せよ……」冷たい声。
「放さない、絶対っ! ゆうや、気がついて。あたしはキミの……」
涙が止まらない。お願い、ゆうや。目を覚まして。剣を下ろして。それとも、自分もろともあたしを突き刺してしまうつもりなの。ゆうやの冷たい視線が痛い。見下して蔑んだようにあたしを見ないで。そして、気がつけばあたしは叫んでいた。
「フゥ! あたしのゆうやを返せ! あたしはあんたの思い通りになんかならない!」
泣き声を張り上げた。あたしは空を見上げる。フゥがどこにいるのか判らないから、あたしは無意気のうちに視界の開ける上を向いたのかもしれない。
と、突風があたしとゆうやの間を吹き荒れた。
「あっ!」
巻き上げられた砂に視界を遮られた間に、ぎゅうっと抱きついていた感触がふわっとなくなってゆうやの姿が消えていた。気がつけば元の場所。卒塔婆があって廃墟が見える。そして、あたしの足元に転がっていた。ファイアレッドの球。手のひら大で表面はつるつると輝いていた。
あたしはしゃがんでそれを拾う。真ん中あたりには一文字の亀裂が入っていた。心臓がドクンと大きく脈を打つのを感じた。赤い石榴石と水色の緑柱石。フゥリュージョンとアクアリュージョン。それぞれの思い、愛すべき存在。
『柊まさき……』
石が言葉を解する理不尽さを超越し、冷たい宝石が暖かい声色を放つ。とっても懐が深くて、優しい声。ずっと昔、遠い記憶の彼方から聞こえる父さんの声みたい。
「……はい」あたしは答えた。
すると、亀裂が開いて大きな眼になった。赤い瞳。まるで寝不足の朝みたいな目。けど、白目は充血してなくて……。やっぱり、無性に突っついてみたい。みずみずしく輝いた瞳だから、硬くはないよね。アクアの時は出来なかったけど、あたしの手の中にあるフゥなら。
『――』目がバッチリあった。『何か良からぬ事を考えているだろう?』
「うっ……!」図星だ。「ごめんなさい」うなだれてしまう。
『正直だな……。まさき――、お前の心を見定めた。お前ならば、信じ切れる。お前ならば私とアクアの思いに答えられると信じることが出来る』
「ゆ、ゆうやは――」
そんな信用出来る出来ないの話よりも先に、目の前で消えてしまったゆうやが心配だった。
『まさきが帰れば、そこで会える』フゥは真っ赤な瞳を可愛らしくぱちくりさせて答えてくれた。
「ありがとう」あたしは素直に言う。そしたら、ユメがいつも調子で茶々を入れる。
リンネとの決着はついたようだった。散々手こずったかのように、髪はぐちゃぐちゃ、かすり傷みたいのが体中のあちこちに見えた。セイは凄腕のレイピアの使い手だって言ってたものね。
「素直に礼を言っちゃ、らしくないよな? 実際」
「な? 何だってぇ?」あたしは思わず手を振り上げた。そしたら「あっ!」
「――お〜飛んでいったな、可哀想に。――これも初めての経験だな。フゥのやつ」
他人事だと思って何を呑気に言ってるんだ、ユメは。フゥのご機嫌を損ねたら、帰れなくなっちゃうかもしれない。と言うか、十分すぎるくらい損ねてるよね。
「って、ユメ。ユメっ! 地面に落っこちたら割れちゃうんじゃない?」
「割れないと思うけどなぁ」面倒くさそうにユメは言って、あたしがフゥを飛ばした方に走っていった。「迷惑な話だよな、フゥ!」
そして、ユメは地面に直撃しそうなところをスライディングキャッチ。流石、ユメ。
「大丈夫か?」大丈夫だと思っていて聞いているみたいに、心配していないようだった。
『なかなか、ス、スリリングだった……』そうは言ってるけど、目が泳いでる。
「ご、ごめんなさい」
もう、平謝り。投げるつもりはなかったけど、もし、これで粉々になっていたらと思うと、ぞっとした。流石におかしな生きてる宝石(?)だとは言っても破片から再生出来るとは思えない。
『では……、あとはお前に任せたぞ。私は少し眠らせてもらおう。――疲れた、お前が来るのを待つのに。長すぎたよ。五年というと言う制約、数百年という時の潮流――』
見開かれた瞳が眠そうに閉じられていく。けど、ちょっと待ってあたしはまだ聞いていない。
「フゥ、眠る前に教えてっ! 帰り道はどこにあるの?」
ユメの手のひらの中で眠りに落ちそうな虚ろなフゥの瞳がうっそりと動いてあたしを見た。
『お前はその道をもう見付けている……。己を信じ、私とアクアを信じろ――』
「ど、どういう意味?」もっと、聞き出せないかとあたしは食い下がる。
『答えはお前の中にある。――自分で探せ。お前は必ず帰る。私とアクアは再び出会い、二つに分かれ、焦がれた世界は一つになる。私は信じる。お前は疑うな』
言いたいことを言い終えたら、フゥは瞳を閉じて寝入ってしまった。人の気も知らないで。
「ホラ、まさき。フゥはお前のもんだ」
「うん……」ユメはフゥを渡してくれた。「あたしが初めてなんだね……」
「ああ、最初で最後の真のファイナリストだ……」
ユメの背中は淋しさでいっぱいに見えた。シャンルーの洞窟で泣きに行った時以来かな。ううん、その時よりもずっと淋しそうにあたしには思えた。
「……さて、わたしの役目ももうおしまいかな」マスターが言った。「やっと帰れる」
あたしにはマスターの発言の意味が理解出来なかった。役目って何なの。
「みんな元の鞘に収まるってことだよ」あたしの聞きたがりの顔を見てマスターが言う。「マイと一緒の墓守もおしまい。わたしは初めからそうだったものにもどるんだよ……」
マスターの象徴的な一言。初めからそうだったものって何だろう。シェンリースーのマスターに戻るってこと? あたしはマスターは今も昔もシェンリースーのマスターだけと思ってたけど、違っていたのかな。そう考えているうちに、ユメはあたしの横を通り過ぎてリンネの方に歩いていった。
「……セイ、――帰るぞ。……三年ぶりだ。スイも喜ぶ。それとも驚くかな……?」
ユメは倒れたセイをお姫様だっこした。ぐったりしてる。けど、最後は峰打ちだったんだ。あたしは秘かににほっとした。ユメはセイを抱っこしたままマイに歩み寄る。その昔、兄妹だった二人。今は敵……じゃなくて、考え方の違いで袂を分かった不遇の兄妹。少なくとも、ユメとセイが敵同士であって欲しくなかった。
「マイ……。ボーダーランドに行ってジュンのINNで降ろしてくれ」
「判ったわ、乗せて」マイはスッと身をかがめた。「マスターも帰るんでしょ?」
「帰るよ。グリーンズで降ろしてくれると助かるね」
「もちろん、いいわよ。送り迎えはきっちりとさせてもらいますわ、マスター」
マイはマスターとセイを乗せて空の彼方に消えていった。ユメはどんな気持ちで見送ってるんだろう。ジュンやレンには死んだって、ベリルの子どもに殺されたんだって。そう言ったって言ってのに。死んだはずの娘が突然帰ってきたら、戸惑うんじゃ。
「ユメ……?」
「何も言うな……」ただ一言、ユメは言った。
でも、きっと、大丈夫なんだよね。親子なんだから。他人のあたしが心を砕いて心配しなくても元の鞘にきちんと収まるんだよね。あたしはしばらくの間、マイの姿が見えるまで空を見上げていたユメの背中を眺めていた。
「一緒に行けば良かったのに。あたしは――大丈夫だから」
空の彼方に消えていったマイからユメの視線が戻ってきた。儚くて優しい笑顔。
「最後までつきあうって言っただろ? 俺もクロウも。お前が帰るその瞬間を見届けてやる。……さてと、俺たちも戻るぞ。長居することもないだろう?」
ユメの言うとおりだとあたしは思った。まだ終わってない。あたしは帰り道を探さなくちゃならないんだ。けど、フゥはもう見付けていると言っていた。
「ねぇ、ユメ。……ユメはどこだと思ってたの?」
「だから、上着の裾は引っ張るなと言ってるだろ、いいかげん聞けよ!」
「ううん」あたしは目を閉じて大きく首を横に振った。そして、ニコっ。「絶対、やめない!」
「何でだよ? お前が引っ張るから、そこだけ伸びただろ?」機嫌悪そう。けど、気にしない。
「それがあたしのステータスなんだ。諦めて引っ張られてなさいっ!」
「何だそりゃ?」納得いかなさそうに眉をひそめた。
「はははっ。もうどうでもいいよ。クロウに乗って、ホラ、グリーンズに帰ろう?」
あたしは戸惑うユメの背中を両手で押して、あっちで待ってるクロウのところまで行った。そしたら、クロウはご多分に漏れず、興味津々とばかりにでっかい瞳をくるりと閃かせていた。
「また、一段とお近づきになったんだな? ユメ?」冷やかし?
「うっさいよ、お前。さっさと乗っける! 帰るぞ」
ユメはぶつぶつ言いながら、尻尾から背中に上った。あたしもユメにくっついてクロウに登る。
「……帰るか? ……帰ったら淋しくなるな。折角、仲良く……」
クロウは飛んだ。加速する風切り音にかき消されたクロウの言葉の続きは何だったのかな。その答えを聞く暇もなく、クロウは急上昇し、フォーレスタの廃墟と卒塔婆の群れはあっという間に地面のシミに取って代わった。
「どっちにしても。もうすぐ終わりだな……」クロウの呟きがあたしの耳にひっそりと届いた。
もうすぐ終わりかもしれないけど、簡単には終わらなさそうだよ。けど、言葉には出さなかった。帰り道は自分で探せ。あまりにショックであたしはしばらく口が利けなくなった。でも、言われてみれば、そんなものがあるなんて誰も言っていなかったもんね。
「行くところが判らない……」
あたしとユメは顔を付き合わせた。
フゥリュージョンを手に入れたらそれでおしまいだと思ってた。けど、そこから先がまだあった。前人未踏。ここから先はホントにあたししか踏み入れたことがないんだって。だから、ユメもその先は知らない。今までずっとユメがそれとなくサポートしてくれてたけど、今度はあたしが本気で考える番なんだね。と言っても、あたしは考えるの苦手なんだけど。
ユメはそんなあたしを見透かしてるのかニヤニヤしながらあたしの顔を見ていた。
「……だから言ってるだろ。まさきの百面相は見ていて飽きない、面白いって」
「うあぁ、しまったぁ」どうも、あたしは考えてることが顔に出ちゃうタイプらしかった。
「お〜お、見せつけちゃってくれちゃってさぁあ? オレのこの満たされない気持ちはどうしたらいいんだろね? マイちゃんは先に帰されちゃうし。オレの背中の上はこんなんだし……」
「ねぇ、クロウ。何か、あたしに文句ある訳?」凄く恐い顔をしてクロウの目を除いた。
「い〜え、別に」無表情な平坦な声。恐くはなかったらしい。
「じゃ、黙ってなさい。あたし、今、とっても重要な局面にいるの!」
「へ〜いぃ……」全然、重要だとは思っていないような気の抜けた返事。腹の立つ、クロウめ。
「でさ、どうしようか、ユメ?」
「どうしようって言われてもな。考えるのはまさきの仕事だろ? 俺は補佐」
「! そしたらたまに頭使えよな」思わず憤慨。
「もう少し、じっくりと考えてみろよ」
ユメは静かに言った。けど、ユメはここまで来たんでしょ? だったら、少しくらいは目星を付けていたんじゃないだろうかとあたしは思った。
「ねぇ、ユメ。意地悪しないでさ?」
「はぁっ?」訝られた。「何を言ってるか? 俺は意地悪なんかしてないぞ?」
でも、あたしのアクアリュージョンでの物語はもうすぐ終わりを迎えそうだった。あたしはあたしたちの物語のステキなフィナーレのために何をしたらいいんだろう。いつかマスターの言っていた言葉をあたしは思い出す。“この物語、どう終わらせたい?”
もちろん、ハッピーエンドで終わらせるんだ。