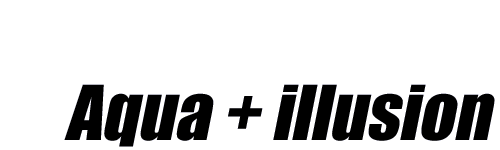
09. 緑柱石と石榴の思い(2)
シャンルーの架け橋の見えるシャンルーの洞窟の上で最後の夜明かし。シャンルーもその重たい巨体を動かして外に出てきてくれた。初めて見るシャンルーの全身。やっぱり、クロウよりも、マイよりもずっと大きいんだね。そして、肌。つやつやじゃなくくてガサガサしてる。そんな、長い年月をキミはここで過ごしてきたんだね。
「まさきが終わりを見せてくれるとは考えてなかったな……」
その低くて渋い声があたしのココロを揺さぶる。瞳も綺麗。洞窟で見た淀んだ煌めきは何だったんだろう。それよりも、もし、世界が一つになったら、あたしはシャンルーとまた会えるのかな。
「……終わり、終わりって言わないでよ」
「事実は事実。それは受け止めるべきだ」瞳だけをあたしに向ける。
それはそうだけど、あたしを少しは気遣ってよ。でも、わがままなのかな。
「判っているけど、シャンルーとは会えるの? クロウに会えるの? だって」
その言葉を言おうとした時、シャンルーに遮られた。
「もちろん、承知の上だ」遠くを見ていた瞳。それがくるっと回ってあたしを見詰めた。「……まさきのところには飛竜はいないんだろ……?」再び、瞳は谷を眺めた。
あたしは黙ってシャンルーに抱きついた。そして、お腹に頬をこすり付けた。
「――それも一つだけど、違う」
あたしの杞憂はそんなところにはない。会えないんだったら、例えようもなく辛いだろうけど、きっといつか会えると信じて、乗り越えられると思う。でも、
「キミは……この世界が一つになってしまったら、ひっ」シャックリがでる。「あ……、キミの居場所はなくなっちゃう。もう、ずっとずっと、会えない。ううん」あたしは首を横に振った。「シャンルーとクロウにあたしと同じ思いをさせたくない……」
「――オレたちも帰れるさ」クロウが言う。「まさきが成功したら、オレたちの世界とここはもっと近くなる。ユメが言ってただろ? そしたら、帰れる。その場所がここだって判ったんだ。紛れ込んだ時のようにスッと帰れるよ……」
けど、それはまるであたしを慰めるためだけに言ってるみたいだった。二人は帰れるなんて欠けらも思ってない。きっと、シャンルーもクロウも、マイだって離れてしまう。あたしを心配させないためだけに、キミたちは姿を消す……。
「でも、やっぱり、あたしはキミたちにもう一度会いたいよ。一つになった二つの……」あたしは涙をぬぐった。近頃、泣いてばかりだな。「一つになった四つの世界で……」
当分、叶いそうにもない夢のようだよ。今生の別れにならない予感はある。でも、すぐに会いたい。一緒にいられない。会いたくてもキミたちはあたしの手の届かないところに。あたしのシャンルー、あたしの――クロウって言ったら、マイに怒られちゃうね。あたしのユメっ!
「これでさよならだね、ユメ」
と言うと、ユメはゆっくりと首を横に振っていた。
「忘れたのかい、まさき。お前が帰るってこととは二つの世界は一つになるってことだ。さよならじゃないよ、捜せばまた会える」
「捜せばまた会える?」涙がボロボロとこぼれ落ちた。
「な、何で、そこで泣くんだよ。また、会えるって言ってるだろ? らしくないぞ?」
そんなこと言ったって、泣けてくるんだもの。別れは嫌だ。湿っぽい別れはもっと嫌だ。ドライにクールに何でもないように。笑顔で手を振りながら別れてやる。そんな思いを秘やかに抱いていたよ。けど、この思いだけはどうにもならなかった。
星の降るようなステキなところで、みんなとたき火を囲んだこの時が永遠に続けばいいと思ったりもした。けど、フゥはあたしを信じてくれた。だから、あたしは立ち止まったらダメなんだよね。あたしも、フゥを信じて、キミをアクアの元に送り届けなくちゃならない。そして、ゆうやが待ってる。だから、あたしは帰るんだよ。
「いい加減に泣きやめよ。な、泣き虫はお前に似合わない」何をしどろもどろになてるんだ。
「クロウだって、そんな言葉は似合わないよ。キミはもっと、大雑把でもっと笑顔で……。照れくさそうにしてるなんて、変っ!」
「変だぁあ? 折角、気を遣ってやれば、そう言うかっ」
「うん、だって、フツーでいいの。お別れじゃないからフツーで……」
そう言ったあたしが一番普通を望んでいなかったのかもしれない。構って欲しい。空が白むまで……もっと喋ろうよ。朝にはいつものあたしに戻るから。ずっとずっと、大断絶の傍らで、澄み切った夜空の下で、忘れられない思い出を作ろう――。
「お〜い、まさき? 眠いのか? うつらうつらしてる」
「ううん。まだ」あたしは眠い目をこすった。「まだ、がんばれるから……」
「おいおい、夜更かしをがんばってどうするんだよ」
ユメの声がドンドン遠くなっていくよ。あたしは朝まで起きてる。だって、あと数時間しかないんだよ。朝になったらすぐ出発だから、眠る時間だって惜しいんだ。
「バカだな」
ユメが呟いたのが頭の中でこだました。ひどいな、ユメ。あたしはバカじゃない。
「毛布を掛けてやるから、お休み、まさき」ユメへ目を閉じそうなあたしに優しく毛布を掛けてくれた。「この場所でちゃんと待ってるからな……セイと一緒に。だから、ゆうやも連れて来いよ」
「うん……絶対に来るよ。だから、ユメ――」
ここから、何だか良く覚えていなくて気がついたら、最後の朝が来ていた。みんなは眠っているみたい。あたしは二度寝をしないで、みんなが起き出す前に起き、みんなの寝顔を見て回った。こんなコトは初めて。いつもは、みんなの方が先に起きてて、あたしばかりが幼気な寝顔を見られていた。不公平だ。早く起きてやる。と意気込んでも結局寝過ごしてたから、自業自得なんだけどね。
でも、今日は違った。いつもようなどよ〜んとした朝じゃなくて、清々しい朝。スズメが鳴いてる。陽射しが気持ちいい。ああ、ジュンのINNで、早起きした日以来だ。
「う〜ん……」
ユメは毛布をかぶり、クロウのお腹を枕にしてよく寝てる。寝相、いいんだね。もっと、凄まじい寝相をさらしてくれてると思ったのに。いびきもかかないでス〜ス〜って可愛い寝息。クロウは思いの外、綺麗に丸くなってる。身体が柔らかいんだね。そして、ユメが寄りかかってるのが判ってるのか、あんまり、動かないんだね。
「……あれ? シャンルーは……?」
あたしはキョトキョトしながらシャンルーの姿を捜した。昨日の夜までそこにいたと思ったのに。けど、すぐに見つかった。大断絶の縁に立って、谷底とノーシーランドを眺めていた。あたしはそっと物音を立てないようにしながら、シャンルーに近づいた。
「まさきか……」シャンルーの瞳があたしを見てた。
「何だ、気付かれちゃった」あたしは何だか照れくさくなって頭の後ろで手を組んで、空を蹴る。
「判るさ」瞳がまた向こう岸に向いた。「まさきの空気は独特だからな……」
どういう意味なんだ、それは? でも、悪い意味で言ってるのではなさそうだった。
「……静かだね」
「いいや、ずっと風は吹き続いてる。――もう三十分か一時間で風がやむ。今日の凪はいつもより少し長そうだよ。――そよぐ風の精霊も味方に付けたのかな」シャンルーがクスリと微笑んだ。
「朝っぱらから、何をやってるんだ? 二人で」
ユメが眠そうな目をこすってあたしたちの方に歩いてきた。
「な〜んもしてないよ。ね? シャンルー?」
と言ったら、シャンルーは眉間にしわを寄せて目を白黒させたように困っていた。こういうシチュエーションは苦手なんだね。そんなちょっとだけ困ってるシャンルーなんて初めて見たから、印象もがらりと変わる。恐そうに見えて、ホントは可愛らしくて優しいんだね。
「ふふ〜ん。照れちゃって可愛いなぁ。シャンルーは!」
冗談めかして言ってみたら、シャンルーはもっと困ったような顔をしてた。ごめんなさい。
「年寄りをあまり虐めちゃ可哀想だぜ?」
「オレはお前に言われるほど、じじいじゃない! 黙ってろ」
「何だ? 親父? 朝からケンカとは元気がいいね?」
今度は大あくびをしながらクロウがドタドタと歩いてきた。これで全員そろったね。二頭の飛竜と二人の人間がずっと彼方を眺めてる。他には何にもない。朝早く、まだ、吹き抜ける風も冷たい時間。この何とも言えない涼やかな時を封じ込められたらいいのに。
あたしはみんなの横顔をまじまじと見詰めた。これで最後だ。今、きっちりの心に留めておかないと、残り少ない時の中にこんなチャンスがあるとは思えない。ホンのひとときかもしれない。けど、さよならなんだよ。涙が出そうになる。今生の別れじゃないんだから我慢しなきゃ。
「……まさき。また会えるよ。だから、別れの挨拶は言わない」
ユメの言葉を聞いて、我慢出来なくなった。涙が止めどなく溢れてもう止まらない。あたしは立っていられなくなって、地面にぺたんと座り込んだ。もう、泣かないって決めたのに。
「あたしもさよならなんて言わない」
でも、説得力が全然ないよ。みんなが笑ってる。けど、とっても暖かい。ユメはこのアクアの世界にあたしの居場所はないと言ったけど、あたしは見付けた。この世界でのあたしの場所はここなんだ。ユメとクロウとシャンルーの間。ホンの短い間だったけど、キミたちと一緒にいられて良かった。それだけが判っただけでもステキな旅だったんだよ。
「えへへぇ……」あたしは泣き笑い。
「どうした、急に変な顔をして……?」
「ホラ、だから言っただろう。まさきの百面相は面白いって」
「また、そんなことを言うの?」あたしは我慢しないぞ。今日こそ、思い知らせてやる。
「怒ったっ!」はしゃいでるようにユメが言った。
「怒ったじゃない! もうっ、どうしてユメってこうなの!」
「……朝っぱらから、痴話ゲンカとはたまらないものだな。クロウ?」
「親父、もう、オレは慣れたよ。……ようは諦めて何も聞いちゃいけないってこと。こう、黙って、できるだけ聞かないようにして、嵐が過ぎ去るのを待つのがコツさ」
「なぁんだって? クロウ。キミはあたしが嵐だって言いたいのかい?」目は三角だ。
「……そして、要らぬ発言は控えろと言うことだな?」
「な? シャンルーまで。こんな幼気な娘を捕まえて虐めないでよね」
と言ったら、シャンルーは大笑いした。目を細めて、大きな口を開けて笑ったら、空気がびりびりと振動した。飛竜はやっぱり、スケールが大きな。
「む……?」シャンルーの目つきが変わって、谷を見た。
「まさき、そろそろ、風が凪いでくる。いつまでもわめいてないで、準備しろよ」
さっきまでふざけてたのはユメじゃないの。それなのに急に真顔になって、ずるいよ。けど、ユメの言うこともその通りだからあたしは準備をする。スタートのタイミングを外したら、切れ目に行くまでに強風があたしを襲うかもしれない。そうなったら、どうにもならない。クロウもシャンルーもきっと助けに来てくれると思う。けど、フゥを裏切ったことになる。
「! そうだ、まさき。これをして行け、お守りの代わりだ」
ユメがあたしに渡してくれたのは白いはちまきだった。
「これは?」あたしは当然のごとく聞いた。
「はちまきだ」いや、そうでなくて。と瞳で訴えたら通じたみたい。「昔、俺が使ったやつだ。……こう見えても、俺、足は速かったんだ」何だかぶっきらぼうな口調。
「リレー走者かなんかやってたっていいたいのかな」あたしはニマッとユメを覗いた。
「ま、まあ、そんなようなもんだ」
目を合わせない。と言うことは、微妙に気恥ずかしいんだね。
「うん、使わせてもらうね」
あたしは白いはちまきをギュッと締めて、しゃがんだ。まずは靴の紐をきちんと締め直して、間違っても途中で脱げないようにしておかないと。作業通路は足場が悪いから万一のことを考えて、できる限りの予防策をしておかないと、きっと後悔することになる。それだけはごめんなんだ。
立ち上がると、あたしは靴のつま先で地面をとんとんと蹴った。鉄橋の向こう側を睨み付ける。これで全部の決着がつくと思ったら、自然と気合いが入った。ユメとクロウは緊張の眼差しであたしを見ている。
「……まさき、気をつけるんだぞ」
あたしはコクンと頷いた。
シャンルーはもうずっと谷間を眺めてる。まるで、大断絶に住む風の精霊と話をしているみたい。じっと身じろぎ一つせずに、真摯な研ぎ澄まされた視線を持って、風を見てるのかな。
「シャンルー! あたし、行くよ!」あたしの言葉にシャンルーがこっちを向く。「あたしたちはもう一度、出会うんだから、それまで元気でいてよっ!」
「当たり前だ。まさきこそ、オレに会う前にくたばるなっ!」
「うん、もちろんだ! 約束だよ。死んでたら、骨を掘り起こしても会ってやる!」
「何をおバカなやり取りをしてるんだか……」ユメが呆れたように言った。
風がやむ。強かった風も徐々にそよ風になって、やがて凪が来る。失敗出来ない旅路の始まりの合図。あたしがこのシャンルーの架け橋を信じ切れなかったら、あたしは谷底に真っ逆さま。クロウがサポートしてくれるだろうけど、昨日みたいに上手に拾ってくれるとは思えなかった。クロウとユメを疑ってるワケじゃないけど、奇跡は二度も起こらない。
風がやむ。みんなとのお別れが近づいているんだね。けど、もう泣かない。あたしは必ず会いに来る。アクアとフゥが一つになったら、あたしはこの場所を探し出してみせる。
「まさき、時間だ、行け!」
「うん!」あたしはユメの顔を見て大きく頷いた。
「行くよ! レディ・ゴー」
あたしは走る。向こう側についたら、そこはきっとあたしの世界。そして、二つになった一つの世界は元の姿を取り戻す。あたしがこの鉄橋と、ここで過ごしたみんなの思いを信じ切れたら、アクアリュージョンの夢が叶う。
カンカン……。小気味よく足音が響く。この長距離走、単調のように見えて実は大変だった。昨日、走りながら、あらぬ方向にひん曲がってあたしのじゃなをする鉄骨とかは折ったり、さらに曲げたりしてよけたはずなのに。余程、この架け橋が傷んでいるのか、それともあたしの邪魔をしたいのか判らないけど、上の方からまた色々降ってきてる。
これは心してかからないと、足元まで抜けちゃうかも。カシャン……。
「え……?」
右足が金網に取られた。あたしはバランスを崩してつんのめる。でも、これで左足を思い切りついたら、金網が抜けちゃう。足が突き抜けたら、怪我をしてもう走れない。そうなったら何もかも水の泡だ。ここまでがんばったんだから。ここは転んでしまえ。
と思ったけど、そうは行くか。あたしは両手を金網について、引っかかった右足に軽く力を入れて、金網を蹴り上げた。すると、背中が金網に落ちて、その勢いで前転をした。
「ふう、我ながら上出来!」
あたしは再び走り出す。今度は同じ失敗はしない。まだ、半分も来ていないから油断は禁物だ。
「なあ、ユメ。まさきは向こうまで行けると思うかい?」いつか、クロウの言ったことを思い出す。
「行くさ。まさきは思いこみが激しいんだ。行けなくても行き着く。それがまさきさ」
微睡みの中、あたしはユメとクロウのそんなやりとりを聞いていたような気がした。信じてくれて、ありがとう。だから、あたしは期待に応えなくちゃならないんだ。五百十二人目の挑戦者は真のファイナリストにならなくちゃならない。
そんな想いを胸にあたしは走った。
「――橋から眺める風景」
あたしは呟いた。見てみたい。この架け橋から、大断絶を見る一度きりのチャンス。少しくらい横を向いても大丈夫だよね。大丈夫じゃなくても、あたしの破滅的な好奇心は抑えられない。ユメが聞いたら“狂ってる”とか何とか悪態をつくんだろうけど、そんなの関係ない。
思い切って、まず足元から。……奈落の底まで通じているみたい。金網の間から見える景色はあまり面白くない。断絶が深すぎて暗いから、全然視界が開けていない。だから、あたしはもう横を向いた。ひっくり返って転んだら、その時はその時だ。もし、そうなっても、許してね、フゥ。
「うぁああぁ」言葉が出ないって、こういうことを言うんだとあたしは思った。
綺麗。どこまでも大地が裂けてる。終わりなき谷間。ずっと遠くの向こう岸に滝があるのが確認できた。あれに太陽の光が当たったら、とってもステキな虹が見えそうな予感がする。けど、あたしにはもう見れない。ちょっぴり残念だけど、それは諦めるしかないね。
そして、通路の終わりがあたしの視界に入り出した。でも、あれは終わりじゃない。見えないだけで、あの先もずっとあって、大断絶の向こう岸までつながっているんだ。
風は吹かない。あたしが作業通路を駆けるカンカンという乾いた金属音以外に聞こえる音はなかった。まだ覚めやらぬ朝の静寂。いつものあたしだったら、まだ寝てるな。だから、少しだけ得した気分。鉄骨の間から見える大断絶もいつも外から見るのと趣が違って面白い。
「……もうすぐ切れる」
昨日、飛び降りた架け橋の切れ目が近づいている。でも、今度は大丈夫。フゥがいる。みんなの思いがあたしを支える。アクアリュージョンとフゥリュージョンが一つの世界になったらまた会える。そう言ったよね、ユメ。それまで、さよなら。
あと、十メートルくらいかな。止まるなら今のうち。だけど、あたしは止まらないよ。信じてる。他の言葉なんか必要ない。ただその一言だけがあったら、あたしは絶対に見えない金網を踏みしめることができる。あと、三メートル。そして……。
あたしは虚空へと最初の一歩を踏み出した。
胸がドキドキする。この右足が空を切ったら、この世界で過ごした一週間が全部水の泡になるんだ。今度はクロウが幾らがんばっても間に合わないよ。だって、約束したんだ。何があっても渡りきれる。だから、来るな。それがフゥとアクアの思いを信じたことになるんだって。ちょっとだって疑っちゃいけない。相手を信頼させるのは難しいんだ。一度、壊してしまったら、すぐには修復出来ないから。
「まさきぃ〜〜!」
橋のたもとからユメの声が聞こえたような気がする。クロウの咆吼が谷間を駆け抜ける。
風が吹く。そよ風から、再び、猛り狂う嵐の予兆、竜の咆吼が近づいてくる。あれに呑まれたらあたしたちの負けだ。五百十三人目はもっと足の速いのを連れてこないとね。けど、負ける気はしない。アクアとフゥと焦がれた世界にあたしたちの思いを届けてやるんだ。
「一つになろう。そうしたら、見えなかったものが見えるから」
あたしの右足は作業通路を捕らえた。
「まさきぃ〜! 待ってるからなぁ! 必ず、来るんだぞ!」
風景が変わる。アクアリュージョンの緑いっぱいの風景から……。
『ありがとう』
誰かが遠くでそう言ったのが聞こえたような気がした。
そして……。風景が白さに呑まれる。すぅ〜っと霧が立ちこめて視界が失われていくかのように。明瞭な輪郭が失われて、ぼやけ、濃い色彩は淡く。やがて、彩色を失う。明度は高く、白い闇の中に放り投げられて、あたしの前から手に触れ、目に見えるものがなくなる。
覚えてる。前にも味わったこの感覚。昨日の決死のダイビングとは違う。でも、昨日のあれはそんな気持ち悪くならなかったなぁ。腰骨、背骨は砕け散ったかと思ったけど、遠のこうとした意識の中にあったのは風が身体をなでていく奇妙な感覚。
けど、今日のは吐きそう。二度も勘弁してください。
「もうっ、こんな感じ嫌だよっ!」フリーフォールは嫌いなんだって。
「……何が嫌なんだって?」聞き慣れた声が隣から聞こえた。
「え?」あたしは横を向いた。足は地に着いてる。床。美術館の床だ。
「ゆ……ゆうや! あはっ! ゆうやだ。無事、無事だったんだね」
あたしは欲しいものを買ってもらった子どものようにはしゃいだ。フォーレスタで消えたあと、どこに行ったんだろうと思ってた。けど、無事に帰ってきてたんだね。フゥは約束を果たしてくれた。ここにいるってことはあたしはアクアとフゥの思いに応えられたのかな。
嬉しくなって、あたしはゆうやの腕にギュッとしがみついた。
「おい……、そんなにくっつくなよ。は、恥ずかしいだろ」ゆうやらしいね。
「ううん。まだ、大丈夫だよ」あたしは目を閉じて首を横に振る。
だって、まだ、周りが静かだもの。出発した時と同じように、ここにいるのはあたしたち四人? だけ。他には誰も見てない、誰もあたしたちを感じていない。だから、恥ずかしがらなくてもいいんだよ。ゆうやは覚えているのかな。
「ねぇ、ゆうや。覚えてる……?」あたしはそっとゆうやの視線をガラスケースに誘った。
あの日、たった一つで淋しそうに佇んでいたアクアマリンの瞳。その時、ゆうやの言ったことをあたしは覚えてるよ。『そいつは二つ並ぶのを夢見てるのかもね?』その通りだった。二人は焦がれた。ずっとずっと、あたしたちが生まれる前から二人はこの時を待っていたんだ。
アクアマリンの瞳の隣にはファイアレッドの瞳が眠っていた。まるで最初から、あったように。
「……覚えてる」ようやく、ゆうやは口を開いた。「目が覚めたら、俺の前にフゥがいた。赤い綺麗な瞳を開いて、何て言ったと思う?」
ゆうやはアクアとフゥを見ていた視線を外して、あたしを見た。あたしも見詰め返す。もちろん、フゥが何て言ったのか、あたしには判る。だって、女の子だもの。ゆうやには少し可哀想かも知れないけど、フゥはきっと……。
「待ってろって。まさきを信じて、待てと言った」
「……それで、ゆうやはどうしたの?」あたしは意地悪な笑みを浮かべてゆうやに詰め寄った。
「待ったよ。逃げ出す気になれば、いつだって逃げれるような場所だった。けどさ、逃げちゃダメなんだと思ったよ」ゆうやは言葉を切ると、再びフゥを見ていた。
「どうして、そう思ったの?」やっぱり、気になるよね。
「つぶらな瞳を潤ませて、訴えてたからだよ。いつも『信じて、待て』それしか言わなかったけど、まさきや俺に危害を加える気がないのは判った。帰り道も判らないから」
「はぁ〜ん。泣き落とされてしまったという訳ですか。キミは!」
何だか、しゃくに障るぞ。ちくしょう。あたしは精一杯、がんばったのに。
「けど、ね?」不意に思い出した。「フォーレスタでのこと覚えてる……?」
あたしは恐る恐る問い掛けた。もし、覚えていたらどうしようと思った。あたしに襲いかかってきたことを覚えていたら、ゆうやはきっといつか心を壊す。そんなのヤダ。
「それが、何か、最後の一日か二日くらいって、何も覚えてないんだよねぇ?」
「えぇ?」あたしは素っ頓狂な声を出した。
そして、もの凄い勢いでフゥのいる方をみた。すると、気がついたかのように目がパッチリ開いていた。二人とも目を開いていて、じっとあたしたちを見詰めていた。アクアの瞳は鋭い眼光を放っていて威圧感がある。フゥの赤い瞳は優しい色をたたえている。そして、フゥがウインク。
『わたしたちの望みは人を傷つけることではない』フゥみたいだね。この声は。
「でも、あの、フォーレスタの卒塔婆の群れは……なんなの……?」あたしは聞いた。
『初めからそうだったものに戻るんだよ』アクアが目を閉じた。『マイと一緒の墓守もおしまい』
「え……?」それはあたしと別れる時、マスターが最後に言った言葉。
『向こうで初めて会った時……片割れを探せと言ったのは、我』
それ以上は聞かなくても理解できた。この際、ことの真理なんかどうだっていい。詰まるところアクアはマスターとあのボロをまとった男が自分なんだと言いたいんだ。
「そうなんだ。キミが全部、仕切ってたんだね?」
『そう言うことだ。すまない』どうして、そこで謝るのかな。だから、あたしは言ってやった。
「謝ることなんかないよ。むしろ、あたしがお礼を言いたいくらいなんだから。貴重な体験をありがとう。キミたちに出会わなかったら、あたし、こんなステキな冒険には一生出会えなかったよ。だから、ありがとう。ユメや、アクアリュージョンのみんなに会わせてくれてありがとう」
本心だった。最初は冗談じゃなかったけど、本当にステキだった。
『ありがとう……』
アクアとフゥの二つの声色が重なり、二つの瞳が閉じられるた。もう、この目が開いて、喋っているところは見られないのかもしれないね。
そして、雑踏がかえってきた。まるで、あたしたちの一週間なんてなかったみたい。何事もなかったように。あの日、来た時、一個だけだった“秘宝”は二つになった。けど、最初から二つだったみたいに。警備員さんも、他の来館者も誰も、それは青色の一つだけだったことに気がつかない。ここに運ばれてきた時から、アクアとフゥは対になってガラスケースの向こうにあったかのように。
「ほら、帰ろうぜ、まさき。遅くなったら、と〜ちゃん、か〜ちゃん、うるさいから」
感傷にふけってところをゆうやに引き戻された。折角、いい気持ちだったのに。
「そうだね、ゆうや、今日は帰ろう。……けど、ゆうや」
あたしはゆうやの腕を捕まえて、目を細めてニヒヒと笑った。
「今度はあたしが誘っちゃう。週末、ちょっと付き合ってよ。約束したんだ。もう一度、出会おうって。だから、ゆうやも付き合ってよ。その人と約束したんだ、ゆうやも連れてくって」
「そ、その人って誰だよ?」声のトーンがおかしいぞ。少し動揺しているみたい。
「会えたら判る。だから、その時までの秘密っ! さぁ、帰ろっ!」
あたしはゆうやの言葉をするりとかわして、歩き出す。
「おいっ! ちょっと待てよ。まさきっ! そうやって、中途半端にするのよせって」
「ふふ〜ん♪ 教えて、あげない。教えて欲しかったら、あたしに勝って見せろっ!」
「あ、それは卑怯だ。学校ナンバーワン、アスリートに俺が勝てる訳ないだろ?」
あたしはゆうやに振り返った。そうやって、最初から希望を捨てるのはダメなんだぞ。あたしはユメや、クロウにそう教えてもらった。がんばって、努力して、ダメそうでもそれでも諦めない。やっぱり、そうじゃなくちゃ。勝とうが負けようが、成功しようと失敗しようと、結果に辿り着くまでに何かがある。それがとても楽しいことなんだって、教えてもらった。
だから、次はあたしがそのことをあたしに教えてあげるんだ。
「さぁ〜て、諦めるのはまだ早い」あたしは腰の後ろで手を組んだ。「ハンデをあげよう!」
「ハンデ?」ゆうやの瞳が瞬間きらっと輝いた。やる気だな。
「ゆうやが美術館から出たら、あたしも走る。ゴールは駅まで。いいかなぁ?」かなり真面目な顔になってゆうやは頷いた。「じゃ、迷子になったらダメだよ? レディ、ゴー!」
ゆうやの姿が玄関から消えて、あたしも走り出した。
ユメ、ゆうやは元気だよ。何にも心配することなかったんだ。アクアもフゥも悪いやつじゃない。だから、セイと一緒にもう少し待っていてね。あたしたちは必ず再び出会う。