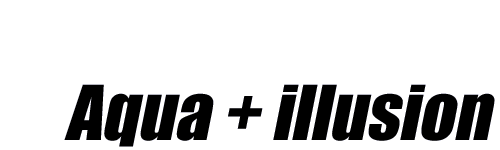
10. 丘の向こうのファイナリスト
「だから、いつまで寝てるか、このバカ娘!」
階下からお母さんの声がする。今何時? 七時半。まだ、楽勝だよ。あたしの足だったら、顔を洗って、ご飯を食べて、歯を磨いて、着替えても、まだ余裕があるよ。
「それ以上寝ていると、今日も千五百、持久走だぞ! 判ってるのか? 柊まさき!」
そう、あたしは柊まさき。疲れているんだから、いいでしょ。遅刻しないように起きるから。
「こら! 朝ご飯食べないつもりか」
大丈夫だって。お母さんも心配しすぎ。って、
「……ひ〜ん。お母さん。七時までに起こしてって言ったのに、どうして、起こしてくれないのさ。これじゃあ、いつもと変わらないじゃない。また、ダッシュ?」
「文句を言うな。毎日、七時から叫ばしておいて、何て言い草だ」すごい苛立たしげだ。「もう、いいから、さっさと着替えて降りてくる! パンと珈琲、食って、飲んでけ」
そんなの判ってるよ。朝食は身体の資本だって誰かが言っていたよね。それに食べていかないと一日持たないんだから。まだまだ、育ち盛りなんだから。ううん。こんなコト考えてる場合じゃない。早く着替えないと、ホントに遅刻しちゃう。
「って、うわぁあっ!」あたしはまたベッドから転がり落ちた。
「……、こら、まさき! 二階の床をぶち抜くつもりか」お母さん、ご機嫌斜めだ。
「ち、違うって、セ、セーラー服をかぶったら前が見えないくて……」
「だったら、ベッドの上で着替えるな!」
もっともな返事が返ってきて、あたしはそれ以上何も言えなくなった。 ともかく、あたしは着替えをすませて、下に降りた。そしたら、お母さんはあたしの上から下までをくまなく眺め回して大きくため息をついた。何で?
「ま、どっちにしても朝食抜きは良くないから、食ってけ」
そう言って、お母さんは焼きたてのトーストと珈琲をあたしに渡してくれた。
「……今日もゆうやくんが待ってるんじゃないの?」意味ありげにニヤニヤしてるね?
「なぁに言ってるの? そんな毎日毎日来ないよ。あいつだって。遅刻したくないだろうしぃ」
「ほ〜う」あたしを横目で見詰めながらわざとらしい返事。
ピンポーン。こんな時間に誰だろう。あたしはパンを口に運びながら、玄関に行く。近所の子どもたちがピンポンダッシュしていったんだろうと思いつつ、玄関ドアをおもむろに開けた。
「もふぅっ!」
うあぁ。ゆうやだ。しかも、バッチリ目があって、食パンをはんでるところを見られちゃった。恥ずかしすぎるよ。あたしは、一瞬、唖然としてたゆうやを無視してドアを閉めた。冷や汗が背中からだらだら。みっともないったらありゃしない。
「まさき、どうしてそこで戸を閉めるんだよ。早くしろよ!」
ゆうやがドンドンとドアを叩く。その気持ちは判るけど、少し抑えて。
「ほぉ〜」お母さんがあたしの後ろで腕を組んで頷いてる。「あのシャイボーイもなかなかやるようになったじゃない。そして、我が娘はその思いを無下に蹴散らすか……」
「ちょぉっと、お母さん、何言ってるの?」
「早く、飯食え! まさきっ! のんびりしてたら、真面目に遅れる!」
「麗しの君が今か今かと待ち受けているぞ」うろたえるあたしの鼻っ柱を突っつかないの。
「だって、こんな格好見せられる訳ないじゃない」
「……」凄い嬉しそうな微笑みを浮かべてる。「意中の君になら良いではないか」
「いい訳ないでしょ!」
「まさきっ! それより、お前、何で制服着てるんだ?」
「おっ、なかなかいいところに気付きましたね。ゆうやくん」
「え……?」あたしは胸を押さえて心を落ち着かせようとした。
待ってよ。美術館でアクアとフゥに出会ったのが水曜日で、あれから、何日たったんだっけ。ユメとの冒険のおかげですっかり曜日感覚なんかなくなってる。でも、昨日、一昨日とがっこに行って、週末には二人でユメに会いに行こうって。
「あっ! 今日は土曜日、がっこ休みだ!」
「ご明察。週末、ゆうやくんと出かけてもいいかって、散々聞いてたでしょ? 折角、お父さんのお許しもでたのに、全く、我が娘ながら、呆れるばかりだ……」
お母さんは頭を抱えて大きなため息をついた。そんなこと言われたって、あたしはお母さん似なんだから。つまり、お母さんの若かりし日はこんなんだったってことでしょう?
「ホラ、開けてあげなさいよ」
「うん……」あたしは仕方なくドアを開けた。「おはよう……」
「おはよう? 何、呑気に言ってるんだ? 約束の時間なんてとうに過ぎてるんだぞ。全く、待ち合わせ場所に来ないと思ったら、パンをもしゃもしゃ食ってるしっ! 八時四十四分だぞ! あと、二十五分」そんなに興奮しなくてもいいのに。
「大丈夫だよ、ゆうや。あたしの足があれば、駅まで十分かからないから」
「俺の足も考えろよ……。切符も買わなくちゃ」
「……細かいよね。ゆうやって」あたしは思わず感心したように言った。
「まさきが大雑把すぎるんだって」
「そおかな?」そんなことはないと思いを巡らせつつ、あたしは珈琲カップをからにした。
「……ラスト、二十分」あたしたちの後ろでお母さんがポツンと呟いた。
「!」あたしとゆうやの目があった。
「もう、そのままでいいから来いよ」
「ダメ、着替える。がっこでもないのに制服なんか着て行ったら、間抜けだし」
「間抜けでも何でもいいよ。誰も気にしない。そんなことより、急がないとタイムアウトだ。その電車を逃したら、昼までにそこに着けないだろう?」
「ひぃ〜。折角、ユメに会いに行くのに、格好悪い」
「そんなこと言ってる場合か。そもそも出かけないと会えもしないだろ」
「う……。は〜い」あたしは諦めた。
この間まではあんなに頼りなかったゆうやなのにいつの間にこんなに意見を言うようになったんだろう。驚きは隠せない。けど、こんなゆうやも悪くない。あたしはまじまじとゆうやを見る。
「な? 何だよ……」訝しげに眉をひそめる表情は似合わない。
「ふふ〜ん、別に」あたしは腰の後ろで手を組んで意地悪に口元を歪める。そして、ゆうやの肩をポンと叩き、傍らを通り過ぎた。「さぁて、岡田ゆうや! 時間切れになる前に行くよっ」
どんなにゆうやが変わっても、これだけは譲れないな。あたしはドアノブに手をかけてニヤリ。
「レディーゴー!」あたしは駆け出す。
「うわっ、卑怯だぞ」
卑怯結構。うかうかしてるゆうやが悪いんだ。あたしは通い慣れた道を駆けて行く。駅はがっこに行く途中にある。駅までは一・五キロ、がっこまでは約三キロ。ゆうやはどうか知らないけど、あたしは楽にたどり着けるよ。そして、ゆうやは駅の階段を上る頃にははぁはぁと息を切らしていた。何だか情けないな。もっと体を鍛えてもらわないと困るぞ、ゆうや。
けれど、責任感は強いんだ。ヨレヨレしながら切符を買いに行った。
「まさきっ。早く、改札。発車ベルが鳴る!」
妙に生き生きとしているね。ゆうやはこういうことは好きなんだね。あたしたちは改札を駆け抜けて、連絡橋を渡って、プラットホームに駆け込んだ。発車ベルがリリリと鳴ってる。ホームの隅っこで駅長さんが発車の合図を出そうとしていた。
「あぁ、待って、待って〜!」あたしは叫びながら手を振って、電車に飛び乗った。
「はぁっ……。しかし、まさきはよく息切れしないでいられるな」
ゆうやはシートに身を投げ出して座った。
「キミとは鍛え方が違うよのだよ」あたしはゆうやの隣にちょんとおさまった。
「でも、制服だろ?」
「制服なのはキミのせいだ」
「はぁ? まさきが寝坊するからだろ?」
「ゆうやが調べものをサボろうとするからだ」
顔を覗き込みながらそう言ったら、思い当たる節があったのかうつむいて押し黙っちゃった。
今日までの二日間。あたしは必死になって色んなものを探した。二つの世界が一つになったなら、絶対にあの風景が、あたしの見たあの風景がどこかにあるはずなんだ。その場所を見つけられたらきっとユメに会える。
でも、はっきりとした手がかりがない。あの高台から見下ろしてた景色。あそこにいたら、自分がまるでその景色の一部になったみたいな錯覚に囚われる。小さな山に挟まれた谷間のどこまでも続いていた畑と、澄んで暖かかった空気。ひょっとしたら、シャンルーの鉄橋だって現役で使われているのかもしれない。何だっていい。写真や絵があれば絶対にあそこに行けるのに。
この二日ずっとそう考えてた。けど、あたしの手元には写真も絵もない。あるのはユメと二人で歩いた記憶。リンネや、ジュンの家族、ヨウ。シャンルー、クロウ。あたしたちは再び出会えるのかな。あの時はいつまでかかってもいいと思った。けど、会えないかもしれないと思うと、急に会いたくなって我慢ができなくなった。
そんな時だったと思う。
あたしは、あたしの鞄の底に一枚の絵とヒントを見付けた。絵はあたしがユメと一緒に見下ろしたマルーンヒルの全景を俯瞰したステキなもの。誰が描いたんだろう。とっても細かくて、ビニールハウスや家々がきちんと描かれていた。美術の評点、五だね。
「マルーンヒルの絵……。マスターが描いたのかな……」
車窓から外を眺めながらあたしは呟いた。
「あの綺麗な絵のことかい?」ゆうやが言って、あたしは頷いた。
でも、きっと、絵があるだけじゃ、何も判らなかったと思う。そこには“マルーンヒル”と大きく字が書いてあった。意味もなくそんなことをするはずもないと思って、あたしはそこから色々と調べてみた。旅行案内、地図帳、とにかく何でも。
「俺も見たかったなぁ」ちょっと淋しそうにゆうやが言う。
「これから、見に行くんだから、我慢しなさい」
あたしの予想が外れない限り。とは敢えて付け加えなかった。
マルーンヒルを見つけられたらみんなに会える。でも、でも! なかなか見つけられなかった。ユメと歩いたあの場所が日本のどこかだと言うことは判っているのに。農村の涼やかな景色。観光のためでも嗜好のためでもなく、必要だから出来上がった壮大なランドスケープ。
ユメに会いたい。みんなに会いたい。
と、気がつけば電車は目的の駅のプラットホームに滑り込んでいた。出発した駅とは全然趣が違って、人影はゼロ。一番ホームの向こう側は雑木林で草や木がぼうぼうに生えてる。ホームだって、アスファルトの継ぎ目からひょこひょことスギナが生えてる。たまに暖かいそよ風が吹いて、色んなものを揺さぶって過ぎ去っていく。のどかだね。
「無人駅……か」駅の全景と、改札口を一通り見渡してゆうやが言った。
「そうだねぇ……」
けど、それでいいと思った。あたしの知るマルーンヒルの雰囲気はこうなんだ。閑散としていて、どこまでも淋しい。けど、さびれているんじゃなくて、仄かに暖かい空気を持ってる。小さな駅舎から外に出るとそこにはやっぱり小さな駅前広場があった。そして、その左手に街の案内板がある。よぉ〜く見ると上の方の山が連なったイラストのところに“栗の丘”と書いてある。
「遠いな……」それを見ながらゆうやが言った。
「近くはないよね」
「まだ、ここから歩くんだよな?」
「バス、走ってないから、仕方がないでしょ。歩け、歩け」
「タクシーは使っちゃダメなの?」
「そもそも、車があまり走ってないじゃない」
「……しょうがない。歩くか……」ぶつぶつ言いながらもゆうやは荷物を背負って歩き出した。
駅から続く小さな街並み。駅前通をずっと歩いていけば、あの場所にたどり着けそうな予感がした。似てる。見てくれは全然違ったけれど、ここには一度来たことがあるような気がした。あたしが歩いたボーダーランドと同じ空気がある。
小さな商店街。人影もまばらで、閑散としていた。
風景写真集をひたすらめくって、絵と同じ場所を探した。もう、見つからないと思って諦めかけた時、失礼極まりないけどある無名の写真家の写真の中にそれを見付けた。偶然という奇跡。運はまだあたしを見放していないと思った。けど、この写真家さんの顔ってどこかで見たことがあるような気がした。それから、あたしは地図帳を繰って、この場所を見付けた。
「なぁ、まさき。この道はどこまで上ってる?」まだ、半分も来ていないのにもう弱音なの?
「……峠までに決まってるじゃない」
あたしはついつっけんどんに言った。けど、ゆうやはそこについては言及せずに。
「距離を聞いてるの」判ってて、そう言ったんだけどな。あたしは苦笑する。
「あと、三キロ、四キロ、一時間?」
「一時間かぁ」
少しほっとしたようにゆうやは言ったけど、それは峠までだからね。その先は雄大なランドスケープを横目で見ながら、自分たちがその風景の一部になるまでずっと歩く。大丈夫? と尋ねようと思ったけど、やめにした。既に見た目の雰囲気だけで全然大丈夫じゃなさそうだった。
そう思えば、アクアリュージョンもいい勘してる。今までも、カップルや親子、きっと大切なもの同士の組み合わせで色んな人を選んできたんだよね。それとも、人を見る目が鋭いのかな? あの眼光の鋭いでかい目の玉も伊達じゃないんだね。
ずっと歩いて、大きな国道での信号待ち。アクアにいた時は流石にこんなのはなかったな。車の群れが通り過ぎていく。でも、あたしたちの進みたい方向に曲がっていく車は一台もなし。つまり、ユメやジュンたちの居場所はそう言う場所。
「……」げんなりしてるね。ゆうや。
けど、本物のあれを見たら疲れなんて吹っ飛ぶから、もうちょっと歩け。
「……それとも、ゆうやなんて放っておいて、あたし一人で行った方がいいのかな」
「冗談を言うなよ。こんな人気のないところで、熊に襲われたらどうする?」
「熊?」突然、何を言い出すんだ。
「熊っ!」
「あはは! 熊なんか出てきたら二人いても一緒だって。その時は諦めるしかないよ、流石に」
そして、黙々と歩く、歩く。それしかすることがないし、喋るとそのぶん体力を消耗するものだから、二人で沈黙。舗装道路と進むとゆっくりと両脇に分かれて流れていく雑木林の緑の風景。野の花。白いガードロープに……。
「ねぇ、黙ってないで、何か喋ってよ」
と言っても、ゆうやは疲れたような笑みを浮かべてそれっきり。ユメだったら、気を利かせてもう少し何か話してくれたのに。比べるのも悪いけど。それがゆうやと言えばゆうやなんだから諦めろと言うことか? と、色々愚にもつかないことに思いを巡らせいると、不意に視界が開けた。
峠を越えたんだ。あたしたちの目の前には懐かしいと言うにはまだ早すぎるあの風景が広がっていた。細かいところは微妙に違っているみたいだけど、地形は同じ。違っているのは木の位置とか、建物の場所とか。この前来た時も、過ぎ去りながら眺めただけだからよく覚えていない。でも、ちょっとだけ違和感があるんだ。
横を向いたら、ゆうやは感嘆の表情で丘からの風景を見下ろしていた。
「すっごいステキでしょう?」あたしは腰の後ろで手を組んで、ゆうやを覗き込む。
「あ? ああ? 学校から見えるあの灰色とは違って、緑なんだな……」
「それはそうだよ。ここ、田舎だもの」
再び歩き出す。長く立ち止まっている時間はないのだよ。道なりに進む。舗装か、砂利か、という以外では道が延びていく方向には変わりがないみたいだった。あの時と同じに、坂を下って、道をくねって、角を曲がって、あたしたちは風景の一部になる。
あたしはマルーンヒルの小さな集落には立ち寄らずに、ユメと約束し場所に一番に行こうと思った。そこにマスターのシェンリースーやヨウの家がなかったら、恐いから。あれがゆうやと二人で見た白昼夢だったら淋しすぎるから。会いたいと思う反面、それは焦りにも似た恐怖だった。
「大断絶……あるのかな……」あたしは呟いた。
あの広い谷間を抜けて響いた、竜の咆吼をまた聞けるのかな。
あたしたちはマルーンヒルの山の間の狭い平野を歩いた。そう、途中でリンネに会ったんだよ。初めて会った時は途方もなく恐い人だと思った。けど、違ったんだ。もし、リンネがセイじゃなかったら、あたしはどうなっていたんだろう。
大断絶に続くはずの一本道を進む。この道は大断絶を渡っているのかな。アクアの世界ではこの道は岸に着いたら途切れていた。向こうまで渡りきれない無念の道筋だった。そして、一つになった二つの世界では橋が架かっていた。
「……」
大断絶と呼ばれた大地の亀裂は小さな小川みたいになっていた。何か、色々とスケールダウンしているみたい。ちょっと残念。あたしはふと左手の方を向いた。クロウの背に乗って空を飛んだ時、この方向にシャンルーの鉄橋が見えたから。
でも、全長三キロにも渡るシャンルーの架け橋は欠けらも見えなかった。そう、ここに来る時、電車が通った小さな鉄橋が“シャンルーの架け橋”だったのかな。
……風が吹いた。優しく頬をなでていく心地のいいそよ風。その風に乗って、声が聞こえた。あたしたちの行く手から。
「――まさきとの待ち合わせ場所はシャンルーの洞窟。……どうして、架け橋にしなかったの?」
「記憶を頼りにするんだったら、先にこっちの方に来るんじゃないかなってさ」
「ふ〜ん。まあ、妥当なところだろうね。あれを想像したら、まず判らないよね」
「きっとね。……あれは土か風の方に近かったんだな……」
「うん……」
「だがなあ、まさきは本当に来ると思うか……」
一つは知っている声。もう一つは知らない女性の声だった。あたしたちは二人に気付かれないようにそっと近づいていった。声をかけて、万が一、全然違う人たちだったら恥ずかしいから。
「来ると思うよ。あの娘。こういうことにかけてはしつこそうだから。それにマスターが言っていなかった? まさきが来れるようにこっそりヒントを渡しておいたって」
二人は谷の方を見て、あたしたちにはちょうど背を向けていた。
「聞いたような気もするな」
「絵を渡したって言っていたよ」
「絵?」
「そう、絵」
「誰の絵?」
「マスターの絵だよ。昔、写真をやってたんだって。こっちに来た時は道具がなくてどうにもできなかったから、絵を描いてがんばってきたんだって。まさきの似顔絵、もらわなかった?」
「は? なんだそれ? 初耳だぞ」
訝しげに眉をひそめているよ。けど、ユメは誰と話しているのかな。
「わたしは前から知っていたよ」
女の人がユメを見上げた。その横顔は知ってる。口調も声色も違ってる。けど、その女の人はリンネ。ううん。あたしは首を横に振った。瞬間、ゆうやが不思議そうな素振りを見せたけど気にしない。あの人はユメの妹、セイなんだ。そう判ったら、あたしは走り出していた。もう、ためらうワケなんかないもの。
「けど……すぐに見付けてくるかなぁ」ユメが頭の後ろで手を組んだ。
「来ると……思ってるんでしょう? 思ってなかったら、こんなところで待ってないよね?」
セイがクスクス笑ってる。凄いいい笑顔をするんだね。あの時は荒んで見えたのに。人ってこんなに変われるんだ。と言うよりはむしろ、この“セイ”が地なんだろうな。
「まあな。意外と根性あるだろ? あいつ。セイなら判るよな?」
「うん、もちろん」
二人の会話があたしに届く。あたしたちに気がついてるの? 聞こえるようにわざと大きな声で喋ってるの? でも、信じてるんだ。あたしがフゥを信じたように信じてくれてるんだ。
「ユメ〜! セイ〜!」
こっそり近づいていって、おどかしてやろうと思った。けど、もう我慢できない。一秒だって早く二人と話がしたいんだ。あたしはリュックを片手に右手で大きく振った。
二人ともこっちを向いた。
「! まさきぃ〜!」ユメが手を振った。
「ユメ〜! 会いたかったよ」あたしは止まらないで、そのままの勢いのままユメに抱きついた。
「うわっ」
そしたら、ユメはバランスを崩して後ろに勢いよくどすんと尻餅をついた。
「何をするんだ! この」
「あはは! ごめんね。けど、どうしても止まりたくなくて」
「止まりたくなくて?」うわ、しまった。
「いや、あの、その、口が滑った」
「まさきぃ、お前、早すぎるんだよ」ようやく、悪態をつきながらゆうやが追いついてきた。
「口が滑った?」口調は怒ってるけど、目は笑ってる。よし、二の句を継ぐ前に。
「今さら、紹介しなくても知ってるだろうけど、ゆうやくんです」
少し呆気にとられたみたい。あたしとゆうやを見比べていた。
「……どうも、初めまして」
ゆうやはひどく緊張しているみたいだった。あ、そうか。最後の二、三日は記憶が曖昧だと言っていたから、ゆうやにはユメは初対面なんだ。
「初めまして、ゆうやくん」
気まずい沈黙。お互い口べたなのかな。見合ったまま喋りもしないよ、この二人。
「そ、そして、キミは――セイさん――でいいのかな?」
「そう“セイ”でいいよ。まさきちゃん?」
「あ、あたしも“まさき”でいいです」
そして、何を話していいのか判らなくなる。セイだって覚えているよね。あの時はリンネだったけど、二重人格な訳はないでしょう。あたしは口を開かずに暫くセイの優しい顔を見詰めていた。でも、うち解けるまでにはまだ時間が必要だよ。顔を見るたびにどうしても心臓がドキドキとしてしまう。だから、あたしはセイにごめんなさいをして、ユメに向き直った。気まずい空気を感じていたのはセイも同じみたいで、セイはほっとしたようにそっと頷いてくれた。
「ねぇ、クロウとシャンルー、マイは?」あたしは聞いていた。聞かなくても結論は判っていると思った。ここには来ていないんだよね。どこに行ったのかも判らないんだよね。「……ここには来れなかったんだね……」
あたしはどうしようもなく淋しくなった。シャンルーのガサガサの肌。とぼけたクロウとユメとの漫才みたいな駆け引きも聞けないのか。すましたマイ。クロウは尻に敷かれてたよね。
「ホントにそう思ってるのかしら? まさきちゃんは」セイ。
「どうやって、説明したらいいと思う?」とっても困ったようにため息をついた。
「? 何、どういう意味なの?」あたしはユメとセイの二人の顔を見比べて尋ねた。
「まず、一言で言ってみようか?」頭をかきながらユメが言って、あたしは頷いた。「まだ、終わってないみたいだ……」
「終わってない?」とても嫌な予感がした。
「ああ。言っただろ? 最後の日に。四つあるんだって」
「四大精霊。水、火、風、土ってやつだっけ?」
「そうっ!」ユメが嬉しそうに言った。「よく覚えてるな。じゃあ、話が早い。セイ……」
「はい。兄さん」
ユメに言われてセイがあたしに見せてくれたのは大きな水晶の球だった。大きさはちょうどアクアリュージョンと同じくらい。材質はガラスのようにも見えるけど、アクアとフウの例を考えると無色透明の石英だと思う。それにはやっぱり真ん中辺にひびが入っていて。
「ねぇ、ユメ……」あたしは目をそらして上目遣いにユメを見た。「やっぱり、あたしなの?」
「……まさき以外に誰がいるんだ?」さわやかな笑みを浮かべて言わないで。
「でも、これだけをもらっても、どうしたらいいか判らないよ」
「――そこに」ユメはゆうやを指さした。「優秀なブレインがいるんじゃないのか?」
「あ〜、全然、ダメなんだ。そう言うことには役立たず」
あたしは顔の前で左手を左右に振った。だって、調べものだってあたしがほとんど。背筋に痛いほどの何かを感じると思ったらゆうやがあたしを睨んでいた。
「ウソは言ってないよ。ウソは」あたしはちょっとうろたえた。
「今度は待ってるだけなんてごめんだぞ。俺も一緒に行く!」
あたしはじと〜っと横目でゆうやを見た。勉強に関しては信用できるけど、行動力についてはいまいち信用できない。その前にキミは筋金入りの方向音痴で迷子になったりしない? あたしは思わず苦笑して、ゆうやを見る。
「な? その笑いは何だよ?」
「ううん、何でもないよ」あたしはクスクスしながら首を横に振った。
と、セイから受け取った石英の球をあたしはまじまじと見詰めた。手触りは普通のガラスと同じみたい。とても経年を耐え抜いてきたとは思えないほどにつるつるしていた。所々に傷が入っていたけど、それはよく観察しないと判らないほど微細だった。
「……これ、やっぱり、目玉なの?」
聞いたら、ユメは無言であたしが持っている石英の球を指さした。
「……?」あたしは訳も判らずに手元を見た。「うわっ!」
びっくりしすぎて、あたしはこの間のフゥみたいに放り投げてしまいそうになった。目が開いてる。つぶらな瞳。でも、よく考えたら、これそのものが目玉だよね。そして、かなり不思議。全体は透明なのに瞳は何故か鳶色。なのにまぶたを閉じたら、手が透けて見える。どうして? この目玉はどうやってものを見ているんだろうね。
「どういう風になってるんだ? こいつ」
ゆうやが興味を持って球を手に取った。そして、二人でじっと見つめ合ってる。気が合うのかな。石英の瞳は好奇心満々みたいで瞳をキラキラさせながらゆうやに見入ってる。ゆうやも視線を逸らそうとしないからかなり怪しい。そして、根負けしたのか先に瞳を閉じたのは球の方だった。
「……? どうして、そこで目を閉じちゃうんだ?」
「それ、どこで手に入れたの?」
あたしは面白そうにゆうやと石英の瞳を見ているユメに尋ねた。
「まさきが帰ったその日、シャンルーがいた場所に転がってるのを見付けたんだ」
「え?」あたしは瞬間考えあぐねた。「シャンルーたちは帰れたの?」
「さあなぁ。ここにいないなら、そうだと俺は思いたい」ユメは嫌な感じにニヤリとした。「きっと、シャンルーが持っていたんだと思う」
「じゃあ、何で、そのシャンルーがいないで、それがあるの?」冗談じゃないよ。「あ〜、もう、ひょっとして、今度は突然なんてことなしにしてよ? 準備させてよ?」
「……それは俺に聞かないでそいつに聞けよ」
とユメが言ったら“そいつ”はぎょんとでっかい目を開いた。心臓に悪いよ。そして、ゆうやの手のひらの中から、じっとあたしの瞳を見詰める。
『……よろしく頼んだ』初めて口を利いたその声色はとても柔らかかった。
「うげっ、ちょっとマジで言ってるの?」
すると、そいつは頷くかのようにそっとまぶたを閉じて、ゆっくりと開いた。
『……クロウとシャンルーが待ってる』真摯な眼差しがあたしを捉える。
石英の瞳から思いもかけない名前を聞いた。つまり、キミはことの経緯を全部知っているんだ。もしかして、アクアとフゥのこの出来事でさえ、キミが仕組んだことだったの? ……それとも、キミがシャンルーなのかな。ううん、それはないよね。シャンルーや飛竜のみんなはクロウが言っていたようにどさくさに紛れて帰れたんだ。そして、一つになったこの世界とシャンルーの世界を結びつけるためにキミがあたしたちの元に現れた。
けど、そんなのどうだっていいや。あたしたちは再び出会うって約束したんだから。
「行くよ! ゆうや。レディーゴー!」