03. the bell of eternity(永遠を告げる鐘)
からのと気軽に会話する仲になってから二週間あまりが過ぎた。それはつまり、怪物退治をしてヴェイロンにこの屋敷へ招待された日からほぼ二週間になることを指していた。当初の予定ではここで長居するつもりはなく、シメオンで山羊の肉にありついてるはずだった。さらにはシメオンをも越えて、北リテールまで足を伸ばしているはずだった。
「……飽きた――。そろそろ、新しい風を感じて、清流の水を飲みたい……」
「アーネストさま、屋敷のお水がお気に召さないのなら、清流の水を取り寄せて……」
「からの。そう言うことじゃないんだ」
「――どう言うことなんですか?」
「自分の足であちらこちらを訪ね、そして、欲しいものを手に入れる。他人に頼っていたらダメだったこと。人の助けを借りてばかりいたら、真の英雄とは言えないな」
「そう言うものですか?」
何十回目かのからののそれをアーネストは聞いた。
「そう言うものなのさ。人は一人じゃ生きていけないと言うけどね、何でもかんでも依存したらダメだよ。自分ですべきこと、譲れないことを他人任せじゃね。例えば、俺の今の状況なんてそんな感じだよ。みんな、とてもよくしてくれるけど、物足りないんだよ」
「その日暮らしの方が満ち足りてるんですか?」
「いや、そ〜じゃないって。――そろそろ、潮時だと思って――」
「潮時って……」からのはひどく心配そうにアーネストの顔を覗いた。
アーネストは屋敷を出ることを決めた。気ままな風を自称するにはこの屋敷に長く居すぎたと思う。こんな調子ではリテール全域を旅し終える頃には骸骨にでもなっていそうだ。それでは困るし、アーネストとしては世界のあちらこちらを回って、見識を広めたい。
「……からのの想像の通りだよ」アーネストはからのの肩を押さえて、小さく頷いた。「ここには長居しすぎたよ。俺は旅の身、気ままな風さ。或いは清流の清水の如く。一つの場所に長く居座ると、色々なものが淀んでしまうのさ。だから、行くよ」
そこで、アーネストはからのの瞳をジッと熱い眼差しで見詰めた。
「……からのも俺と一緒に来ないかい? 外の世界に興味があるんだろ?」
アーネストは朗らかに言った。他意はない。暇さえあれば、アーネストに外の世界のことを訊いてくるからののことを思ってのことだった。人伝に話を聞くよりも、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の感覚をフルに活用して世界を感じるのが最もいいのに決まっている。
「わたしは……」からのは瞳を潤ませた。
「からのに見せたい景色があるんだ。リテールには珍しい小高い丘でね、遠くまで良く見渡せるんだ。キレイでステキな場所だよ。夕焼けの空の下、そこからリテールを眺めるんだ。黒き湖の割と近くにあるんだよ。あの場所はまだ誰も知らない。キミに最初に見せてあげたいんだ」
嬉しい。有り難い。からのの心はアーネストに対する感謝の気持ちでいっぱいになった。
「……い、行けません」からのは俯いて小声で答えた。
「どうして……?」
からのにはその理由は答えられなかった。ただ、アーネストから視線を逸らし、沈黙した。ヴェイロンには拾われて以来、ここまで育ててもらった恩もある。ついこの間、知り合ったばかりのアーネストに付いて屋敷を出たら、それはヴェイロンに対する裏切り行為だ。
(からのを躊躇わせているのは何だろう……)
アーネストの考えによると、そんなことはなさそうなのに。メイド長さんはからのの仕事ぶりに辟易としているようだし、他の召使いさんとはあまり親密でもなさそうだ。とすると、ネックになってるのはヴェイロンへの恩だろうか……。
「――ヴェイロンには俺から話をしておくから心配しなくていいよ」
ヴェイロンはからのに色々と手を焼いているようだから連れて行きたいと言っても、問題なくすぐにオーケーをくれると軽く考えていた。が、敵はどうやらヴェイロンではなくからの本人のようだ。心の奥底ではアーネストの提案を応諾したいようだけど、何かが拒絶させている。
「――いえ、そう言うことではないんです」
からのは頑として譲りそうにもない。アーネストは無理に連れて行く気にはなれなかった。理由はどうあれ、着の身着のまま宿無しの旅にからのの同意なしには連れて行けない。楽しくはあるけれど、いつだか飢え死にしかけたように過酷な一面があるからだ。
「……そっか、残念だけど、一人で行くよ」
「あ……。そう言う意味じゃ……」
からのは顔を上げてアーネストを引き留めようとした。瞳はまだ迷っている。からのの揺らぐ瞳を見て、アーネストはそう読み取った。からのの迷いを断ち切れなくても、もしかしたら、自分と一緒に旅立つことの出来ない理由を聞き出せるかもしれない。
「じゃあ、どういう意味?」
「それは……。――何でもありません……
アーネストが質問をするとからのは押し黙ってしまった。いらぬコトを喋ってはならぬとヴェイロンからきつく言い渡されているかのように。からのはまとても淋しそうな瞳でアーネストを見ていた。後ろ髪を引かれる思いだ。でも、アーネストの決心は一つも……一つくらいは鈍ったかもしれない……鈍らなかった。自らの信念を貫き、放浪の旅を続けるのだ。
「……必ず戻ってくるよ。その時は一緒に……」
流石にからのを置いては意気揚々とまではいかないけれど、世界にはアーネストを待つ美女が、もとい、助けを求める人たちがたくさん待っているはずなのだ。アーネストは荷物をひとまとめにして屋敷を後にしようとした。二週間前にくぐって入ってきた門を通って。
アーネストはヴェイロンに誘われ屋敷を訪れた時とは逆に、空腹を満たし、疲れを癒し、鞄には分けてもらった乾燥食料をしっかりと詰めた。少なくとも、シメオンに辿り着ける分だけの食料はあるから、途中で倒れると言った失態は演じなくてすむだろう。アーネストは足取りも少しは軽くなって歩く。けれど、何かがおかしいような気がした。普通じゃない。平原の風景が行けども行けども変わらないのは当然のこととして、それを加算して考えても違和感は拭えない。
風がそよとも吹いていない。微かではあるが、空気が淀んでいるような気がする。周囲に気を配って歩いてみると、同じ形状をした木が何度も何度も自分の行く先に現れる。明らかに不自然だ。
「おかしいな……。……?」
気がつけば、何故だか判らないけれどアーネストは屋敷の裏庭に立っていた。そんなはずはない。とばかりに、アーネストは再び正門を飛び出して歩いた。しかし、結果はさっきと同じ。同じ風景がくるりくるりと二回転、三回転して、フと気が付くと屋敷の裏庭にいる。三度目のチャレンジは正面から出るのが悪いのだと、逆から回ってみたが事態は何も解決されなかった。
(自分で判らないなら……、誰かに聞くしかないか……)
アーネストはキョロ、キョロと辺りを見回して、たまたま歩いていた召使いさんを掴まえた。
「ここから出られないんだけど、どうしたら出られるのかな?」
「ここは閉じているのです。ここから出ることは出来ません、永遠に」
永遠に出ることは出来ない。アーネストにはそのニュアンスが伝わっただけで十分だった。ヴェイロンは魔術師だから、魔法で屋敷を隔離しているのかもしれない。ならば、ヴェイロンの魔法により隔離、隠された場所から抜け出すのは容易ではない。頭で判っていても、感情は抑えきれない。
「しかし、俺はここから出たい! 今すぐに」
「――ご自由にしてください」
ご自由にと言われても。とアーネストは思った。ご自由にして出られないから訊いているのに、その答えは答えになっていない。でも、いつもは生真面目で温かな召使いさんもこのことは知らないのか、触れられたくないのか素っ気なくなってしまう。アーネストは十分すぎるくらいに何か隠し事をされていることに気がついていた。こうなるとますます外に出たくなる。
と言って、打つ手がないのもまた事実。
「――ここには恥ずかしがり屋の精霊姉弟はいないのかな……?」
アーネストはブチブチ言いながら、一回戻って新たな策を練ってみることにした。と言って、すぐに妙案が浮かぶとも思えない。この屋敷から外へ出られないと言うことは空間がねじ曲がっていて、さらにきっと、時間の流れもおかしな事になってるに違いない。としたら、大して魔法に自信のないアーネストが策を弄するだけ無意味かもしれない。誰かの助けを借りないとダメかも……。
しかし、一週間、二週間と焦燥のうちに過ぎていった。
その間、ヴェイロンは一度もアーネストの前に姿を現さなかった。召使いさんたちの話を総合すると、ヴェイロンは自室で研究に勤しんで部屋から出てこないそうだ。そして、これは決して珍しいことではないらしい。しかし、それを悪い方に考えると、ヴェイロンはアーネストとは会話したくないと暗に指し示しているのかもしれない。
「――勘ぐるだけ無意味なんだけどな……」
仕方なく、アーネストはからのに根掘り葉掘り尋ねてみた。けれど、そこから得られたのはないようなものだった。からのの知ってることは他の召使いさんたちと大差なかった。いい加減、脱出の仕方を考えるのもイヤになる。自分で出来る方策は全て試したが、結局は徒労に終わった。
「なぁ、からの。ここはどのくらい昔からあるんだい?」
アーネストはベッドにゴロンと転がって、天井を見上げた。
「判りません」申し訳なさそうにからのは言った。
「ふ〜ぬ」アーネストは俯せになって枕を抱き寄せた。「お屋敷はよく手入れが行き届いていてピカピカだけど、ピカピカすぎていつから建っているのかは全然だな……。しかし、今はそんなことより、どうやってこの屋敷の敷地から出るかだな……。ヴェイロンはどうやって、この屋敷と外を出入りしているんだ……? それさえ判れば、俺も――」
アーネストの苦悩は簡単にはケリがつきそうにもない。だが、ヒントは必ずヴェイロンの行動に隠されているのに違いない。ヴェイロンは確かに屋敷の敷地外にいたはず。でなければ、アーネストはここにいるはずがないのだ。と言うことは、屋敷から外へ出る方法が何らかの魔法として存在しているはずだ。全ての事柄が憶測の域を出ないが、絶対に間違いはないとアーネストは確信していた。そして、その方法を必ず手に入れる。
「……からのはここから出たくないのかい?」
アーネストは暫く尋ねなかったことを改めて尋ねてみた。今日こそ、からのの本心を聞くと決めたのだ。アーネストは一歩も譲らないぞと決意を込めた眼差しで見詰めた。
「――一度でいいから、外の世界を見てみたいです……。でも、わたしは――」
からのは自身の思いをアーネストに告げることはなかった。アーネストがこの話題を切り出すと、決まってからのは淋しく、暗い顔をする。
「ごめんなさい。アーネストさま――」からのは部屋を飛び出していった。
からのが出て行った後でアーネストは日向ぼっこをしに庭に出た。屋敷の中にいても気が滅入ってくるばかりだ。外からの出入りは不能と言っても、日は射すし、風は吹くから気持ちはいい。アーネストはぐぐ〜っと両腕を空に伸ばして伸びをしながら、居心地の良さそうな場所を探し出した。毎日同じ場所と決めるのもいいが、気ままな風と自称するからにはこう言うところにも気を遣う。
アーネストはゆらりゆらりと歩いて、庭の片隅の木立の陰を今日の居場所と定めた。
「あ〜あ、八方塞がり二週間。いい加減、退屈な上に打つ手なし。どうにかならないかな……」
アーネストは木の根本に腰掛けて、何気なく屋敷を見上げた。改めて考えてみると、アーネストは屋敷全体を外側から隈無く観察したことはなかった。
「……あれは……?」
フと鐘楼が目に入った。考えてみると一度も鐘が鳴ったのを聞いたことがない。近所迷惑だから……と言うにしても辺りに家はないし、鳴らし放題だと思う。しかも、さらに深く考えてみると、鐘楼に上る階段、梯子が屋敷の中にも外にもない様子だった。
あれれ。アーネストは不審に思って、近くで庭仕事をしている召使いさんに尋ねた。
「鐘楼への入り口はどこにあるんだい?」
「――ありません」召使いさんは手を休めて、アーネストの顔を見詰めた。
ありませんと言われてもすぐには納得できない。そもそも、鐘は鳴らすためにあるのに鐘楼への道筋がないなんておかしすぎる。アーネストはさらに探るため、アプローチの仕方を変更した。
「はぁ……。そういえば一度も鐘の音を聞いて無いなぁ。どうして鳴らさないんだい?」
「わたしどもには分かりません。――ただ、あれは鳴らしてはいけないものだと……」
尋ねてみると、要領を得ない返事ばかりが返ってくる。鐘楼への出入り口もなく、鳴らしてはいけない訳もないのに鳴らさない。もちろん、鳴らす理由もないんだけど。アーネストは腕を組んでひとしきり考えた。あれには何かある。絶対に何かがあるに違いない。ついでに、鳴らしてはいけないと言われると余計に鳴らしてみたくなるのが性分なのだ。
「まあ、そう言わずに。折角だから、鳴らしてみよう」
「いけません。鐘を鳴らすとご主人がお怒りになります」
召使いさんは必死の面持ちでアーネストを止めようとした。余程、ヴェイロンが怖いのか、それとも、鐘を鳴らすとによって、この屋敷の七不思議でも暴露されるのだろうか。アーネストはますます好奇心をくすぐられたらしく、どうにもこうにも止まらない。
「大丈夫。俺から言っておくよ。君らは止めようとしてたが、俺が勝手に鳴らしたんだと。そうしたら、君らはご主人からお咎めを受けることもないだろう?」
アーネストは身振り手振りを交えながら、召使いさんの説得を試みた。けれど、取り付く島もない。ただ、どちらかというと鐘を鳴らすことを禁止していると言うよりはむしろ、主人であるヴェイロンに言われてるからダメと言うだけで、強い制止は感じ取れなかった。
「も〜いいっ! 勝手にやる――。――もし、あれを鳴らせたら、これからずっと、あの鐘を鳴らすのは君たちの仕事になるからね。止まったような時の流れにせめて、彩りを添えるんだ」
「そんな、いけません。あの鐘に触れることは許されていないのです」
「いいや、そんなことはもう関係ない。とにかく、鳴らすんだ」
拒絶されるほどに燃えるたちなのだ。アーネストは腕まくりをして何か良い方策はないものかと考え始めた。無理矢理に壁を上るか、鐘楼の屋根にロープをかけるか。鐘楼に通じる通路がないのなら、いずれにしても力任せの行動に出ざるをえないと結論した。
アーネストは登れそうな場所を見つけると、壁に手をかけて鐘楼へのチャレンジを始める。
何が何でも絶対にあの鐘を鳴らすのだ。そこまでヴェイロンに禁止された鐘ならば、鳴らせば何かが起きるのに違いない。何が起きるのかは全く予想も付かないが、今以上に悪くなることはないはずだ。むしろ、退屈な現状に変化が訪れるなら悪くなっても構うことはない。
アーネストは壁をよじ登ろうと、必死にあがいていた。けれど、垂直の壁はアーネストの挑戦を弾き返すかのようにそびえ立っている。
「くそっ!」アーネストは庭から鐘楼を見上げ、悪態を付いた。
「――君はとうとう気付いてしまったのだね」
不意にヴェイロンの声が聞こえた。けれど、辺りを見回しても居るのはさっきの召使いさんと、一人、屋敷の方から歩いてきたからのだけ。アーネストは辺りを見渡した後で、遙か上空を見上げた。すると、白い鴉がアーネストとからのの頭の上辺りを不自然に旋回していた。
「アーネストさま……」
「からの……?」
「その鐘は始まりと終わりを告げる鐘なのだ」
声はやはり、その白い鴉から発せられているようだった。アーネストはヴェイロンが鴉の姿をしているとはにわかには信じがたかったが、取りあえず、質問した。
「それはどういう意味だ!」
「その鐘が鳴らぬ限り、この屋敷は永遠にこのままと言うことだよ」
白い鴉は上空から舞い降りてくると、からのの左肩にとまった。
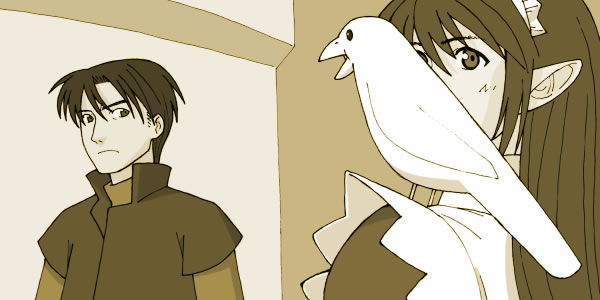
「……ここは現世と幽界との狭間にある一種の停時空間なのだよ。入るのは簡単だが、出るのは易くはない。鐘を鳴らせば、現世への扉が開く。だが、その為には代償が必要なのだ。――このまま鐘を鳴らさなければ永遠に二人+αで生きられる」
魅力的な話だった。しかし、自分で連れ込んでおいて、代償を払わなければ出られないというのも随分と身勝手な話だと思ったのも事実だった。
「しかし、あなたは自由に出入りしている!」吠えるようにアーネストは言った。
「仮にもわたしは魔術師なのでね。通り抜け方くらい心得ておる」
「その通り抜け方を教えてもらう訳にはいかないのかい?」
「教えたところで、キミがそれを行使することは不可能だ。代償を払わぬ限り」
「……その代償とは何だ?」
白い鴉はアーネストの問いに答えることなく、喋り出した。
「からのと共にここに居たら良いではないか。何も失うこともなく、永遠に……」
アーネストは心が少しの間、揺らぐのを感じた。好意を持っている人、愛する人と永久に暮らす。普通ならば、誰しも憧れることだろう。けれど、今のままなら、閉じた世界に二人きりで居て、召使いさんたちはたくさん居るけど、外界との接触がないなら死んでいるも同然だ。
「それでは生きていることにならない。誰かに何かを伝え、伝わる事こそが生きるという事なんだ。少なくとも俺はそう思ってる。そう、教えられて今まで生きてきた」
「――そうか」残念そうに白い鴉は言った。
白い鴉はアーネストのもとから離れ、鐘楼への階段を作り上げた。
「鐘を鳴らせ。……しかし、それだけでは屋敷を出ることは叶わぬ。お前の最も大切なものをかけてもらおう。屋敷をこの場から解き放つためには命であがなわねばならぬ。この屋敷は我が妻の命を持って存在しているのだ。その存在を否定するのなら命を賭せ」
それでも良いのかと言わんばかりの険しい表情、眼差しをして白い鴉は言った。アーネストはその真っ直ぐに受け止めていた。自分が一番、大切なものの命……。ホンのしばらく前までそんなものはなかったのだが。アーネストはちらりとからのを見やった。
ヴェイロンと思しき鴉はそれを知っているに違いない。
「……逆のことは出来るのか? 俺の命を賭して、大切なものを外へ出すことは出来るのか?」
「そう言った人間は初めてだ。よかろう……、お前の大切なものとお前の命を……」
「――からの……」
「……! ……や、やめましょう? アーネストさま」
からのは怖ず怖ずと言った。アーネストが自分のことを大切に思っていてくれていたのはとても嬉しいし、外の世界を知りたいとは思う。けれど、アーネストの命を賭けてまで、外の世界を追い求めていくことに価値があるか判らないのだ。からのはアーネストの右手をキュッと握り締めた。
「……いや……」
アーネストはからのの手を取り、両手を握った。
「このままでは、死んでいるのと何も変わらない。死んでいるのと変わらないなら、俺はキミをここから解き放ちたい。キミがここから出ることで、俺の思いが生き残り、それが永遠に繋がるんだ」
その言葉を聞いていると、からのの目から涙がポロポロとこぼれ落ち始めた。嬉しいのか、哀しいのかすらも判らない。アーネストは涙で頬濡らすからのの両肩をそっと抱いた。
「でも、――アーネストさまが死んでしまう」からのは震える声を絞り出した。
「大丈夫。俺はからのの中でずっと生きてる。からのが俺のことを忘れない限り、――キミの子供たちが俺のことを少しでも知ってくれたら永遠に生き続けられる……」
「でも……、でも……。アーネストさま――」
「――行くがよい。それがお前の望みならば、あの鐘を鳴らすがよい」
白い鴉はそれだけを言うともはや言うべき事は何もないと悟ったかのように飛び去った。白い鴉が去るのを見送ると、アーネストはからのの肩をポンと叩いて鐘楼に向けのびた階段に向き直った。まやかしの永遠が続くのはいけないことだ。例えどんなに生き長らえたとしても、それでは無意味なのだ。意味を求めるのなら、何かアクションを起こさねばならない。アーネストは一歩踏み出した。ここでの時を終わらせて、新しいことを始めよう。その尊さをからのに伝えたい。
「――お別れとは違うんだよ、……からの」
からのの返事は嗚咽に埋もれて聞き取れるような声にはならなかった。
アーネストは階段を登る。まるで、この世に未練の一つでもないかのように、振り向きもせずに。アーネストは階段を登り切り鐘楼にたどり着くと、誰も間近に見たことのないだろう鐘の前でしばし立ち尽くしていた。つばをゴクリと飲む。閉ざされた空間は閉ざされたままなのが一番なのだろうか。アーネストは庭から心配そうに見上げるからのをちらりと見やった。あの娘に広い世界をプレゼントしたい。からのもアーネストも知らない世界がどこまでも広がっていることを教えたい。
アーネストは鐘を鳴らす。何度も、何度も。力の続く限り。
ゴーン……、ゴーン……。重々しい鐘の音が屋敷とその敷地に鳴り響いた。
「何回鳴らせば、いいんだろう?」
重い鐘の音が響き身体中に震えが伝わる。凛とした響き。ありとあらゆるものを揺るがし、根底から覆していくような感覚。芋虫が蛹になり、やがてそれが羽化し蝶になっていくような。生まれ変わる? アーネストは力無くストンと膝をついた。風がアーネストの頬を撫でる。いつも、吹いていた風とは違う新鮮な風。何かが開こうとしている。新しい何かが始まろうとしている。アーネストは酷く久しぶりに清々しさを、始まる事へのときめきを覚えていた。
けれど、身体に力が入らない。
「アーネストさま! アーネストさま!」
からのが堰を切ったような勢いで鐘楼へと駈けのぼった。登り切った時、アーネストは右膝を床につき、左手で身体を支えつつ切れ切れの息をしていた。からのは顔面蒼白になりながら、アーネストを抱き起こした。
「……からの?」 アーネストは掠れた辛うじて聞き取れるような声で言った。
「こんな事されてもうれしくなんかない! だって、だって」
「――これで、外の世界に出られるよ。自由にどこへだって行ける……」
からのは両手で口元を押さえた。涙がその双眸から再びボロボロとこぼれ落ちた。
「外に行ってもアーネストさまがいないもの」
「いい……迷惑だったか?」消え入りそうな、けれど、温かな口調だった。
「そんな事ない。でも、わたし、わたし、本当にアーネストさまの事が……」
「大丈夫、きっと、キミは一人で歩いていける……」
アーネストは言う。からのはアーネストの瞳を見詰めて首を横に振った。一人ではどこへも行く自信はない。けれど、外の世界に道が開けたなら……。温かい風が吹く。ここでは心地よいそよ風も、さらわれるような強風になってしまうかもしれない。
「さよならは……言わないよ……。いつかどこかでまた会える……。頼んだよ、キミは……生きている時間に戻るんだ。俺を――」
「アーネストさま! ……。……」
アーネストは息絶えた。からのの腕に抱かれ、満足そうな微笑みを浮かべて。
からのは哀しみに暮れた。アーネストが自分にこんなに好意を持ってるとは知らなかった。それは薄々勘づいてはいたけれど、命を賭けてくれるほどだとは思っていなかった。外の世界をもっと知りたいと熱望していた自分のために戦ってくれた――?
からのは哀しみを押し殺しつつ、アーネストを鐘楼から降ろした。屋敷はアーネストが鐘を鳴らしたことですっかり、“現実”を取り戻していた。けれど、切り出されたのはからのとアーネストの二人きりのよう。二人は現実に、ヴェイロンと召使いさんたちの住まう不思議な場所は今もあのままなのだろうか。からのはたった一人きりで墓穴を掘り、アーネストを埋葬した。
「……迷惑だって……言ったのに。アーネストさまの思いがやっと判ったのに。あなたはもういない……。外の世界を……あんなに“見せて”くれたのに……。――あなたがいないなら、世界をみても……色褪せてしまう――」
でも、そうまでしてアーネストが見せたいといった世界、黒き湖の近くにあるという丘。行ってみたい。そして、そうしなければ、アーネストの思いに応えることは出来ない。
「これをわたしだと思って、待っていてください……」
からのはポケットに忍ばせていた植物の種をそっと埋めた。アーネストが淋しくないように。屋敷に広がる淋しげな草むらが緑豊かな森になりますように。木々に鳥や動物たちが集いますように。
「――アーネストさま、――わたし……行ってみます……。あなたが見せたかった世界へ……」
*
やがて、種は芽吹き、可愛らしい双葉が姿を現した。それは立派に育ち、エルフの平原がエルフの森へと姿を変えていく礎となった。一本の木が育ち始めると、遠くから舞ってきた種子も類が友を呼ぶように集まりだし、ブッシュが育つ。少しずつ、少しずつ、ゆっくりとゆっくりと。ただの木の集団は星霜の時を経て、エルフの平原を呑み込むような森に成長した。
アーネストとからのの思いを宿した木は森の要となり、森を支えた。
時は満ちる。からのが世界を巡りこの森で没して数百年後、小さな小さなフォレストグリーンの精霊核が生を受けた。この森の記憶を持ち、記憶が結晶化した命。やがて、その精霊核はドライアードを産み落とす。その名は……。

文:篠原くれん 挿絵:晴嵐改 タイトルイラスト:ぽに犬
