12. the truth to rage(暴れる真相)
「わたしとともにここから外に出ましょう」
その優しい声色はどこかで聞いたことがあるような気がした。切れ切れの意識の向こうで、何度も呼びかけられて、闇の向こう側に転がり落ちていきそうになるのを救われていた気さえする。暗く、湿気った地下牢に射し込んだ一筋の光のようだった。
「……あなたと一緒に、外に出る……?」
たどたどしい言葉でジェットは答えた。顔を上げ、明るい扉の向こうから現れたシルエットを眺めた。そう、“彼”の名前も一度は聞いた。幸せを運ぶ何か草花の名前とダブって記憶の淵に留まっていたような、そうでないような淡い記憶。
「――。あなたは……、クローバー!」
「そうです。さあ、早く。ヘクトラが帰ってくる前にここを出ましょう」
クローバーは地下牢の奥に入り込んで、まだうずくまったままのジェットの手を取った。ヘクトラが期成同盟に掛かり切りになっている今しかチャンスはない。怪しげな呪法を発動される前にその影響範囲から離れてしまうのがベストなのだ。
「……ヘクトラ……って、誰……ですか……?」
どこか虚ろにジェットの声は地下牢に響き渡った。
*
「で、どうするよ?」迷夢はアズロ・ジュニアにつっかるように言い放った。
「そうですね」対するアズロも迷夢の相手には大分なれた様子で平静そうに受け答えをするようになっていた。「現状、手筈通りに動き出しましたから、迷夢さんに教皇猊下をアイネスタまでお連れしていただく番でしょうかね?」
迷夢のほぼ予想通りの答えが返ってきた。実際、迷夢はそれを望んでいた。とかく、頼りなくて、探りを入れてくるイメージの受け答えが嫌で嫌で堪らなかったのだ。自由に自在に思いのままにやって欲しい。迷夢自信の思い通りにはならないと多少癪に障るのだが、それも国が生まれるのなら仕方がないと割り切れる。
「大分、言いたいことを言ってくれるようになったじゃなぁ〜い?」
「それは迷夢さんを師匠に持てば皆さん、そのようになると思います」
「あら?」わざとらしく驚いて見せる。「ステキな物言いだこと。ま、いいわ。教皇猊下さまはわたしがしっかりとアイネスタまで連れていってあげる」
「では、わたしもそろそろ出発するとしましょうか」
アズロは言う。ウィズとサムの率いる部隊を先発させ、こちらは途中で王位継承者を擁する一行と合流させる。一方、アズロはトリリアン・ガーディアンに対する陽動を狙っていた。期成同盟軍が動いたことは当然、トリリアンの知るところになる。統制の取れていないガーディアンと言えど、自らの存亡がかかっている時くらいは驚異の統率をみせるだろう。ガーディアン全軍が同盟軍を標的としたら勝ち目はない。
「――ところで、ガーディアン相手の陽動作戦。キミ、一人で大丈夫かしら?」
「大丈夫ではないと思います。しかし、期成同盟は人手不足ですし、陽動のための部隊を配置する余裕なんてありません。それは迷夢さんもご存じかとは思います」
アズロは机の上で手を組んでマジマジと迷夢を見つめていた。
「それはご存知ね。けど、わたしが言いたいのはそうじゃなくて、よ? “キミ、一人で”大丈夫なのかってこと。アイネスタに集まるだろうガーディアンの人員は相当数だろうし、その一部の気を逸らせるといっても簡単じゃない。ま、先発にはウィズ、サム、特に久須那がいるから問題はないはずだけど、アズロくんは大丈夫なのかなって?」
迷夢は腕を組んで、半ば詰め寄るかのようなきつめの口調で言った。
「そんなに頼りなさそうに見えますか……?」
「うん♪」嬉々として迷夢は答えた。「わたしはキミの本気を一度も見たことがない。きっと、ウィズやサムにだってみせたことはないんでしょ? そして、期成同盟の誰にもね。けど、キミはそこに座って采配を振るだけの男ではないんでしょう?」
意味深な響きを乗せて迷夢は微笑んだ。エスメラルダ期成同盟盟主・アズロ・ジュニア。実際、迷夢が期成同盟に顔を出すようになってからも、アズロが本領を発揮したところや、その片鱗をたったの一度さえも見たことがない。確かに頭脳面で活躍することは当たり前だったが、実動に関して完全に未知の世界なのがアズロという男だった。
「……そうね。まず、キミは魔法使いなのかしら……?」
「……。いい勘をしていますね。流石は迷夢さんです。……では、こんなのはいかがでしょうか。これを見たら安心していただけると思いますよ?」
アズロは迷夢の目の前に手のひらをスッと差し出した。それからアズロは目を閉じて、口の中で呪文のような何事かを短く唱えた。すると、何も存在していなかった手のひらの上に氷の塊が一つでき上がっていた。それ自体は何の変哲もない氷の塊だったが、とても高度な魔法だった。実際、素人が遊び気分で出来る程度を遥かに越えていて、氷で造形をするのならフラウやフェンリルを師に持たなければ不可能な所業だと言われている。
「アイスメイクかぁ。――知り合いにフェンリルでもいるのかしら?」
「正確にはいまし“た”ですね。氷の魔法に適性を持つものは非常に珍しいとか何とか言われて、散々基礎から応用まで叩き込まれましたよ」
「それを何故、ずっと黙っていたのかしら?」
「秘密兵器ですから」にこやかに微笑みながらアズロは臆することなく言った。「まぁ、冗談はそのくらいにしておきますが、ただ単に語る時間も理由もなかっただけですよ。それでは納得できないようですね」
「そりゃそうでしょ。氷を自在に操れる人材がいたら、かなりの戦力アップよ」
「わたしを頼りにしすぎて欲しくなかったものですから……。それはそれとして、迷夢さんはわたしが魔法を使えることをご存知なかったワケはないと思うのですが……?」
いつもやられている借りを返さんとばかりにアズロは迷夢に言葉の攻撃を仕掛けた。
「まー、察しはついていたけど、敢えて指摘はしなかった、と言うべきかしら?」
迷夢はアズロの方を向くことなく、ヘラヘラとした様子で言った。
「まあ、キミがいるなら、陽動作戦の方はデュレを連れて行けばより安心といえそうな感じ。……じゃあ、わたしにはもう一つの核心を探しに行く余裕がありそうよねぇえ?」
「――もう一つの核心とは何でしょうかね?」
「……そうね、キミにだけ教えてあげる。――秘教・ドラゴンズティースとトリリアンの関係――。無関係かもしれないけれど、つながりを示唆する情報を手に入れたのよね。その確認が取れたら、国取り合戦以上に面白いことが起きるかもしれなくてよ?」
迷夢は口元を歪ませて、確信的ななお且つ意味深な笑みを浮かべていた。
「国取り合戦以上に面白いこと。ですか?」
「そ。面白いこと」にんまり。「けど、まあ、キミはまだ知らなくていいかも?」
迷夢は悪戯な、けれど同時に意地悪な笑みを浮かべた。
「そんな連れないことを言わないで、わたしにも教えてくださいよ」
「んふ。じゃ、教えてあげよっかなぁ〜。――ベリアル、もう入ってもいいわよ?」
迷夢はくるっと振り返ってツカツカと戸口まで向かうと、おもむろにドアを開いた。ドアの陰にはすっかり退屈してしまって空を見上げているベリアルがいた。もし、万が一にでもトリリアンの関係者に発見されるとあとで面倒なのだが、今更、大して気にするつもりもなくなっていた。
「あれ? ベリアル〜〜、どうかしちゃったのかしら?」
迷夢はひょいとベリアルの顔を下から覗き込んだ。
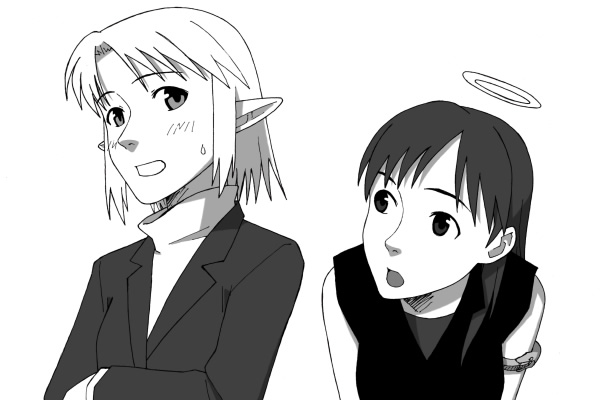
「え? いえっ、大丈夫です。問題はありませんよ」ベリアルは慌てて取り乱した。
普段は気を張っているとはいえ、僅かな緩みを突かれたら、驚くと言うものだ。
「さてと。まーそんなことはどうだっていいわ。さっさと、こっちに来なさい」
ベリアルは迷夢に言われるがままに中に入った。そして、期成同盟の盟主・アズロを初めて見た。確かに、迷夢と出会って、期成同盟とその盟主、活動内容の概要は聞いたものだ。が、流石にその人となり容貌までは知り得ない。
「初めまして。紹介にあずかりましたベリアルです」
「……この場に迷夢さんの紹介で来たということはあなたはわたしたちに手を貸していただけると理解してもよろしいのですね」
アズロは机上で手を組んで、ベリアルに真摯で、どこか冷たい視線を投げ掛けた。
「そのように受け止めていただいて構いません」
「かたいわねぇ。いつも思うけど、もっと人当たり良くないともてないわよ?」
「無理にもてたいとは思いませんよ。そもそもここでもててどうするんですか?」
「どうもしないわよ、別に」キョトとして迷夢は答える。
そう言えば迷夢とはこんなヤツだった。真面目に真に受けていたら、自分が疲れるだけ。適当に相手をしてテキトーに答えておけば迷夢は満足だなのだ。
「それよりも、迷夢さん? ベリアルさんを紹介いただいたのはよいのですが、その方とドラゴンズティースとの関係はどこにあるのですか?」
「ベリアル。その辺りのことを説明してあげてちょうだい」
「わたしとドラゴンズティースとの間には直接の関係はありませんが、長年トリリアンに居る間に蓄積した情報を元にすると少し面白いことが判ったということに過ぎません」
ベリアルは少々興奮気味の迷夢とは裏腹に淡々と語る。
「なるほど、それで?」アズロも少しばかりの興味を持ってベリアルを促す。
「いくつかの内部資料を検証しまとめると、協会から除名されたアリクシアは一時期、協会内で形成された“アリクシア派”をもとにしてトリリアンを設立。……ここまでは皆さんはご存知かと思います。その十数年後、アリクシアはトリリアンを見限っています」
「見限った?」ピクリとアズロの眉が動いた。
「そう、見限られちゃったみたいなのよねぇえ、トリリアン」
「トリリアンに残っているだけの資料ではそこまでしか手掛かりはなかったのですが、つい最近になって興味深い事実が明らかになりました。……秘教・ドラゴンズティースが極最近まで活動していたこと。そして、その――」
ベリアルはこの先を喋ってもいいのかと目で伺った。そして、迷夢は頷く。
「その生き残りが身近にいるのです」
「そこからその存在が疑問視されていたドラゴンズティースが存在していたことと活動拠点だった場所までが明らかになったワケよ。で、ベリアルが暇に任せて調べて持ったら、判っちゃったのよねぇ、アリクシアがドラゴンズティースと関わっていたことが」
「暇は余計です、迷夢さん」
「まぁ、細かいことは言わない」手をヒラヒラ。「ともかく、そこから芋づるのように色々と出てきたのよねぇ〜〜。その確認はこれからとってくるんだけどさ」
「なるほど……、それは確かに迷夢さんには面白いかもしれませんね……」
「そゆこと。じゃ、あたしはちょっと出掛けてくるから、あとは二人でお願いね」
迷夢はそう言うと二人を残して、さっさと出掛けていった。
*
トリリアンとエスメラルダ期成同盟のリテールでの存在をかけた戦いが始まる。そして、それはリテール史に残る戦になろうことは誰しもが予想していた。エスメラルダが国としての復興を望むのならば、トリリアンがリテール全体へと影響力を増して協会を放逐したいと望むのならば、避けることは出来ない二つの勢力の争いなのだ。
その頃、期成同盟軍はかつてのエスメラルダ王都・アイネスタに向けて進軍を開始、二日後にはエスメラルダの正当な王位継承者と合流する予定になっており、近いうちにリテール協会教皇の名の元に国王の戴冠式を行い、エスメラルダ王国の復活を宣言する手筈になっていた。
そう言った重要な役割を担った軍を率いるのはウィズとサム。かつての“十二の精霊核の伝説”に終止符を打ったある意味でヒーローだった。とは言うものの、成りゆきで巻き込まれた形の二人にはそのような自覚はあまりないようだった。
「どう思う、ウィズ」サムは唐突に、問いを投げ掛けた。
「何に対して、どう思えばいいんですか?」ウィズは返す。
「ああ、トリリアンの野望……ではなくて、天使召喚術について……だな」
何をまた唐突に質問してくるのか、少々不可解だった。天使召喚術はとうの昔に使う術者のいなくなった魔法で、最後に行使されてから二百年以上も過ぎ去った所謂、エンシェントスペルなのだ。トリリアンの野望については何かしらの意見があるが、天使召喚術については意見など欠けらも思いつかない。
「天使召喚術がどうしたって言うんですか?」
「うん、あぁ……」サムはしばらく黙り込んだ。そして……。「天使召喚術があったから久須那や迷夢、トリリアンの黒翼の天使がいる訳だよな……。異界ってどんな場所なんだろうな。天使も故郷に帰りたいと思うものなんだろうか……」
「何を急に感傷的になっているんだ?」
空から久須那の声が舞い降りてきた。ちょうど、ウィズとサムの真上にいた時に二人のやり取りがフと耳に届いた。それが少し気になってふらりと降りてきたのだ。
「てめぇはよ、異界に帰りてぇと思ったことはないのか?」
「ない……と言えば、やはり、ウソになるのだろうな。昔はよく異界に帰りたいと思ったものだよ。サム、お前と会うまでは……ね?」それ以上喋るとおのろけになると思ったのか久須那はそこで口を閉じた。「今はこのリテールが故郷みたいなもの。どこか遠くへ……なんて考えたことはない」
「そうか……」言葉少なにサムは答える。
そのちょっとしたやり取りを聞くウィズはトリリアンに所属する黒い翼の天使に思いを馳せていた。ウィズの知っている限りではその天使は幼少の頃にトリリアンの第五代総長・ソノアの時代に異界から召喚されたらしい。召喚の理由は古の魔法の研究といった比較的崇高なものでもなく、ある意味で純粋にトリリアン自らの権力の増大。かつてのリテール協会が行った天使の召喚による軍事力の拡大と、それによってリテールの覇権を手に入れることだったのだという。しかし、その目論みは失敗。結局、召喚した天使の力を上手に制御することも、それ以上に天使を召喚することも出来なかった。
以降、トリリアンは闇の時代を迎える。
「……天使召喚術……か……。それが諸悪の根源だな……」ウィズは呟く。
「否定はしないな。だが、諸悪の根源ではなく悲劇の始まりと称して欲しい。天使召喚術がなければ、このようなことは起きなかったとも言えるが、わたしや迷夢もこのリテールにいなかったからな。――難しいところだと思うぞ」
「久須那さんや迷夢さんは良識があるからいいですけど……」
「――良識、ねぇ」サムはひっそりと突っ込みを入れた。「まぁ、ウィズがどう思おうが勝手だが、そろそろ無駄口を叩いている場合じゃねぇぞ? トリリアンのガーディアンはアズロと迷夢が揺動する手筈にはなっているが、正直なところ、多勢に無勢。どこまで足止めできるか不確定な要素が大き過ぎる」
「そうだな。ひとまずは王位継承者との合流地点へ急ぎ、アイネスタへ」
「王子を抱えた状態でのガーディアンとの戦闘はきつい。こっちの有利に運ぶには先にアイネスタに到着し、準備を整えておく必要があるってこと」
エスメラルダ期成同盟軍はサムとウィズを筆頭に一路、アイネスタを目指す。
*
エスメラルダ期成同盟・テレネンセス臨時司令部でのベリアルのアズロへの紹介を終えた迷夢は一つの懸念材料の解決に向けて、奔走していた。トリリアンの創始者にして、ドラゴンズティースの開祖・アリクシアの生存情報をある消息筋から入手した。
当初、ベリアルから仕入れた情報はあくまでドラゴンズティースとアリクシアの関係性だけだったのだが、多方面から紛れ込んだ資料の中にアリクシアの名が記されたものが散見された。無論、迷夢もトリリアン総長・ヘクトラの妹にアリクシアがいたことは知っているが、彼女は既に故人となっていたし、ヘクトラと同列に語れることが多かった。そして、迷夢が確認した資料はヘクトラの妹のアリクシアとは無関係なところまで突き止めた。
と、したら……。
「……この話が本当だったら、やっぱ、何かに利用できるわよねぇえ?」
詰まる所、迷夢の目的とはそこなのだ。結局はガセネタだったと言う可能性も捨て切れないが、アリクシアが存命であれば、現在のトリリアンに大きな波紋を投げ掛けられる。そうしたら、万が一の確率ででも、トリリアンを崩せるかもしれない。
ただ、それが成功する条件には総長・ヘクトラの考えに異を唱え、疑問を抱き、初代総長・アリクシアの思想になびいてくれる必要がある。
「――そんなに都合よくはいかないか……」
しかし、都合よくいってくれたほうが、実力行使が避けられる分だけリスクは分散する。が、これに問題点がないわけではない。アリクシアがどれだけの人望と影響力を持っているかが判らないが故に、しくじるとアリクシアを中心とした第四の勢力が立ち上がって事態に更なる混沌をもたらすかもしれないのだ。
「……ま……、深く考えるのはやめておこうかしら……」
辿り着いた先はアリクシアの生まれ故郷・クアラパート。今でこそ何もないが、トリリアンが産声を上げたのもこの街だった。ここが現在までにつながる禍根が生まれたある意味、始まりの街なのかもしれない。
「――ここまで、何もないところってのも珍しいわよねぇえ、やっぱり」
迷夢は周囲によく通る声で独り言を言うと、クアラパートの街のとある施設を探し始めた。それは教会。迷夢が調べた限りではここの教会にはエルフの老司祭がいるはずなのだ。彼の年齢を考えれば、アリクシアがこの街でトリリアンの設立を見守っていたはず。その予測が正しければ、アリクシアを知る機会でもある。
「因縁の街よね。――アリクシアとトリリアンの生まれた街」
複雑な表情をたたえながら、迷夢は異常なほど静かなメインストリートを歩いた。よそ者に警戒しているというよりはむしろ、始めからヒトなど住んでいないかのようだ。遥か昔から寒村だとは聞いていたが、迷夢の想像を遥かに越える。
「ふ〜ん。どんなに元気でいても気が滅入ってくるわねぇ。ここ」
と、のべつ幕無しに不平やら不満やらをぶちまけながら歩いていくと、教会レルシア派の十字架を掲げた教会の前にいた。迷夢は鋭い眼差しで品定めをするかのように教会の全景を確認すると、礼拝堂に続くだろう扉を開いて、堂々と進入した。
ヒトがいるなら向こうから先に気が付くはずだ。そして……。
「――この老いぼれにご用があるのはどなたかな?」
幾分、前時代がかったセリフとともに姿を現したのは齢を重ねたエルフだった。
「……老いぼれというほどの老いぼれでもないでしょうに……」
迷夢は凍てつくような冷たい視線と同時に、突き刺さるような言葉を発した。こう言った掴み所のない人物を相手にするの厄介だ。幾ら迷夢本人が掴み所のないヒトだからといって、飄々としたヒトの扱いになれている訳でもない。実際、同類になるほど考えが読まれる傾向にあり、対応に詰まりやすい。
「まあ、細かいことはどうでもいいわ。ちょっと聞きたいんだけどさぁあ? ここ、クアラパートで協会のアリクシア派が組織されて、のちのトリリアンになるのよねぇえ? キミは……その歴史をその目で見ていたのかしら」
自明のようなことを、迷夢は敢えて問い掛ける。
「……確かにそのようなこともございましたねぇ……」
エルフの老司祭は祭壇に掲げられた協会十字を慈しみを持った眼差しで見上げた。
「アリクシアさまと、マリエルさまと、ラナさまと……。まるで、昨日のことのように覚えております。……あの方々が居られなかったら、協会はどのような道を辿ったことでしょう。レルシア派はこのように存在していたのでしょうか?」
「そんなこと、あたしが知る訳ないでしょう。そもそも、あたしはその“もしも”ってのが嫌いなのよ。もう、起きちゃったし、こうなっちゃったんだから、クロニアスでも抱き込まなければ、どうにもならないのよ、基本的に。ま、あのわからず屋のとんとんちきはどうごねたって何もしてくれないでしょうけど」
「……そうですね。過ぎた時にもしもはない」
老司祭のもっさりとした口調に迷夢は苛立ちを覚えた。迷夢が感じるにはワザとなのだ。彼の目を見れば判る。半分、惚けたふりをしつつ、迷夢を試しているのに違いない。
「――ズバリ聞くわよ。アリクシアは生きているのね?」
迷夢は腕を組んだまま、険しい眼差しを老司祭に投げ掛けていた。
「いきなり、大それたことをお尋ねになられるのですね?」
「回りくどいのは嫌いなのよ。生きてるなら生きてる。死んでるなら死んでる。知らないなら知らないって、ズバリを答えて欲しいのよねぇえ?」
「左様ですか……。――ご存命でございます」
老司祭は隠し立てすることもなくあっさりと答えた。
「そう、やっぱりね。じゃあ、もう一つ聞くわ。アリクシアをどこに隠したの?」
老司祭に向けて迷夢は歩き出した。
「……。幾ら、あなたさまでもそこまではお教えできません。どうしてもと仰るのならば、ご自分の力で見つけ出してくださいませ」
「ま。そう言うだろうとは思ってたけどね……。じゃ、勝手に捜すとしますか……」
迷夢は踵を返して戸口へと向かった。と、不意に立ち止まり老司祭を見やった。
「――戴冠式には連れて来るわよ? だから、そのつもりで」
老司祭は目を閉じて、静かに頷いた。無下にはしたものの、迷夢がアリクシアのことを話題にしたということは目星はつけているのだろう。恐らく、迷夢は数日後、アリクシアを連れてアイネスタ教会の祭壇に立っていることだろう。
「ええ、構いませんよ」
ただ微笑みだけを湛えて老司祭はいう。それがまた気に入らなくて、迷夢は「そう」とだけ短く答えて、教会を飛び出していた。老司祭は迷夢が視界から消えるのを待って、ゆっくりと祭壇に向かって歩き出した。
「とうとう、この時が来てしまいましたよ、アリクシア。――いつか再び、あなたを呼び戻すこともあるとは思っていました……。……しかし、これほど早いとは……」
老司祭は特に何をするのでもなく、そのまま礼拝堂の奥に消えた。
*
それはまるで、恋する二人の駆け落ちのようだった。許されざる恋。お金持ちのお嬢様と庶民の男。どこまでも追ってくるお嬢様の衛兵と、どこまでも追っ手を振り切るために逃走する恋する二人。お金持ちのお嬢様は黒き翼のジェット。庶民の男はトリリアンの未来を見失った参謀、クローバー。そして、お嬢様の奪還をたまわったのは……。
「――手を放せ……」
ジェットの裏側に隠されたもう一人のジェット。
「キミは魔法で操られているんです。それから解放するまでわたしから離れないで」
微かな違和感を感じながらもクローバーは答えた。交流も深くない男に急に連れ出されて気が動転しているのに違いなく、魔法の呪縛が解けたら元に戻るに違いない。実際、クローバーはヘクトラのかけた呪法がどのようなものかまでは把握し切っていなかった。
「わたしは誰にも操られてなどいない。わたしはわたしの意志で行動している」
「いいえ。ジェット、キミは騙されています。ヘクトラの言いなりはいけません」
「ヘクトラ……。あぁ……マスターのこと……。わたしは彼の言いなりに動いているのではない。彼の言動をもとにわたしの都合のいいように行動しているだけ。彼がどういう志を抱いていようとも関係はない。わたしはわたしの思うがままに」
ジェットはギロリと激しく険しい眼差しでクローバーを睨み付けた。
文:篠原くれん 挿絵・タイトルイラスト:晴嵐改
