02. let's go finding!(探しに行こうぜっ)
「じゃ、シルト、今日、行ったところを出来るだけ詳しく思い出して辿ってみてくれる?」
「……今日、行ったところぉ?」
シルトは小首を傾げながら、酷く自信なさげな面持ちで記憶の糸を手繰っているようだった。そもそも、家を飛び出して遊びに出たらどこに行ったかなんて覚えていない。遊ぶことのみに集中して他のことなど眼中にないのだ。
それでも、シルトは頑張って、立ち寄った場所を思い起こそうと必死になった。どこで遊んでたかが判らないと、肝心のアミュレットの探しようがないことはシルトにも痛いほどよく判る。しかも、それが自分の存在に関わることとなれば否応なしに気合いも入ると言うものだ。
「……まだ?」しびれを切らして、セレスが言った。
「うんとぉ、付いてきて」ひとしきり考えるとシルトは走り出した。
「あのさ、どこ行くんよ?」
「わたしに聞かないで、シルトに言って、早く早く」
余所見をした隙にシルトは屋外へと姿を消していた。慌ててデュレとセレスは外に飛び出す。
「右? 左?」デュレは見回す。
「いたっ! 左」叫ぶのと同時にセレスは指さした。「もお、あんなところ走ってるよ」
と、シルトが急に困ったように急停止したのが見えた。場所は十字路、交差点。キョロキョロと首を左右に振って、見覚えのある道を探しているようだった。
「早くっ! 今のうちに距離を縮めないと一気に引き離されますよ」かなり真剣にデュレが言う。
「了解!」返事よろしく、セレスはシルトの姿を追って駆け出した。
「返事だけはいいんだけどなぁ。どうして、こう、他はさっぱりなのかしら」
ため息。そして、デュレはちょっと遅れてセレスの背中を追い出した。
「……あの娘って、すばしっこいよねぇ」
セレスとデュレはようやくシルトの背中を捉えられた。走りながら、キョロキョロしてるおかげで全速力はでていないらしい。それが功を奏してなのか、デュレとセレスは辛うじて、シルトを追跡している状況だった。
「それにしても、シルト。あたしたちが付いてきてること判ってるのかな?」
「どんなものでしょう? 一つのことに集中すると他が吹っ飛ぶのはセレスと一緒ですから」
「済みませんね。ど〜せあたしゃあ単細胞です。一度に一コのことしか出来ないんだも〜ん」
セレスは頭の後ろで手を組んで、つんと唇を尖らせた。
と、全くの不意にシルトは路地裏に入った。デュレとセレスは急停止することも出来ずに、通り過ぎてしまった。
「セレス、違いますっ。そっち、そっち!」一緒に通り過ぎた自分を棚に上げ、セレスに言う。
「判ってるって」セレスは目を細め何言ってるんだかと言いたげな恨めしげな表情でデュレを見詰め、シルトが曲がった路地に戻った。
「うわっ、まさか、こんな狭苦しいところを行くの?」
セレスはそのまま絶句した。狭いところは嫌い。ついでに真っ暗なところも好きじゃない。見詰めた路地は暗くはないけど、薄暗くてセレスの気を滅入らせて、行動不能にするにも十分だ。
「行くしかないでしょうね。シルトが行ったんだから、通り抜けれるってことでしょう?」
「そりゃ、判らないよ。あの娘だったら道なき道にだって平気で突っ込んでいきそうだし」
「……否定しきれないところが恐ろしいです」
デュレは自分自身を抱きしめて思わず身震いした。
「あ〜……。行くかい、シルトのアミュレット、見付からなかったら困るしさ……。見失ったら手遅れになりそうだし。よっしゃ、行くぜ」セレスは気合いを入れ直して、路地に突っ込んだ。
セレスとデュレの思いをよそにシルトは駆ける。入り組んだ路地。そこはテレネンセス新市街でも特に迷宮とまで呼ばれるまでに複雑怪奇な場所なのだ。迷宮素人が水先案内人なしに訪れると、半日は出てこれないと言うのは有名な話だ。
「うへっ! シルトってさあ、こんなところで一日何やってるのさ?」
ありとあらゆる障害物を何とか避けながら何とかシルトの姿に追いすがる。
「セレス、頭っ!」
「頭ぁ?」
バキッ! 大きな音と共にセレスは店先の吊り看板に顔面を強打した。
「うくくく……」顔を押さえてうずくまる。「何でこんなに低いとこにあるの!」
「知りません、そんなこと。ほらほら、いつまでもうずくまってないで、行きますよ」
「あ〜もう、ヤメヤメ。あたし、リタイヤ、帰る!」セレスは顔を押さえたまま首を左右に振った。
「はぁ?」デュレはため息をついて左手で額を押さえた。「何、子どもみたいなこと言ってるんですか。おばさんの癖して……」
「誰がおばさんだいっ。こんなピチピチギャルを掴まえて」
「シルトは……って、あっ! 見失っちゃう」
「こらっ! 人の話は最後まで聞け」セレスは仕方がなく、デュレの背中を追い掛ける。
シルトは狭い路地を巧みに駆ける。地面に転がった段ボール箱、空き瓶、ゴミ箱を避けていく。実に手慣れて、動きに無駄がない。シルトは確実にこの路地裏を何度も駆け抜けてきたのに違いない。一方のデュレとセレスはシルトがひょいひょいと楽々かわしていく障害物に足を取られて先に進むのは楽ではない。シルトの背中を見失わないよう注意しながら、足下を注目……するのはなかなか辛い。ちょっとでもよそ見をしているとシルトはどこかに行ってしまいそうだし、かといって足元を見ないと植木鉢に蹴躓く。
「身軽よねぇ、シルトって」感心したように言った。
「だから、セレス、気を抜かないっ!」と、デュレは急停止した。
「は? 何?」
「――ドアが開きます」物凄く冷静な声色でデュレは言った。
ドバンっ! 看板に当たった時よりもさらに激しくセレスはドアに体当たりを喰わされた。
「くぅぅううぅ……」言葉にならない悲鳴を漏らし、セレスは地面に崩れ落ちた。
「あら、ごめんなさいね」ドアの向こうから、小太りの女性が現れた。
「あぁ、気にしなくてもよろしいですから……」
デュレはセレスを助け起こそうとしながら、軽く会釈をかわした。
「ほら、セレス。立ちなさい。歩けないほどじゃないでしょう?」
「ダメ……。あたし、全身打撲で再起不能……。動けませぇん……」
「何言ってるんですか。行きますよ」デュレは動く気配さえみせないセレスの腕を引っ張った。
「あぁ、わぁった、判ったから。腕がちぎれるっ!」
「そう、早くね」セレスが起きると判った瞬間、デュレはセレスの腕を放した。瞬間、セレスは支えを失って、後ろに倒れ込んだ。
「こぉの、ちくしょうめ!」
セレスはさっきのだらけぶりはどこへやら、瞬間で覇気を取り戻すとやる気全開モードでデュレを追撃。ここまで無下に扱われては黙っていられないと言うものだ。シルトのことはもはやそっちのけ。目標はデュレの背中。デュレだろうとシルトだろうと探し物は同じなんだから、どっちを追い掛けようと構わない。そうなれば、セレスは百人力で眼をランランとさせて、目的を果たす。
そして、ふと気が付けば、かなり町外れまで来ていた。路地という路地を駆け抜けると、デュレとセレスの家からほど近いメインストリートとは反対側に出たようだ。
「しかし……、どこじゃここ?」
セレスは額に手をかざし見慣れない風景にとまどいは隠せない。けど、デュレは来たことがあるようだった。その場所はテレネンセス中心街から、数キロ離れた場所にある森林公園の近くだった。シルトは森林公園に用事があるのではなくて、その外れにある子供たちの遊び場スポット。大人たちは危険だからと子供たちに近寄ることさえ許さない場所を目指す。
「う……っ。地下水道……」
デュレは土管が大きく口を開ける地下水道に消えていくシルトの後ろ姿を目で追い掛けたまま、入口で固まった。仄かに変な臭いがして奥へ進むことがはばかられる。自分自身がまだ子供だというなら、いざ知らず。流石にこれは冗談ではない。
「――けど、仕方がないですか……」
デュレは肩を落として大きなため息をついた。入って出てきたら、靴や靴下はべちゃべちゃに濡れているだろうし、丸一日は身体から臭いが抜けなさそうな気がする。サイテーな気分だ。デュレは意を決して中に入った。が、入口から遠く離れるに連れ視界が暗闇に閉ざされる。この中をどうやって、シルトがかけていったのか不思議になるくらいに。確かに、シルトは闇の精霊でフツーの人間やエルフよりも夜目は利くだろうが、それにしても不思議な気持ちになってしまう。遙か遠くになった入口の光点以外に光源は存在しないのだから。
「ライトニングスペル」
デュレは手をかざし、地下水道の奥に向かって小さな光の球を浮かばせた。本来なら、それは攻撃系の魔法に属するのだが、使い方に気を付け丸めてやるとちょうどいい照明になる。プラス“フォローイング”をかけてやれば目標にした物体を追い掛けてフヨフヨとそこはかとなく頼りなげな雰囲気を漂わせながら移動していく。
「うわぁ〜、こりゃ、流石に気も滅入るってもんよねぇ」背後からセレスの声が届く。
「……あら? セレス。リタイヤしたんじゃなかったんですか?」
「ホントはそうしたかったけど、シルトの居ない生活も味気ないかなって」
「つまり、セレスと同レベルのおコちゃま遊び相手が居ないと詰まらないって事ですね?」
「な、何でそう言うかなぁ」セレスは手を合わせてもじもじしながら、心外そうに言った。「あたしはただ、あんな瓦礫の街に戻らなきゃならないなんて、可哀想だなって」
「判ってますよ。けど、半分はホントでしょ?」
「ま、ね」セレスは二ヒヒと笑って頭の後ろで腕を組んだ。「あの娘と居ると退屈しなくて。面白くて楽しいでしょ? デュレといて息苦しくなったら、ちょうどいい、息抜きにね」
「何ですって?」デュレは半ば本気にセレスを睨め付けた。
「あははっ! 冗談だって、本気にしないでよ」
セレスはいつものようにデュレの背中をバシバシと引っぱたいた。
「冗談にも思えないんですけど? その言葉」
デュレは横目でジロジロとセレスの顔を眺め回す。セレスはあははとばかりにお気楽さを炸裂させていたものの、背中にはちょっぴり冷や汗を感じていた。ここは対処を誤ると、後々に地獄を見る羽目に陥るのは自明の理。慎重に言葉を選んで……。
「ねぇ、シルトってどうしてあんなに元気いっぱい弾けちゃってるお転婆娘なの?」
「セレスに似たんでしょ? 元祖、弾けちゃってる開き直り娘さん?」
「それは嫌味かってんだい?」
「その通りです。嫌味以外に一体、何があるって言うんですか?」
「……何もあるわけないよね。ど〜せ、デュレだし」
「どうせ、わたしですから。それに元からの性格ってのもあるんでしょうけど、近くにいる人の影響も受けるのよ。シルトはまだまだお子さまだから、特にその傾向が強くなるのよ」
「だったら、デュレのその捻くれ几帳面の性格もうつっちゃうんじゃない?」
「余計なお世話さんです。わたしはセレスほど“濃く”ありませんから、大丈夫です」
「いや、十分濃いから……」セレスは手をやる気なさそうに振りながら、呆れて言った。
「何ですって?」目が三角。
「あうっ。ほら、あたしに注目しなくていいから、ねっ? 見失っちゃうよ」
「……もうすでに余裕で見失ってますから、気にしないでください」
「あ、あらら?」
セレスは意外そうに慌ててシルトを捜そうとしたけど、すでに影も形も見当たらない。しかし、遠くから水飛沫を跳ね上げる音が聞こえてくるから、地下水道を走ってるのは間違いない。
「――全力疾走で行きます。いいですか?」
真顔になってデュレは言う。本気でかからなければ追いつけない。二人は頷きあうと、豪快に飛沫が跳ね上がってかかるのも構わずに走り出した。けど、緩い流れの底にある石煉瓦は足が取られるのにちょうどいいくらいに滑り、所々にガラクタが転べと言わんばかりの悪意に満ちたように突きだしていた。それから、数百メートルも走っただろうか。
「あっ! いました」
デュレが声を上げ、指し示した方向にはマンホールの出口への梯子を登るシルトがいた。
「うう……。やっと見つけた……。シルト、すばしっこすぎ……、勘弁して欲しいわぁ」
「ごたごた言ってると置いて行かれますっ」
パシャ、パシャッと音を立て、デュレは梯子に掴まると登る。その頃にはシルトはフタを開けて外に飛び出していた。出口まであと十段。シルトの姿が視界に捉えられるうちに地下水道から外に出なければならい。デュレは可能な限り急ぐ。その下からはセレスがデュレを追う。
「ここは……」
外に出た瞬間、デュレは右左を見回した。場所がどこだか判らない。見覚えはあるようなないようなで、そもそも地下水道を数百メートルも移動したことがない。
「いたぁっ!」
後から出てきた、セレスはデュレとは反対側を向き、シルトを発見した。
「待てっ」セレスはやる気全開の全速力で走り、シルトの左腕を掴まえる。「ちょっと待て、キミはさ、もう少し、あたしたちのことを待ていられないのかい?」
「……」シルトはキョトとして小首を傾げ、不思議そうにセレスを覗いた。「だってだって、ずっとフツーに付いてきてくれてるって思ってた。そしたら……」
「あ〜、そうかぁ」セレスはちょっぴり困ったようにため息をついて、頭を掻いた。
と、セレスがシルトにどう言おうと頭を悩ませてるところにデュレが来た。場所を把握して一安心できたらしい。セレスがシルトを捕捉したのを確認できたので、離れすぎない程度に辺りを散策し、この辺りから見える有名なランドマークを見つけたのだ。
「何を困ってるんですか? セレス?」
「いや、別に大したことじゃないんだけど、勝手に先に行っちゃうの何とかならないかなって」
「あ。デュレ、ちょうどいいところで。この前の発掘調査の報告書が未提出なのだが……」
さらに、デュレの背後から白い翼を持った影が近づき、その肩に手をかけた。デュレは一瞬、飛び上がりそうになるくらいに驚き、ついでに背筋も凍りそうな思いがして叫びそうだった。
「く、久須那さん? ど、どうして、こんなところに……」振り返って、眼を白黒。
「どうしてと言われても、困るのだが……。わたしの家はこの近くだし。紅茶と夕食の買い出しに」
久須那は手にさげた買い物かごをちょっと持ち上げた。
「いや、それより、報告書だ」
「あの、それはもう少し、待って頂けませんか?」
「構わないが……。その様子で大丈夫なのか? 期日は……今日の五時までだぞ」
「い?」デュレは仰天して目を白黒。「今、何時ですか?」
「……。もうすぐ、三時半だな。多少の遅れは目を瞑るが、もし、提出が明日になろうものなら」
久須那は虚空からイグニスの弓を取り出して、凄味をきかせた。
「そ、そんなことは絶対にありませんから。ね? 久須那さんはのんびりと大好きな紅茶でも飲みながら教官室で待っていてください」
「ほ〜ぉ。久須那さん、今日はかなり本気だね。やっぱ、前の悪さが過ぎたのかな?」
「あれはセレスが邪魔をするから……!」
「ノンノン。あたしは関係ないでしょ? デュレが勝手に忘れたんだから」ニヒヒと笑う。
「誰のせいでも構わないんだが、期日は期日だぞ」
有無を言わさぬドスのきいた声色で久須那は言う。
「は、はい。判ってます……」
デュレは両手を前で組んで、すっかり縮こまってしまった。
「シルト。デュレは急に忙しくなったみたいだから、先に行ってよ?」
「う……うん」シルトは後ろ髪を引かれる思いなのか、名残惜しそうに何度も後ろを振り返る。
その思いを断ち切ると、シルトは再び走り出した。
「だぁかぁらぁ! どうしてキミはそう先走るのかな?」
セレスは左手で額を押さえて、魂も抜けてしまいそうなほどの大きなため息をつく。それから、肩からずり落ちた弓を改めてかけ直すとシルトを追う。今度は路地裏に紛れ込んだり、地下水道に入ったりはしないらしい。街のメインストリートをひたすら駆ける。
と、思っていたら、いきなり右に折れて建物に飛び込んだ。
「あ〜? 今度は一体何なのよぉ」愚痴も出るというものだ。「あれ?」
建物の前に立ち止まってよく見ると、その雰囲気には感じ覚え、見覚えがあった。戸口に下がる小さな控えめの看板には“月明かりと夜空”亭とかかれていた。
「……あたしは隠し事さえ出来ないのかい……」
セレスは肩を落として、シルトの後から店に入ろうとしたら、勢いよくシルトが飛び出てきてセレスと正面衝突をした。どうやら、目的のものは見付からなかったらしい。
「って、どうして、キミはあたしの行きつけの店まで知ってるの?」
「どうしてって。どうしてだろ?」シルトはキョトとした顔でセレスを見澄ました。
「……聞くだけ無駄か」ため息まじりに頭を掻いた。
「あっ! ちゃっきーどんに教えてもらったの」
「しょうっ! このおいらに隠せることは毛ほどもありはしねぇのだ。Are you understand?」
突如、ポテッとどこからともなくちゃっきーが降って湧いた。
「来たよ、お喋り大好きマシンガントーク炸裂野郎が」
「Yes, Sir! お喋り大好き口から生まれたトーキングマシン、不肖・ちゃっきーにござりまする。静寂に嫌気と淋しさを感じたのならば、呼ばれなくても大登場。ほほほ〜、このおいらがとどまるところの知らぬ愛のメッセージで孤独に荒んだあなたの淋しいココロをい暖めたあげるわぁ!」
「誰が荒んでるのよ」
「It's you! てめぇに他ならねぇ。夜な夜な淋しく枕を濡らすセレっち、てめぇよぉ!」
「……あたしは満たされてるから、いいって」セレスは呆れた眼差しでちゃっきーを見詰めた。
「うそ〜ん♪ 虚勢を張って強がりなんて、このおいらにゃぁ、通用しねぇのだぁ! しゃあ! 淋しさを紛らわせてあげるわぁ! ほい、おいらと共に転落人生を歩むのだ」
「いやじゃ」
セレスはちゃっきーの首根っこを掴まえるとひょーんと遙か彼方までぶん投げた。ちゃっきーは家々の屋根を飛び越えて、……いや、どこかの屋根の上に珍しくスマートに着地を果たしたようだった。ちゃっきーの超軽量ボディーならではの荒技だ。
「このっ、セレっちめぇ! 次、会う時はぜってぇ、許さねぇ、覚悟しとけ〜〜」
「うるさいって……」セレスは目を細めてボリボリと頭を掻いた。「何で、こう、いちいち面倒くさい奴ばかりあたしのまわりに集まってくるのかなぁ……」
“堪らない”を通り超えて、“どうしようもない”と言うのがセレスの正直な感想だった。半ば意気消沈気味に歩み始めたところへ、いつの間にか姿を消していたシルトが必死の形相で駆け戻ってきた。
「あ〜? 今度は一体何なのよぉ?」
セレスの横を通り過ぎたシルトを見て、視線を元に戻すととんでもないものがくっついてきた。
「あっ! うわっ、ごめんなさい。あ、や、追い掛けてこないで」
「おおっ?」セレスも回れ右してシルトと一緒に逃げ出した。
「だから、尻尾、踏んだのは悪かったって謝ってるのに!」
「うわっ! シルト、ちょっと、変なの連れて来ないでよ! あ、あたし、オオカミの扱いには慣れてるんだけど、い、犬は苦手なのよ〜〜」
「狩人の家系なのに、犬が苦手ってどゆこと?」
「どゆことって。こゆことよ。だって、小さい頃、いい子いい子しようと思ったら、右手をがっぷり噛みつかれたんだもの! それ以来、ダメなのよぉ。リボンちゃんは人語を解する変なオオカミだったから大丈夫だったんだけど」
「あ〜、それ、本人が聞いたら激怒間違いなし。大変なことになるよ?」
「いないんだから、いいでしょ? 抱き枕になってくれないあんなやつ、知らないんだもん」
「……おコちゃま……」シルトは目を細めて横目でセレスを見やり、口元を手で押さえた。
「そんなこと、シルトにだけは言われたくないっ!」
「それより、あの犬をどうにかしてよ、セレス。ワタシ、犬、嫌い」
「犬、嫌い? ハンッ、キミほどの魔力があればあんなの一撃でしょ?」
「あっそっか」シルトは急停止して、犬に向き直った。「え〜とぉ……」
シルトはあれこれと考えて、もっとも効果的な魔法を探す。けど、犬を追い払うだけに使うには周囲に甚大な被害をもたらすようなものばかりだ。シールド魔法なんて無意味だし、かといって、効果絶大、ダークフレイムなどを喰らわせて、死霊に呪われたのでは堪らない。
その時、シルトはいい考えをピンと思いついた。
「これでも喰らえ!」自信満々にシルトは叫んだ。
ぽひゅんとちょっぴりお間抜けな音がして、シルトの手のひらの辺りにポケットが開き、その中から何かおかしなものが飛び出してきた。
「……? 何、それ?」思わず問う。
「ワタシのずだ袋。必要なものはなぁ〜んでも入ってるの」得意げにシルトは微笑んだ。
「で、それは?」セレスはシルトが手にしたものを指さした。
「骨。そぉ〜れっ! どっかに行っちゃえ、犬っころ」
シルトは大きく振りかぶって、その骨を追い掛けてきた犬の背後に思い切りよく投げた。
「何で、骨なんかあるのよ……。しかし、ま、一丁上がり」
どこか釈然としないものがあるけれど、結果オーライ。飛んでいく骨を追い求めて去っていく犬を尻目に、シルトは再び走り出した。
と、そこへ久須那の追求を逃れたデュレが息を切らしながら追いついてきた。しかし、シルトの姿はすでに点。やっと追いついて、ようやく一息付けると思ったら、また走らなくちゃならない。
「……デュレ、久須那さんはどうだった?」セレスはデュレの瞳を見ずにそっと尋ねた。
「聞きたいですか?」デュレもシルトの行く先を見てセレスとは視線を合わせない。セレスはデュレの視界の隅っこで小さく頷いた。「万一、日付を越えたらセレスも一緒にとっちめてくれるそうです♪」深刻な表情をしていたデュレの顔がくるっと変わって煌びやかな笑顔になった。「もう、とっても満足です。これでわたしとあなたはある意味、運命共同体」
「あたしはちっとも良くないんだから! けど、ま、今日中に見つけて、シルトをなだめて、さらにデュレの報告書を提出に行けば、完璧っ。だよね?」
「まあ、一応、そう言うことになります……」
「ほほっ♪ じゃ、仕切直してレッツゴー!」
とは言ったものの、今日、何度目か忘れたけれど、また、シルトを見失っていた。けど、セレスはもはや気にしてはいない。とにかく、シルトの走っていった方向を目指すのみ。そうしたら、自然とシルトに追いつけるだろうと楽観的な考えをしていた。
セレスはトトンと地面を蹴って、靴の中で足の居場所を整えるとスタートした。体力勝負になるとデュレには負けない自信がある。だからといって、こういうことは無意味に疲れるから遠慮しておきたいのがセレスの本音だった。
「ちょっと、セレス、待ちなさいって。あ〜もうっ!」
地団駄も踏みたくなる。デュレはやむを得ずに駆け出して、セレスの横に並んだ。
「待ちなさいって言ってるでしょ。作戦会議、作戦を考えないと、闇雲にシルトを追い掛けてるだけじゃ埒が明きません。止まらないんだったら、力尽くでも止めてみせますっ」
と声高に叫んでみても、セレスは先に行くばかり。それどころか……。
「無理だって、体力はあたしの方があるもんね。それに余所見してたら、知らないよ」
セレスは意味深ににやり。デュレの少し先を走っていて、何かを避けたようだ。
「? それはどういう意味ですか? きゃっ!」
ガコンっ。デュレは半開きになっていたマンホールのフタに足を取られてど派手に転んだ。その様子を知って、セレスはわざわざ戻ってきた。
「へっへ〜んだっ。人を呪わば穴二つ! ざま見ろ。そいじゃ、先行ってるから、見失わないでね」
セレスは手をヒラヒラッとさせてデュレの脇を駆け抜けていく。
「ざま見ろですって、この。――思い知れ!」
デュレは身軽に走り去っていくセレスの背中に狙いを定めた。
「禁断の闇の領域より姿を現せっ! フォビドゥンハンマー」
「……? ?」セレスはただならならぬ空気を感じてキョロキョロと左右を見回し、最後に上を向いた。「うわっ、マジかい!」
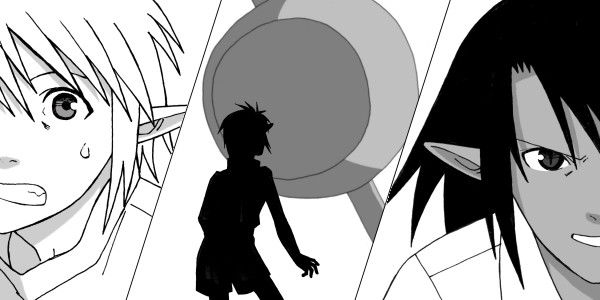
セレスの視界を直径三メートルはあろうかというハンマーに埋め尽くされた。しかも、そのハンマーはだんだん大きくなってくる。四メートル、五メートル? それは落下しながら巨大化しているようだった。セレスは逃げることさえ忘れて……、と言うよりも逃げ出したところで無意味なことを悟ったのだ。そして、ドゴォオオン。
地面から土煙が巻き起こり、それが晴れるとセレスはしっかりとハンマーの下敷きになっていた。
「くっそ〜、デュレめ。くそ真面目なキミがどうしてこんなふざけた魔法を知ってるんだよっ」
ハンマーの下から抜け出そうとセレスはジタバタ。しかし、ハンマーは地面に張り付いてしまったかのようにぴくりともせず、動きもしなければ転げもしない。かといって、ハンマーが重いかと言えば全然そんなことはない。まるで、ハンマーと地面と自分の身体が融合してしまったかのようなのだ。
「わたしに知らない事なんてありません」
デュレはお澄まししながら、セレスの背中を踏んづけて駆けていく。
「もぎゅ。――こらっ、踏ん付けるなっ!」
「あ〜もうっ! セレスのせいで見失った」
近くの十字路まで来て、デュレは悪態を付いた。シルトがどこを駆け回っていたかの手がかりは皆無だから、一度見失ってはシルトを再び見つけ出すのは至難の業なのだ。
「セレスっ! いいですか? わたしは右に行きます。あなたは真っ直ぐか左に行ってください」
デュレは振り返ると、まだ石畳に伏せているセレスに向かって指示を怒鳴った。
「そんなこと言うなら、今すぐ、助け起こせっ、この!」
文:篠原くれん 挿絵:晴嵐改
